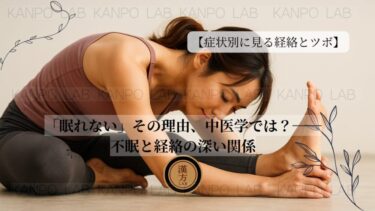目次
「冷え」を中医学で見ると?──陽気と血流を促す経絡とツボの知恵
手足が冷たい。夏でも靴下が手放せない。お腹がいつも冷えている──
そんな「冷え性」は、現代では多くの方が悩まされていますが、中医学では「陽気の不足」と「気血の滞り」によるものと考えます。
本記事では、冷えのタイプと関連する経絡・ツボ・漢方ケアを解説いたします。
🧠 Case:20代女性、手足が冷えて眠れない
夜になると足先が冷えて眠れない。生理不順や疲れやすさもあり。
これは陽虚+血虚+瘀血の傾向が見られ、経絡の冷えが進んでいる可能性があります。
📚 中医学における冷えの分類
- 陽虚型:全身が冷える、顔色が白い、尿が多い。陽気が不足して体を温められない。
- 血虚型:手足の冷え。皮膚が乾燥。血が足りず、末端まで温まらない。
- 瘀血型:冷えと痛みがセット。冷えた部位の血流が悪くなることで発生。
関与する経絡は、特に腎経・脾経・任脈・督脈が中心となります。
🔍 関連する経絡とツボ
🔸 足の少陰腎経(根源の陽気を司る)
- 太谿(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間。腎陽を補い、冷えを改善。
- 湧泉(ゆうせん):足裏の中心。生命力の源を刺激し、全身を温める。
🔸 足の太陰脾経(気血生化の源)
- 三陰交(さんいんこう):内くるぶし上4寸。脾・肝・腎の三経を調える。
- 血海(けっかい):膝の内側上部。血を養い、冷えや婦人科症状にも対応。
🔸 任脈・督脈(体幹の前後ライン)
- 関元(かんげん):へそ下3寸。元気・陽気を補う代表ツボ。
- 命門(めいもん):第二腰椎の下。体のエネルギーの扉を開く。
👐 セルフケアと養生法
- 太谿・三陰交への温灸:腎経・脾経を温めると全身がほぐれる。
- 足湯+内関や湧泉のマッサージ:足先から温めて陽気を引き出す。
- 腹巻き・温灸器:関元・中脘・命門など体幹のツボに熱を加える。
🌿 冷えに用いられる漢方処方
- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう):手足の強い冷えに。
- 真武湯(しんぶとう):腎陽虚によるむくみ・冷え・疲労感に。
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):瘀血による冷え・月経不順に。
📝 まとめ
冷え性は“気の力が弱っているサイン”です。
原因に応じた経絡やツボを選ぶことで、根本から温まる身体づくりができます。
次回は「不眠」をテーマに、経絡とツボの関係を掘り下げていきます。