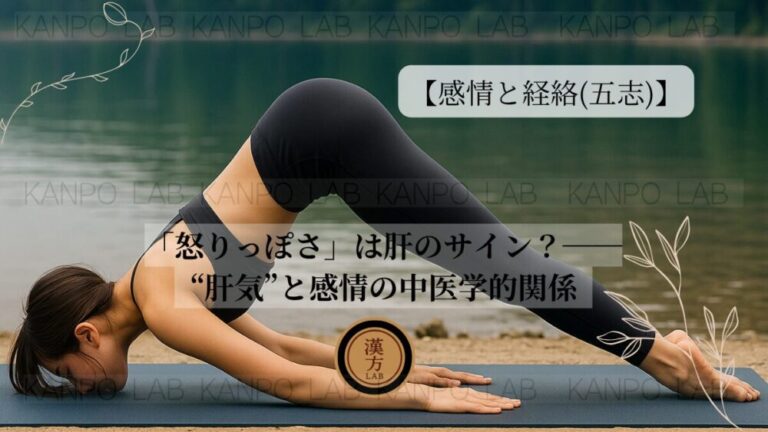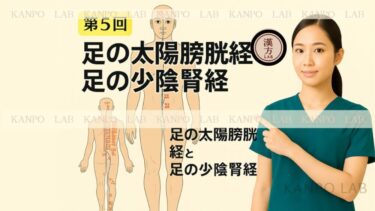目次
「怒りっぽさ」は肝のサイン?──“肝気”と感情の中医学的関係
なぜか最近、イライラすることが増えた。
小さなことにも怒りがこみあげてくる──。
それは、単なる性格ではなく、「肝」の不調が関わっているかもしれません。
🧠 Case:怒りやすいのはなぜ?
ある30代女性の例です。職場でのストレスが続き、些細なことに怒りがこみあげるようになった。月経前になると特にひどく、頭痛や胸の張りまで感じるように──。
中医学では、こうした怒りっぽさや情緒の不安定さは、「肝気の失調」と捉えます。では「肝気」とは一体何なのでしょうか?
📚 中医学でいう「怒」と肝の関係
中医学では、感情と臓腑の関係を「五志(ごし)」として整理しています。
その中で「怒(いかり)」は肝に属すとされ、「怒りすぎると肝を傷つける」「肝の不調は怒りを生みやすくなる」と考えられています。
肝は「気」を全身にめぐらせる“疏泄(そせつ)”という役割をもちます。ストレスが強くなるとこの疏泄がうまくいかず、「肝気鬱結(かんきうっけつ)」や「肝火上炎」といった病理状態に陥ります。
- 肝気鬱結:気のめぐりが滞り、イライラ・胸脇部の張り・ため息が多くなる
- 肝火上炎:怒りが激しく、顔が赤くなる・頭痛・口が苦いなどの症状
🔍 関連する経絡:足の厥陰肝経
肝の経絡である足の厥陰肝経は、足の親指から脚の内側を通り、肝臓や目、頭部へとつながっています。そのため、肝の不調があると、
- 側頭部の頭痛
- 月経前の胸の張り
- 目の充血・疲れ
などの症状も同時にあらわれます。
🌿 使われる漢方方剤と生薬
肝の疏泄を整えるには、気のめぐりをよくし、熱を冷ます方剤が使われます。
代表的な方剤:
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):怒り・イライラ・月経前症候群(PMS)に
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):怒りが激しく眠れないときに
- 抑肝散(よくかんさん):神経過敏・子どもの夜泣き・老人の怒りっぽさに
生薬例:
- 柴胡(さいこ)…肝気を通じる
- 香附子(こうぶし)…気滞を解消
- 牡丹皮(ぼたんぴ)…熱を冷ます
👐 セルフケア:怒りの感情を整えるツボと養生
肝の疏泄を助けるために、次のようなツボや生活ケアが有効です。
📍 おすすめの経穴(ツボ):
- 太衝(たいしょう):足の親指と人差し指の間。肝経の原穴で、怒りを鎮める。
- 期門(きもん):乳頭のやや下、胸の側。肝気の出入り口。
🌿 養生法:
- 深呼吸や瞑想で気の巡りを整える
- ハーブティー(ジャスミン、レモンバーム)で気を解く
- 夜更かしを避け、23時までに就寝
📝 まとめ
怒りっぽさは、自分の意志ではどうにもできないこともあります。
それは「気の巡り」という体のシステムに深く関係しているからです。
中医学の知恵では、感情と身体のつながりを大切にしながら、心とからだの両面をケアします。
次回は「うれしすぎて落ち着かない──“心”と喜びの関係」について見ていきましょう。