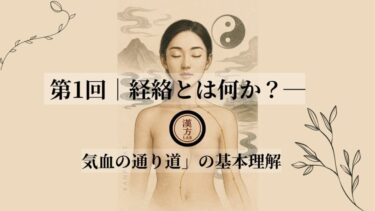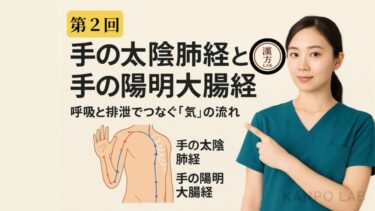手の厥陰心包経と手の少陽三焦経──“情緒”と“水路”を調える裏の主役たち
東洋医学には、「心」「肝」「脾」などの五臓とセットで、“補佐役”のような経絡も存在します。
それが今回取り上げる手の厥陰心包経(しんぽうけい)と手の少陽三焦経(さんしょうけい)です。
あまり知られていないこの2本の経絡ですが、情緒の安定・ホルモンバランス・水分代謝など、実はとても重要な働きを担っています。
🛡️ 心を守る「心包」──ストレスに反応する“内なる盾”
心包(しんぽう)は、“心を包む膜”という意味です。
中医学では心の外衛(がいえい)とされ、外界からのストレスや邪気が心に直接影響を与えないよう、バリアの役割を果たします。
手の厥陰心包経の走行と作用
- 起点:胸部の心包(胸中)→ 内腕の中心 → 中指へ
- 主な作用:情緒の調整・血流の調整・胸部の症状改善
- よく使うツボ:内関(ないかん)、だん中(胸骨中央)
心包経は、動悸、不安感、胸苦しさ、精神的な緊張に対応する経絡です。
イライラや不眠、胸のつかえ感を感じるときに、この経絡を整えることで心がふっと軽くなることがあります。
💧 三焦とは?──“水の通路”と全身の代謝管理
三焦(さんしょう)は、現代医学には存在しない中医学独自の概念です。
「上焦(胸)」「中焦(胃・脾)」「下焦(腎・膀胱)」に分かれ、水分・気・血の流れを調整する“器官間ネットワーク”のような存在です。
手の少陽三焦経の走行と作用
- 起点:薬指 → 手の外側 → 肘・肩 → 首 → 耳・こめかみへ
- 主な作用:リンパ循環・耳の症状・ホルモン調整・代謝改善
- よく使うツボ:外関(がいかん)、翳風(耳の後ろ)
三焦経は、耳鳴り・難聴・むくみ・冷え・更年期症状など、気血水の“流れ”が滞るときに重要な経絡です。
🔁 表裏の関係:心包と三焦のつながり
手の厥陰心包経と手の少陽三焦経は、「表裏の関係」にあるペア経絡です。
表=三焦経は“水路”、裏=心包経は“情緒”と血流の調整。
つまり「水と火のバランス」を調和させる、非常に重要な役割を果たしています。
- 心包経の乱れ → イライラ・胸の圧迫感・手のひらのほてり
- 三焦経の乱れ → 耳鳴り・むくみ・冷え・PMS・甲状腺の不調
🌿 セルフケア:感情と代謝を整えるツボ
- 内関(ないかん):ストレス緩和・乗り物酔い・胸のつかえに
- 外関(がいかん):水分代謝改善・代謝調整・全身の巡りに
- 翳風(えいふう):耳鳴り・難聴・首肩こりに
仕事・家庭・更年期・気圧変化──“なんとなく不調”の背後には、心包と三焦のアンバランスが隠れていることがあります。
📘 次回予告:「足の少陽胆経と足の厥陰肝経」──“巡り”と“解毒”を担う肝胆コンビ
次回は、イライラ・月経トラブル・消化不良などに関わる「肝」と「胆」の経絡へ。
自律神経と密接に関わる「気の巡り」について学んでいきます。
→ 続きを読む:足の少陽胆経と足の厥陰肝経
足の少陽胆経と足の厥陰肝経──“巡り”と“解毒”を担う肝胆コンビ
「なんとなくイライラする」「左側ばかり片頭痛がある」「月経前になると張って痛い」
こうした症状の背景には、肝と胆の経絡のバランスが関わっている可能性があります。
今回は、気の巡り・情緒・ホルモン・筋・目・胆汁の分泌と深く関わる、足の少陽胆経と足の厥陰肝経について学んでいきましょう。
🌀 肝の役割──「疏泄(そせつ)」で全身の巡りを整える
中医学における「肝」は、気血の流れをスムーズに保つ臓器です。
感情、血の貯蔵、生理の調節、目や筋肉の動きにも関与し、「肝気の詰まり」は全身の機能低下につながります。
足の厥陰肝経の走行と作用
- 足の親指から、足の甲・すね・太もも・下腹部・胸へと上行
- 肝の主治部位:生殖器、目、筋、爪、胸脇部
- よく使うツボ:太衝(たいしょう)、期門(きもん)
肝経が滞ると、イライラ、情緒不安定、PMS、乳房の張り、月経痛、便秘などが起こりやすくなります。
💡 胆の役割──決断力と消化を担う“リーダーの腑”
胆は中医学において、「決断を助け、勇気を出す」働きを持つ腑(ふ)です。
胆汁の貯蔵・分泌という役割に加え、思考・判断・行動力のバランスにも関係します。
足の少陽胆経の走行と作用
- 目尻から側頭部・首・脇腹・外腿・膝・ふくらはぎ・足の薬指へ
- 胆の主治部位:頭部側面、脇、外腿、胸脇苦満、めまい、耳鳴り
- よく使うツボ:陽陵泉(ようりょうせん)、足臨泣(あしりんきゅう)
胆経が滞ると、片頭痛、ストレス過多、脇の張り、外側の筋肉痛が出やすくなります。
🤝 肝と胆は“裏表”の関係
肝と胆は、五臓六腑の中でも「表裏関係」にあるペアです。
肝が「気血の貯蔵・巡らせる役」、胆が「その気血を方向づけ・排出する役」です。
- 肝気が詰まる → 胆汁が流れず → 消化不良・胸脇苦満
- 胆が弱る → 決断できない・優柔不断・夜間目が覚めやすい
🌿 セルフケアで“巡り”を整える
- 深呼吸・歩行・ストレッチで気の巡りを促す
- 香りのある食材(シソ・ミント・柑橘)で肝気を疏通
- 肝経のツボ:太衝、期門
- 胆経のツボ:陽陵泉、完骨
- 生活習慣:夜更かしを控え、感情の波を穏やかに保つ
肝胆の経絡を整えることは、感情・自律神経・ホルモン・筋肉・目・爪と多方面に影響を及ぼします。
日々のセルフケアで、“気の巡り”を滞らせないことが大切です。
📘 次回予告:奇経八脈──任脈・督脈と「補助回路」のしくみ
次回はいよいよ、正経十二経とは別の重要ルート「奇経八脈」に進みます。
任脈・督脈を中心に、体全体のバランスをどう調整しているかを学んでいきましょう。
→ 続きを読む:任脈・督脈と奇経八脈