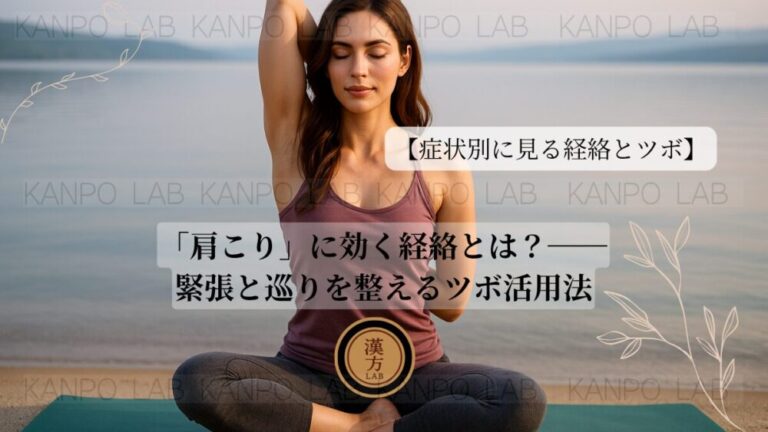目次
「肩こり」に効く経絡とは?──緊張と巡りを整えるツボ活用法
肩が重い、首が動かない、目の疲れとセットでつらい──
それは単なる筋肉の疲れではなく、経絡の“つまり”が原因かもしれません。
中医学では、肩こりは気血の停滞、特に「肝気鬱結」や「寒湿邪」によって生じると捉えます。
🧠 Case:デスクワークで肩が鉄板のように
40代男性。長時間のPC作業後、右肩がズシッと重くなる。マッサージ後もすぐに戻る。
これは胆経・小腸経の緊張や、気滞による経絡の詰まりが考えられます。
📚 中医学での肩こりの見方
肩こりは大きく分けて以下のような要因に分類されます:
- 気血の不足:血虚や気虚によって肩周辺に栄養が届かない
- 気滞血瘀:ストレス・怒りで肝気が巡らず、経絡が詰まる
- 寒湿の停滞:冷えや湿気により経絡が収縮・固まりやすくなる
特に注目すべき経絡は以下の通りです。
🔍 関連する経絡とツボ
🔸 足の少陽胆経(肩の横〜側頭部を通る)
- 肩井(けんせい):肩のいちばん盛り上がったところ。代表的な肩こりのツボ。
- 完骨(かんこつ):耳の後ろ下のくぼみ。側頭の緊張を和らげる。
🔸 手の太陽小腸経(首〜肩甲骨内側)
- 肩中兪(けんちゅうゆ):肩甲骨の内側。姿勢性の肩こりに。
- 天宗(てんそう):肩甲骨中央のくぼみ。深層筋の緊張を緩和。
🔸 手の三焦経(首筋・肩外側)
- 肩髃(けんぐう):肩前部。腕のだるさにも。
- 外関(がいかん):手首外側。気滞を流す通関穴。
👐 セルフケアの実践
- お灸や温熱療法:風寒湿が原因の肩こりには温灸が最適。風池・肩井などへ。
- ストレス型:太衝や合谷を使って肝気の流れを整える。
- 姿勢性:肩甲骨まわりのストレッチや、肩井・天宗への指圧を日常的に。
🌿 肩こりに使われる漢方処方
- 葛根湯(かっこんとう):風寒タイプの肩こりに。首筋・背中のこわばり。
- 疎経活血湯(そけいかっけつとう):寒湿による慢性の関節痛・筋肉痛に。
- 四逆散(しぎゃくさん):ストレス・怒り・肝気鬱結による肩こりに。
📝 まとめ
肩こりを単なる筋肉の疲労と捉えるのではなく、経絡の気血の停滞として見立てると、ツボ刺激や漢方がより的確に効きます。
「どの経絡に沿って張りがあるのか?」を観察して、自分に合ったケア法を見つけてみましょう。
次回は「腰痛」をテーマに、経絡から見る腰の不調の原因を探ります。