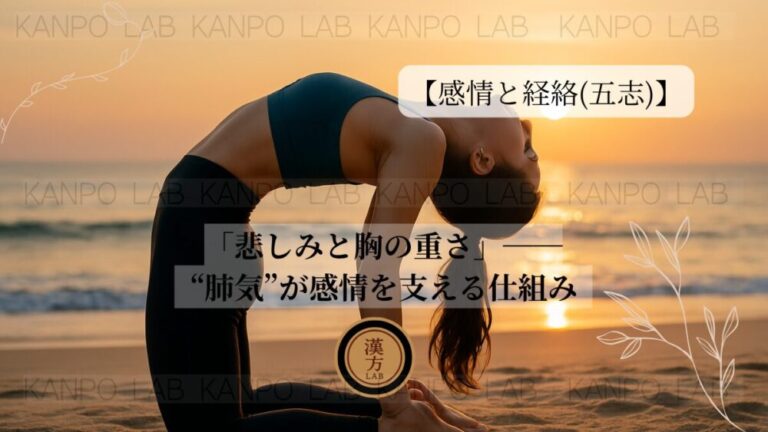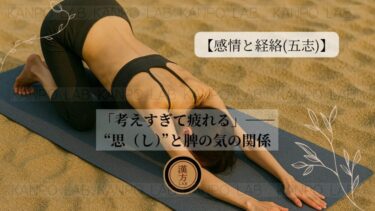目次
「悲しみと胸の重さ」──“肺気”が感情を支える仕組み
胸がしめつけられるように苦しい…。
泣きたくても涙が出ない、または涙が止まらない…。
それは「肺」の不調、「肺気の乱れ」が関係しているかもしれません。
🧠 Case:喪失感のあとに続いた不調
ある女性が、親しい家族を失った喪失感のあと、深く息が吸えず、胸が重い感覚に襲われた。
風邪をひきやすく、咳も長引くようになった──これは悲しみ=肺を傷るという五志の原則が示す典型的なパターンです。
📚 中医学でいう「悲」「憂」と肺の関係
五志のうち、「憂(ゆう)」と「悲(ひ)」はどちらも肺に属する感情とされます。
肺は「気の収斂(しゅうれん)」を司るため、悲しみによって肺の気が失調すると、呼吸器や情緒に影響が現れやすくなります。
特に「肺は気を主る」「肺は百脈を朝(あつ)める」とされ、全身の気と感情の中枢としての役割も持ちます。
🔍 関連する経絡:手の太陰肺経
肺経は胸から始まり、肩~腕~親指に向かって流れます。
そのため、肺の不調があると以下のような症状が見られます:
- 胸の重苦しさ・息苦しさ
- 慢性的な咳・喉の不快感
- 肌の乾燥・バリア機能の低下
🌿 使われる漢方方剤と生薬
肺の気を補い、感情を穏やかに整える処方が選ばれます。
代表的な方剤:
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう):肺気虚による倦怠感・息切れに
- 麦門冬湯(ばくもんどうとう):乾燥による空咳・喉の渇きに
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):胸のつかえ・情緒不安に
代表的な生薬:
- 麦門冬(ばくもんどう)…肺陰を潤す
- 人参(にんじん)…肺気を補う
- 五味子(ごみし)…収斂し肺を安定させる
👐 セルフケア:肺の気を整えるツボと生活養生
📍 ツボ:
- 太淵(たいえん):手首内側、肺経の原穴。気の巡りを促進。
- 中府(ちゅうふ):鎖骨下、胸の前面。肺の要穴として呼吸を整える。
🌿 養生法:
- 深呼吸やゆっくりした散歩で肺を開く
- 朝の白湯や生姜湯で肺の潤いを助ける
- 泣きたいときは無理に我慢せず、感情を出すことも大切
📝 まとめ
悲しみは誰にでも起こる自然な感情です。
しかしそれが続くと、身体の機能、とくに肺の働きを弱めてしまうことがあります。
中医学の知恵は、感情を否定するのではなく「感情と身体の関係性」に光を当て、調和を図ります。
次回は「恐れと腎のつながり」について解説してまいります。