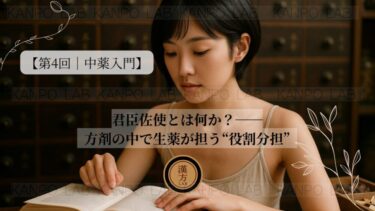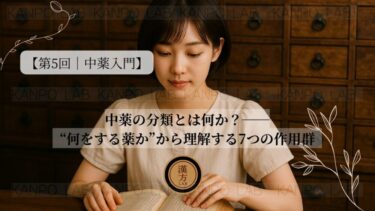🌿 地黄(じおう)|血と陰を養う、熟して深まる補腎の要薬
地黄(じおう)は、ゴマノハグサ科アカヤジオウの根を乾燥させた生薬で、血を補い、陰を養い、腎を潤す作用があります。
中医学では、「生地黄(しょうじおう)」「乾地黄」「熟地黄(じゅくじおう)」の三形態に分かれ、用途や働きが異なります。
🧾 基本情報
- 名称:地黄(じおう)
- 英名:Rehmannia root
- 学名:Rehmannia glutinosa
- 使用部位:根(生/乾燥/蒸し加工)
- 性味:甘・苦/寒(生)・微温(熟)
- 帰経:肝・腎・心経
- 分類:補血薬(熟地黄)/清熱涼血薬(生地黄)
🌿 主な効能と中医学的働き
地黄は加工形態により作用が大きく異なります。
- 生地黄: 清熱・涼血・滋陰の作用に優れ、熱病・出血・のぼせに。
- 熟地黄: 補血・滋陰・補腎の作用に優れ、虚弱・月経不順・めまい・腰痛に。
共通して「陰を補い、血を養う」作用がありますが、生地黄は急性症状、熟地黄は慢性虚証に使い分けられます。
📚 応用される処方例と役割
- 六味丸(ろくみがん): 熟地黄が君薬。腎陰虚に対して、補陰と同時に熱を抑える。
- 四物湯(しもつとう): 熟地黄・当帰・芍薬・川芎の補血代表処方。月経不順・貧血に応用。
- 知柏地黄丸(ちばくじおうがん): 熟地黄+清熱薬で構成。腎陰虚火旺によるほてり・寝汗に。
- 清営湯(せいえいとう): 生地黄を使用。発熱・舌の乾燥・出血傾向などに。
熟地黄は主に「滋養」のために用いられ、生地黄は「熱を冷ます」目的で選ばれます。どちらも肝・腎に深く作用する点が共通しています。
🧪 成分と現代医学的知見
地黄にはイリドイド配糖体(カタポール、レーマンニン)や多糖類、ステロール成分が含まれており、以下のような作用が報告されています:
- 造血促進作用(貧血の改善)
- 腎機能保護作用(糸球体保護)
- 血糖降下・肝保護作用
- 抗炎症・抗酸化作用(老化・更年期対策にも)
熟地黄は「血虚・腎虚」に対する基礎的な滋養素材として、エイジングケア的役割を持つ点が注目されています。
📖 古典における記載
『神農本草経』では「上品」に分類され、「五臓を補い、血を生じ、志を強くし、年を延ばす」と高く評価されています。
『本草綱目』では「腎を補い、髪を黒くし、精を固め、寒熱を除く」とされ、補腎・養血・若返り薬としても重視されてきました。
⚠️ 注意点と禁忌
- 熟地黄: 消化機能が弱い人では胃もたれ・軟便の原因となることあり。
- 生地黄: 寒涼性が強いため、冷え症・胃腸虚弱者には注意。
- 脾虚・痰湿・食欲不振時の投与は慎重に。
地黄は強力な滋養生薬ですが、「補う生薬は、消化に負担をかけやすい」という点に留意が必要です。
📝 まとめ
地黄は、補血・補陰・補腎の代表的な中薬であり、生と熟の使い分けで清熱・滋養どちらにも対応できる生薬です。
とくに熟地黄は月経トラブル・老化・更年期・慢性虚証など幅広い養生領域に使われ、体の土台をゆっくりと補ってくれます。
虚弱や冷え・めまい・生理不順など、「エネルギーが足りない」と感じる時、地黄はあなたの中に力を取り戻す手助けとなるかもしれません。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。地黄の働きについて少しでも理解が深まりましたら幸いです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿