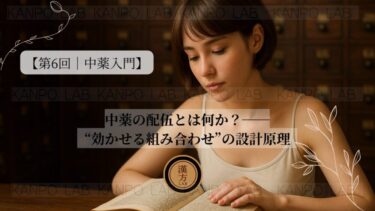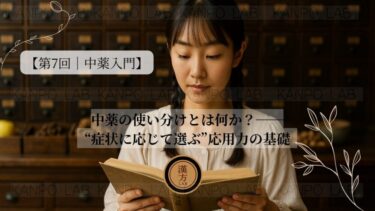🛡️ 黄耆(おうぎ)|体を守る「表気」の盾
黄耆(おうぎ)は、マメ科キバナオウギの根を乾燥させた生薬で、「気を補い、表を固め、体を守る」という働きから、古来より重宝されてきました。
特に「衛気(えき)」を強める作用に優れ、免疫力の低下・寝汗・慢性疲労・皮膚疾患など、幅広い虚証に用いられます。
🧾 基本情報
- 名称:黄耆(おうぎ)
- 英名:Astragalus root
- 学名:Astragalus membranaceus
- 使用部位:根
- 性味:甘/微温
- 帰経:肺・脾経
- 分類:補気薬(補益薬)
🌿 主な効能と中医学的働き
黄耆の最大の特徴は、「表気=体表のバリア機能」を強めることです。
これは単なる気の補充ではなく、外邪の侵入を防ぎ、体内の水分や汗を守る作用も併せ持ちます。
- 補気固表: 衛気(免疫・バリア機能)を高め、風邪をひきやすい体質の改善に。
- 止汗作用: 気虚による寝汗や自汗を抑える。
- 利水消腫: 脾虚によるむくみ、尿の出が悪いなどに。
- 托毒排膿: 膿を外へ出して創傷治癒を早める(補中有攻)。
人参や党参と並び、「補気三本柱」の一角を担いますが、黄耆は特に表に働く補気薬として独自性があります。
📚 応用される処方例と役割
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう): 黄耆と人参のダブル補気で、倦怠感・内臓下垂・汗・息切れに。
- 玉屏風散(ぎょくへいふうさん): 黄耆・白朮・防風で構成。体表の免疫を強化し、風邪を防ぐ。
- 黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう): 小建中湯に黄耆を加えたもの。気虚+冷え・胃腸虚弱に。
- 黄耆単用: 煎じ茶として風邪予防や疲労回復に。近年では健康茶素材としても人気。
処方内では「補気の臣薬」として使われることも多く、人参や当帰、柴胡などとの組み合わせで多彩な調整が可能です。
🧪 成分と現代医学的知見
黄耆にはアストラガロシド(Astragaloside)というサポニン類や、多糖体・フラボノイドが含まれ、以下のような作用が報告されています。
- 免疫活性化(T細胞・NK細胞促進)
- 抗酸化作用による抗老化・抗疲労
- 血糖降下・腎保護作用(糖尿病予防)
- 皮膚の創傷治癒促進
中医学の「補気固表」の概念と、現代の免疫調整・抗炎症作用が見事に一致する生薬といえるでしょう。
📖 古典における記載
『神農本草経』では「上品」に分類され、「久しく服すれば身を軽くし、老を延ばす」と記述されています。
『本草綱目』でも「膿を排し、表を固め、汗を止める」とされ、補いながらも邪を払う“補中有攻”の性質が高く評価されています。
⚠️ 注意点と禁忌
- 実熱がある場合: 補気薬の性質上、熱性疾患の急性期には適さない。
- 外邪が体内に残る時: 風邪の初期などでは「表を固めて邪を閉じ込める」可能性があるため慎用。
- 過剰使用により、ほてり・不眠などが現れることも。
黄耆は基本的に安全性の高い補気薬ですが、使用時期(タイミング)と体質の見極めが重要です。
📝 まとめ
黄耆は、単なる「気を補う」だけでなく、体のバリアを強め、守りを固める補気薬です。
風邪をひきやすい、汗をかきすぎる、慢性疲労が続く、皮膚の治癒が遅い……そんな方に寄り添う存在です。
人参が「根本の力を補う」のに対し、黄耆は「外からの影響を防ぐ」。
この両者を併せ使うことで、補気の真価が発揮されるのです。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。黄耆の特性について少しでも理解が深まりましたら幸いです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿