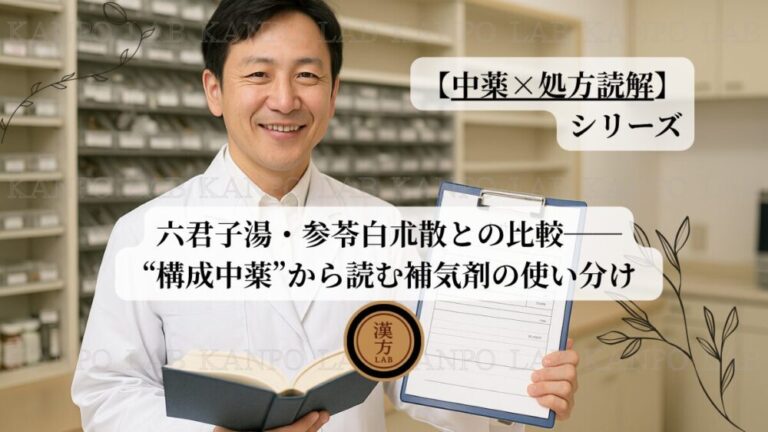【第3回】六君子湯・参苓白朮散との比較─“構成中薬”から読む補気剤の使い分け
補中益気湯を学んだあと、「他の補気剤とどう違うのか?」という疑問が湧いてくるはずです。
今回は補気剤の代表格である「六君子湯」と「参苓白朮散」との比較を通じて、中薬構成の違いから処方の使い分けを読み解いてまいります。
📚 補気剤三兄弟──基盤は「四君子湯」
まず、これらの処方はすべて「四君子湯(人参・白朮・茯苓・甘草)」を基盤に持つ補気剤です。
その上に、追加される中薬によって方向性が分岐します。
- 💡 補中益気湯:昇陽・清熱要素を追加(黄耆・柴胡・升麻など)
- 💡 六君子湯:理気・化痰を追加(陳皮・半夏)
- 💡 参苓白朮散:健脾・利水・補陰を追加(山薬・扁豆・蓮子など)
どれも「気虚」に対応しますが、それぞれの補い方・守り方に明確な違いがあるのです。
🧪 六君子湯──「胃気虚+気滞・痰湿」に
六君子湯は、四君子湯に陳皮・半夏を加えた処方です。
この2味の役割は、脾胃の働きを促進しつつ、痰や気滞を除くこと。
- 陳皮:理気・化痰・調中
- 半夏:乾湿化痰・止嘔
つまり、補うだけでなく“滞りを取り除く”構造となっており、胃のもたれ・食後の膨満・口内の粘つきなどを伴う「脾胃虚弱+気滞痰湿」のケースに最適です。
🌾 参苓白朮散──「脾虚+水湿+下痢・慢性疲労」に
参苓白朮散は、四君子湯に健脾補陰・利水化湿の生薬を多く加えています。
- 山薬・扁豆:補脾+健胃+化湿
- 蓮子・薏苡仁:止瀉・利水
- 桔梗:肺気を通じ、補気の全身作用を助ける
補気に加えて「脾虚による湿滞・下痢」に対応する守りの構造があり、長期の慢性疲労や術後の体力低下、軟便傾向が続く患者に用いられます。
📈 比較まとめ:構成中薬が示す“補気の方向性”
| 処方名 | 追加中薬 | 主な適応タイプ |
|---|---|---|
| 補中益気湯 | 黄耆・柴胡・升麻・当帰など | 中気下陥・倦怠・無力・脱肛 |
| 六君子湯 | 陳皮・半夏 | 胃腸虚弱+食後膨満・胃もたれ |
| 参苓白朮散 | 山薬・蓮子・薏苡仁・扁豆 など | 慢性疲労・軟便・食欲不振 |
同じ「補気剤」でも、補い方(昇提・調気・固表・利湿)によって適応がまったく異なるのです。
🔍 構成中薬を見ることで初めて見える“鑑別”
処方名だけで選ぶと見落としがちな微妙な違いも、構成中薬を見れば明らかになります。
– 昇陽が必要 → 補中益気湯
– 気滞・痰湿が強い → 六君子湯
– 脾虚による水湿・下痢傾向 → 参苓白朮散
これはまさに、中薬から処方を読み解く“応用実践”の第一歩です。
📘 まとめ|構成中薬から“補気剤”を使い分ける
今回は補気剤の代表的な3処方を構成中薬の違いから読み解きました。
中薬が示す方向性を読み取ることで、同じ補気剤でも「誰に、どのタイミングで」使うかがより明確になります。
今回はここまで。次回の記事もお楽しみに。もしご興味ある方は、他の記事も下記から選んでお読みくださいね。
🔧 補足情報
-
各処方の君臣佐使分類は一部文献で見解が異なるため、統合的見地に基づき構成。
-
臨床鑑別のポイントは、各症状の訴え(下痢傾向・痰湿・昇提力低下)に応じた配伍重視の視点で記述。
-
生薬の分類(補気薬・利水薬・理気薬など)は中薬学の標準的分類に準拠。
この記事の分類
- シリーズ分類:【中薬応用実践シリーズ】
- 効能治法分類:補気(ほき)
- 五臓六腑分類:中焦