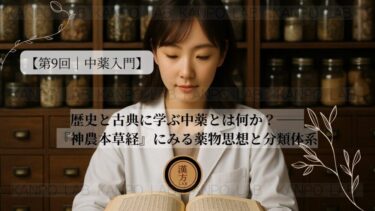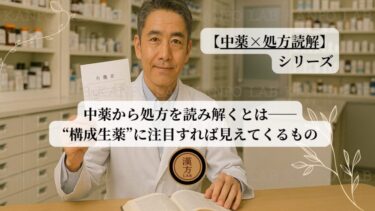🌾 白朮(びゃくじゅつ)|脾を補い、水をさばく、健脾の柱
白朮(びゃくじゅつ)は、キク科オケラまたはオオバナオケラの根茎を乾燥した生薬で、中医学では脾を健やかにし、気を補い、湿を除く働きで知られています。
「補気薬」に分類されますが、特に脾虚によるむくみや下痢、食欲不振などに適応し、補気と利水を兼ね備えた重要な中薬です。
🧾 基本情報
- 名称:白朮(びゃくじゅつ)
- 英名:Atractylodes rhizome
- 学名:Atractylodes macrocephala または Atractylodes lancea
- 使用部位:根茎
- 性味:苦・甘/温
- 帰経:脾・胃経
- 分類:補気薬(健脾薬・利水薬を兼ねる)
🌿 主な効能と中医学的働き
白朮は、主に脾を補い、水湿をさばくことを目的に使われます。
脾は「気と水の運化」を司るため、脾虚になると気虚だけでなく湿がたまりやすくなります。
- 健脾益気: 脾虚による倦怠感・食欲不振・胃のもたれに。
- 燥湿利水: むくみ・水様便・排尿困難などに。
- 止汗作用: 気虚による自汗・寝汗に。
- 安胎作用: 脾虚による妊娠中の不正出血・胎動不安に。
特に、体が重い・だるい・胃がもたれる・軟便・むくみなどの「脾虚湿盛」の症状にぴったりの生薬です。
📚 応用される処方例と役割
- 六君子湯(りっくんしとう): 補中益気湯の一種。白朮が脾気を補い、湿を除く要薬。
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう): 人参・黄耆・白朮で脾気を補い、内臓下垂にも対応。
- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう): 白朮・茯苓で水の停滞をさばき、めまいや立ちくらみに対応。
- 帰脾湯(きひとう): 脾と心を同時に補う処方。白朮が脾を支え、気血を生じやすくします。
白朮は補気作用に加えて「湿を除く」ため、補って滞らせない理想的な補薬ともいえます。
🧪 成分と現代医学的知見
白朮にはアトラクチロン(Atractylenolide)などの精油成分や、多糖類が含まれており、以下のような作用が確認されています:
- 胃腸機能の調整(消化管運動促進・腸管吸収改善)
- 抗炎症作用(特に腸管・関節・皮膚の炎症に)
- 免疫調整作用
- 利尿・抗浮腫作用
これにより、現代でも機能性ディスペプシア・過敏性腸症候群・むくみ・胃腸炎などの補助療法として注目されています。
📖 古典における記載
『神農本草経』では「上品」に分類され、「脾胃を補い、湿を除き、安胎に働く」と記載。
『本草綱目』では「気を益し、尿を利し、腸を健やかにする」とされ、補気・利水の両面に通じた生薬として評価されています。
⚠️ 注意点と禁忌
- 陰虚内熱: 潤いが不足しているタイプには、白朮の乾燥性が逆効果になることあり。
- 実熱証: 急性の炎症・発熱時には慎重投与が望ましい。
- 過剰使用で口の渇き・のぼせ・便秘が起こることがあります。
補気・利水は万能ではないため、体質に合わせて使うことが重要です。
📝 まとめ
白朮は、脾の気を補うだけでなく、余分な湿を取り除いて巡りを整えるという特性を持ちます。
「補いながらも滞らせない」「元気をつけて胃腸を立て直す」──そんな中薬を探している方に、最適な存在です。
気虚で食欲がない、むくみがちな体質、疲れやすい胃腸……そういった不調が気になるとき、白朮がそっと背中を押してくれるかもしれません。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。白朮の働きについて少しでも理解が深まりましたら幸いです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿