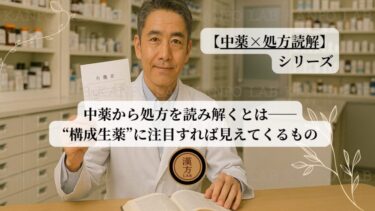🌾 蒼朮(そうじゅつ)|湿を除き脾を立て直す、燥湿の名手
蒼朮(そうじゅつ)は、キク科のホソバオケラ(Atractylodes lancea)の根茎を乾燥した生薬で、脾を健やかにし、体内の湿を除く作用を主とします。
補気薬の一種ですが、特に「燥湿」と「散寒」の力が強く、白朮(びゃくじゅつ)とは異なる応用面を持ちます。
🧾 基本情報
- 名称:蒼朮(そうじゅつ)
- 英名:Atractylodes rhizome (green)
- 学名:Atractylodes lancea
- 使用部位:根茎
- 性味:辛・苦・温
- 帰経:脾・胃経
- 分類:補気薬(燥湿健脾薬/祛湿薬に近い働き)
🌿 主な効能と中医学的働き
蒼朮は白朮と同じく脾を補う働きを持ちますが、それ以上に湿をさばく力(燥湿)に特化しています。
そのため、湿気が体内にたまって起こる症状──頭重・関節痛・浮腫・食欲不振などに対して有効です。
- 燥湿健脾: 食欲不振、胃もたれ、湿による軟便や吐き気に。
- 除風散寒: 関節痛・冷え・身体の重だるさに。
- 明目作用: 頭重感・目のかすみなど、湿困清陽による症状にも応用。
湿困脾胃(しっこんひい)=湿が脾胃に停滞して働きが落ちているタイプに最適な処方薬です。
📚 応用される処方例と役割
- 平胃散(へいいさん): 蒼朮が君薬。脾胃の湿滞による胃もたれ・腹部膨満に。
- 香蘇散(こうそさん): 蒼朮が脾を助け、湿を除いて気を巡らす。風寒+胃腸症状に。
- 藿香正気散(かっこうしょうきさん): 食あたり・嘔吐・下痢などに。蒼朮が湿を取り除く補助役。
- 二朮湯(にじゅつとう): 蒼朮+白朮のコンビで、燥湿+健脾を強化。関節痛や重だるさに。
蒼朮は「気を補いながら湿を祛す」バランス型として、他の生薬と配伍されることで真価を発揮します。
🧪 成分と現代医学的知見
蒼朮にはアトラクチロン(Atractylone)などの精油成分が豊富で、以下のような作用が報告されています:
- 消化機能亢進作用(胃腸運動促進)
- 利尿・抗浮腫作用(体液調整)
- 抗炎症作用(胃腸・関節・皮膚)
- 抗菌・抗真菌作用(湿性皮膚炎にも応用)
白朮より精油成分が多く、燥性が強いため、現代でも湿気・冷え・水毒的体質への応用が注目されています。
📖 古典における記載
『本草綱目』には「湿を除き、風を散じ、脾を強くし、食を進める」と記されており、健脾・祛湿・散寒の三位一体の効能が古くから認識されていました。
また、眼病やめまいへの応用記述もあり、「目を明らかにする」作用も伝えられています。
⚠️ 注意点と禁忌
- 陰虚・血虚: 潤いが不足している体質には燥性が強すぎる可能性があります。
- 実熱・乾燥傾向: 潤いが足りないタイプでは便秘や喉の渇きが悪化することも。
- 長期使用によって、乾燥性副作用(皮膚・腸)を招く可能性があります。
湿が強いタイプに短期集中で使用するのが基本です。白朮との併用でバランスをとることも有効です。
📝 まとめ
蒼朮は、湿をさばき脾を補う「燥湿健脾」の名手。
白朮よりも湿邪除去に優れており、「重だるい」「胃がもたれる」「むくみやすい」など、湿がからむ不調におすすめです。
脾を立て直し、水をさばき、身体を軽くする──
そんな蒼朮の力を、ぜひ日々の不調ケアに活かしてみてください。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。蒼朮について少しでも理解が深まりましたら幸いです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿