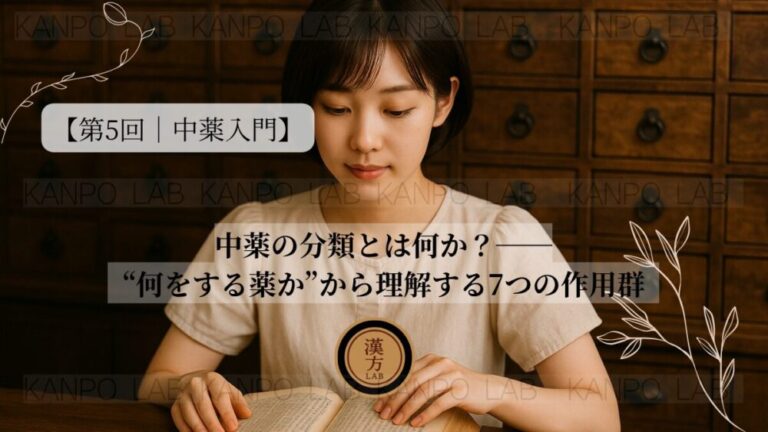【第5回|中薬入門】中薬の分類とは何か?──“何をする薬か”から理解する7つの作用群
漢方薬や薬膳に使われる中薬。では、どのように整理されているのでしょうか?
この記事では、中薬の「功効分類(作用分類)」に焦点をあて、代表的な7つの薬群とその特徴・例をやさしく解説いたします。
🎬 はじめに:目的別に“チーム”があるという発想
薬局の棚には、「解熱薬」「鎮痛薬」など用途ごとに分類された薬が並びますよね。
中薬も同じく、“何をする薬か”という目的別にグループ化されています。
この分類法を「功効分類」と呼びます。
つまり、作用・効能に基づいて中薬をグループ化したもの。
それぞれのグループには、共通の働きや使用場面があるのです。
📘 中薬の分類とは?──代表的な7分類
中薬の分類にはいくつかの方式がありますが、もっとも基本的で臨床にも活用されるのが「功効分類」です。
ここでは代表的な7分類を取り上げます。
- 補益薬(気・血・陰・陽を補う)
- 解表薬(風邪などの表証を発散)
- 清熱薬(熱・炎症を冷ます)
- 理気薬(気の巡りを良くする)
- 活血化瘀薬(血流を促進し瘀血を除く)
- 化湿薬・利水滲湿薬(湿邪を取り除く)
- 鎮静安神薬(心神不安や不眠に用いる)
この他にも「収渋薬」「瀉下薬」「温裏薬」などがありますが、初学者向けには上記7群で体系をつかむのが有効です。
🧪 1. 補益薬──不足を補い、体を整える
代表:人参、黄耆、当帰、熟地黄、鹿茸など
気虚・血虚・陰虚・陽虚に応じて分類されます。疲労・虚弱体質・慢性疾患の補強に用いられます。
🌀 2. 解表薬──外からの“風邪”を追い出す
代表:麻黄、桂枝、紫蘇葉、葛根、薄荷など
風寒・風熱など表証に対して発汗や解熱を促します。風邪の初期、発熱、悪寒に用いられます。
🔥 3. 清熱薬──内熱・炎症を鎮める
代表:黄連、黄芩、石膏、知母、金銀花など
熱証(のぼせ、口渇、イライラ)に対し、熱を冷ます作用を持ちます。
💨 4. 理気薬──気の巡りを改善する
代表:陳皮、香附子、木香、青皮など
ストレス・食滞・月経不順などの「気滞」によく使われます。気分の抑うつや胃腸のもたれにも有効です。
🩸 5. 活血化瘀薬──滞った血を動かす
代表:丹参、川芎、紅花、桃仁、牡丹皮など
瘀血(血の滞り)による痛み・生理不順・打撲傷などに使用されます。
💧 6. 化湿薬・利水滲湿薬──湿邪を除去する
代表:茯苓、沢瀉、猪苓、蒼朮、藿香など
むくみ、湿疹、下痢、関節の重だるさなど「湿」の症状に対応します。
🛏️ 7. 鎮静安神薬──心を鎮め、睡眠を助ける
代表:竜骨、酸棗仁、遠志、夜交藤など
不眠、不安、動悸などに用いられます。現代では心療内科的な症状にも活用されます。
🔗 分類の意義:処方理解・応用・鑑別に不可欠
中薬の分類を知ることは、処方の構造を理解し、自分に合う薬や方剤を選ぶ土台となります。
また、作用重複や使いすぎを避けるための指標にもなります。
次回は、この分類を“どう組み合わせるか”という設計思想──配伍(はいご)について学んでいきましょう。
▶️ 第6回|中薬の配伍とは?記事へ進む
この記事の分類
- シリーズ分類:【中薬入門シリーズ】