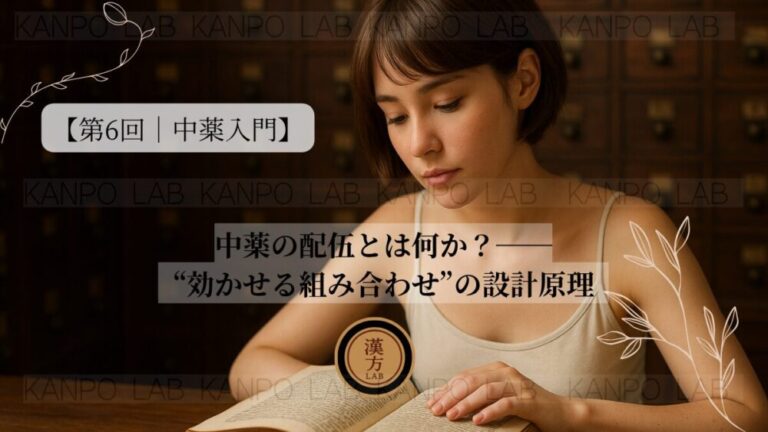【第6回|中薬入門】中薬の配伍とは何か?──“効かせる組み合わせ”の設計原理
「漢方薬って、なんでいくつも生薬を混ぜるの?」
そんな疑問に答えるキーワードが「配伍(はいご)」です。
本記事では、中薬を組み合わせて効果を最大化する“7つの配伍パターン”を具体例とともに解説いたします。
🎬 はじめに:1+1が3になる世界
料理のレシピでも、食材をどう組み合わせるかで味が変わりますよね。
漢方でも同じで、生薬の“組み合わせ”が効果を左右します。
その考え方が「配伍(はいご)」──中薬の組み合わせ設計理論です。
たとえば、同じ「人参」でも、
・甘草と組めば胃腸に優しく
・黄耆と組めば補気力がUP
・半夏と組めば嘔吐にも効く…
このように、生薬は配伍によって別の顔を見せるのです。
📘 配伍とは何か?──生薬の「組み合わせ設計」
「配伍(はいご)」とは、中薬同士の相性・補完・調和を考慮しながら組み合わせることを意味します。
これは方剤設計の核となる考え方で、古くから「七情合和」と呼ばれる7つの基本パターンが整理されています。
🧪 七情合和|7つの配伍パターン
- 単行(たんこう):1種のみで用いる。明確な証や単純な疾患に。
- 相須(そうす):同じ効能の中薬同士で効果を強化する(例:人参+黄耆)。
- 相使(そうし):一方が他方の効果を助ける(例:柴胡+黄芩)。
- 相畏(そうい):一方が他方の毒性・副作用を抑える(例:生姜で半夏の刺激を緩和)。
- 相殺(そうさつ):副作用を打ち消す関係(例:甘草で大黄の瀉下力をコントロール)。
- 相反(そうはん):配伍禁忌とされる関係(例:甘草+甘遂など)。
- 相悪(そうお):一方が他方の効能を弱める・害する(例:丁香と郁金)。
これらを理解することで、中薬の「科学的な組み合わせ設計」が可能になります。
🔍 実例で学ぶ配伍:補中益気湯の場合
補中益気湯では、多くの配伍の原則が同時に活かされています:
- 人参+黄耆(相須):補気力UP
- 当帰+陳皮(相使):補血と気の巡りの調整
- 生姜+甘草(相畏):消化器への刺激を緩和
このように、配伍は処方の立体的な設計思想そのものなのです。
⚖️ 配伍の目的:効能強化・毒性軽減・作用調整
配伍は単なる“混ぜ合わせ”ではありません。主に次のような目的で行われます:
- ✅ 主作用の強化
- ✅ 補助作用の追加
- ✅ 副作用や刺激の抑制
- ✅ 相互バランスの調整
- ✅ 対象臓腑への誘導(使薬的役割)
これらを考慮することで、個々の体質や症状に合わせた“オーダーメイド処方”が可能になるのです。
📚 応用の広がり:薬膳・OTC漢方にも配伍の視点を
薬膳では、甘・辛の食材で補いつつ、苦味で清熱するような配伍が行われます。
またOTC漢方でも、メーカーの製剤設計に配伍思想が応用されています(例:安中散=桂皮+延胡索)。
📘 次に読むべき記事|中薬の使い分け──応用力を高める処方選択術
次回は、いよいよ「学んだ知識をどう使うか?」という視点へ進みます。
同じ症状でも「どの方剤を選ぶか」──応用力を養う使い分けの考え方を深めましょう。
▶️ 第7回|中薬の使い分けとは?記事へ進む
この記事の分類
- シリーズ分類:【中薬入門シリーズ】