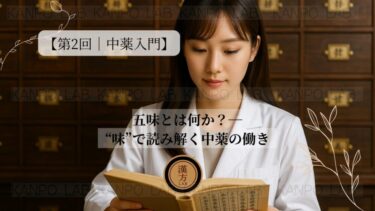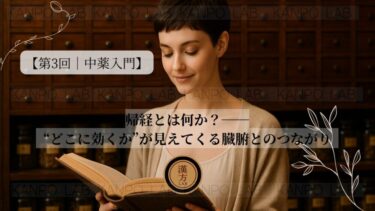🍇 五味子(ごみし)|五味を宿す、体の“漏れ”を防ぐ実
五味子(ごみし)は、その名の通り「酸・甘・苦・辛・鹹(かん)」の五つの味を併せ持つ果実です。
中医学では主に肺と腎に帰経し、体の中から漏れ出てしまう気・津液・精をしっかりと守るために使われる生薬で、「収渋薬(しゅうじゅうやく)」に分類されます。
🧾 基本情報
- 名称:五味子(ごみし)
- 英名:Schisandra fruit
- 学名:Schisandra chinensis
- 使用部位:成熟果実(乾燥)
- 性味:酸・甘/温
- 帰経:肺・腎・心経
- 分類:収渋薬(斂肺止咳薬)
🌿 主な効能と中医学的働き
五味子は主に「斂肺止咳」「益気生津」「滋腎寧心」という作用を持ち、肺・腎・心に潤いと安定をもたらします。
- 斂肺止咳: 慢性的な空咳・喘息に対して、肺気の漏れを防ぎ、咳を鎮めます。
- 益気生津: 気を補いながら津液の生成を助け、口渇や汗の出すぎに作用します。
- 滋腎寧心: 腎陰を補い、心神を安定させ、不眠や夢の多さにやさしく働きます。
特に「気や津液が漏れやすいタイプ(肺虚・腎虚)」の方に適しており、咳・寝汗・頻尿・夢精などの症状に対応します。
📚 応用される処方例と役割
- 生脈散(しょうみゃくさん): 人参・麦門冬・五味子の三薬で構成され、気陰両虚による脱力感・息切れ・動悸に。
- 炙甘草湯(しゃかんぞうとう): 心悸・不整脈・動悸に用いられ、五味子が心神を安定させる補助役。
- 帰脾湯(きひとう): 心脾両虚の不眠・健忘・寝汗に。収渋・安神作用を担う。
- 五味子単味使用: 水で煮出して「五味茶」として気虚・疲労回復・肺の潤い補給に用いられることもあります。
これらの処方において、五味子は気や陰を「補う」だけでなく「守る」役割も持っており、特に「失われやすいものを内に引き戻す」点で貴重な存在です。
🧪 成分と現代医学的知見
五味子にはリグナン類(schisandrinなど)が豊富に含まれており、現代では以下のような作用が研究されています:
- 抗酸化・抗疲労作用(肝機能のサポートやストレス耐性向上)
- 中枢神経安定作用(不眠・集中力低下への改善効果)
- 抗アレルギー作用(ヒスタミン遊離抑制)
- 呼吸機能調整(慢性咳嗽や気管支炎への応用)
五味子は**「肝・心・肺」など多経絡への応用可能性**を持ち、補うだけでなく“引き締める”という独自の機能が注目されています。
📖 古典における記載
『神農本草経』では「上品」に分類され、「肺を補い、腎を強くし、精を養い、心を安んず」と記されています。
また『本草綱目』では、五つの味が五臓に作用し、虚を固める要薬として高く評価されました。
⚠️ 注意点と禁忌
- 風寒咳嗽: 実邪(風寒・風熱など)の咳には適さず、外感症状がある時は慎用。
- 実熱内盛: 陰虚火旺の状態には単独使用で熱をこもらせるおそれあり。
- 過量使用による胃腸障害・のぼせ感に注意。
基本的には穏やかで安全な生薬ですが、「外に出すべきものを収めてしまう」性質ゆえ、**外感病時は使用を避けるのが原則**です。
📝 まとめ
五味子は、失いやすい「気・津液・精・神」を守るための守護薬のような存在です。
咳が長引いてなかなか治らない方、汗や尿が出すぎて疲れやすい方、夢が多くて眠りが浅い方など、体内の“もれ”に困っている方には、五味子がやさしく力を貸してくれます。
現代においても五味子茶やサプリメントなどの形で取り入れやすく、古典と現代の橋渡しをするような生薬です。
五つの味に込められたちから──あなたの体にも、そっと届くかもしれません。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。五味子について少しでも理解が深まりましたらうれしいです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿