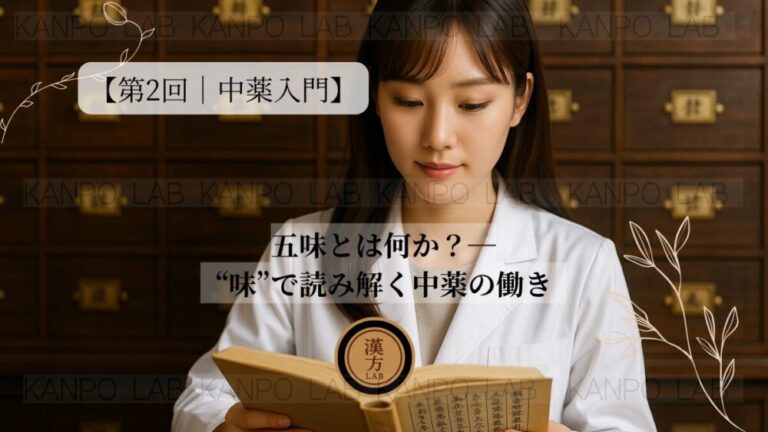【第2回|中薬入門】五味とは何か?─“味”で読み解く中薬の働き
「薬の“味”が効き方を決めるって、本当?」「苦い薬は本当に“冷やす”の?」
そんな素朴な疑問に応える鍵が、中医学の基本概念「五味(ごみ)」にあります。
この記事では、五味の意味と役割、実際の生薬・方剤での使われ方をわかりやすく解説いたします。
🌿 冒頭ストーリー:「甘いものは元気が出る」──直感と中薬の共通点
疲れたとき、つい甘いものに手が伸びる──そんな経験はありませんか?
実はこれ、体が自然と「甘=補う」ことを知っている証拠。中医学では、まさに味=性質と考えます。
中薬においても、「苦い薬は熱を冷ます」「辛い薬は発散させる」など、五つの“味”が薬の作用を決定するのです。
📘 五味とは?──中薬における5つの基本的な“味”の概念
中薬の「五味」とは、薬の味に宿る五つの作用傾向のことを指します。具体的には:
- 🌶️ 辛(しん):発散・行気・活血
- 🍬 甘(かん):補益・調和・緩和
- 🍋 酸(さん):収斂・固渋
- ☕ 苦(く):清熱・燥湿・瀉下
- 🧂 鹹(かん):軟堅・潤下・散結
この五味は、単なる味覚ではなく作用傾向=治療方針の軸として使われます。
🔍 五味の作用を具体例で理解する
1. 🌶️ 辛味(しんみ)
発散・気血の流れをよくする。風邪の初期や冷えに使用され、代表生薬は「生姜」「桂皮」など。
2. 🍬 甘味(かんみ)
補益・滋養・調和の働きがある。虚弱・疲労・胃腸虚弱などに。「人参」「甘草」などが代表例。
3. 🍋 酸味(さんみ)
収斂・固渋作用で、汗・尿・精液の漏れなどを防ぐ。「五味子」「山茱萸」など。
4. ☕ 苦味(くみ)
清熱・燥湿・瀉下などの働き。「黄連」「黄柏」など、炎症・熱証に使われる。
5. 🧂 鹹味(かんみ)
硬いものを柔らかくする(軟堅)・便通を助けるなど。「牡蛎」「昆布」「海藻」などが代表。
⚖️ 補足:淡味(たんみ)という“第六の味”
古典にはないものの、現代中医学では「淡味(たんみ)」も補助的に扱われます。
利尿・滲湿作用を持ち、「茯苓」「冬瓜子」などがこれに該当します。
🧪 方剤での五味の活用──バランスが大切
五味は、単独ではなく処方全体の構成で役割を果たします。
たとえば、補中益気湯には:
- 人参・甘草(甘):補益
- 陳皮(辛):行気・調和
- 黄芪(甘+微鹹):気を補い持ち上げる
このように、味で処方のバランスを取り、複数の作用を同時に実現しています。
💡 五味と五臓の関係──内臓への“帰属”
五味はそれぞれ、特定の臓腑と結びついています(帰経にも関係):
- 酸 → 肝
- 苦 → 心
- 甘 → 脾
- 辛 → 肺
- 鹹 → 腎
この理論は、次回扱う「帰経」と深く関係しており、「どの臓器に効かせるか」という視点を補強します。
📘 まとめ|“味”を知れば中薬の使い方が見えてくる
五味とは、中薬の個性を決める“サイン”であり、薬効の目安でもあります。
味覚だけでなく、作用・対象臓器・使用目的まで含むのが中医学の深みです。
次回は、いよいよ「どこに効かせるか?」を示す指標──「帰経(きけい)」について学びます。
▶️ 第3回|帰経とは?記事へ進む