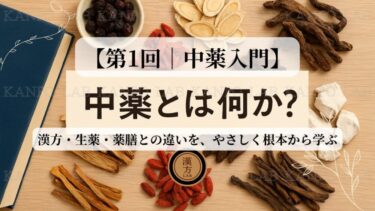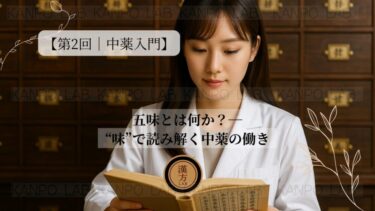🌱 麦門冬(ばくもんどう)|肺と胃を潤す、乾きに寄り添う根の力
麦門冬(ばくもんどう)は、ユリ科ジャノヒゲの根を乾燥させた生薬で、主に「養陰潤肺(よういんじゅんはい)」に用いられます。
乾いた咳や喉の渇き、寝汗、微熱、口内の乾燥など、体内の「陰」が不足したことで生じる症状にやさしく働きかける滋養薬です。
🧾 基本情報
- 名称:麦門冬(ばくもんどう)
- 英名:Dwarf Lilyturf Tuber
- 学名:Ophiopogon japonicus
- 使用部位:根の肥大部(塊根)
- 性味:甘・微苦/微寒
- 帰経:肺・胃・心経
- 分類:養陰薬(清熱潤燥)
🌿 主な効能と中医学的働き
麦門冬の代表的な効能は、「潤肺養陰(肺を潤し、陰を補う)」と「益胃生津(胃を滋養して津液を増やす)」です。
陰虚によって津液(しんえき)が不足し、乾き・ほてり・空咳・微熱・不眠などが生じたときに使用されます。
- 潤肺止咳: 乾燥した咳、少痰または無痰の空咳に。
- 養胃生津: 胃陰虚による口渇・口内乾燥・微熱に。
- 清心除煩: 心陰虚により起こる不眠やイライラ、舌の乾燥に。
肺・胃・心の三経に潤いを与えることから、幅広い陰虚タイプに応用されます。特に乾きによるトラブルに適応します。
📚 応用される処方例と役割
- 麦門冬湯(ばくもんどうとう): 空咳・痰が少ない・喉の乾燥・微熱など、肺陰虚の症状に対応。主薬として麦門冬が活躍。
- 滋陰至宝湯(じいんしほうとう): 心陰虚による不眠・煩熱に。麦門冬が心火を冷まし、潤いを補う。
- 生脈散(しょうみゃくさん): 気陰両虚に用いられ、人参と麦門冬の組み合わせで元気と潤いを補う。
- 天王補心丹(てんのうほしんたん): 陰虚による心神不安・健忘・動悸に。滋陰安神の補助として麦門冬が配合。
これらの処方では、麦門冬は陰液の補充と熱の抑制のバランスを担う補助役として、重要な働きを果たしています。
🧪 成分と現代医学的知見
麦門冬には多糖類(ophiopogonan)やサポニン類が含まれ、近年の研究では次のような作用が報告されています:
- 抗炎症作用(喉・気管支の炎症緩和)
- 免疫調整作用
- 抗酸化作用による細胞保護
- 唾液・涙液の分泌促進(ドライマウスやドライアイの緩和)
漢方処方における麦門冬の使用は「口渇・乾燥症状の改善」と合致しており、現代医学とも親和性が高い生薬のひとつです。
📖 古典における記載
『神農本草経』では「上品」に分類され、「肺を潤し咳を止め、胃を養い津液を生む」と記載。
『本草綱目』にも「火を清し、心を潤す」との記述があり、心火や虚熱にも効果があるとされました。
⚠️ 注意点と禁忌
- 湿痰や脾虚湿盛タイプ(痰が多い、胃もたれしやすい)には適さないことがある。
- 冷えによる咳・下痢には不向き。
- 妊娠中や乳幼児に使用する場合は専門家の指導を受けること。
麦門冬は滋陰薬の中でも比較的おだやかな性質ですが、誤用による「湿の停滞」には注意が必要です。
📝 まとめ
麦門冬は、肺・胃・心に潤いを与える「養陰薬」の代表格です。特に乾燥性の咳・口渇・不眠・微熱など、陰虚の諸症状に効果を発揮します。
現代でもドライマウス・粘膜の乾燥・口臭などに応用が広がっており、東洋医学と西洋的視点の架け橋となるような生薬です。
体の乾きを感じたとき、やさしく寄り添う一根──それが麦門冬の魅力です。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。麦門冬の特性や使い方について、少しでも理解が深まりましたら幸いです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿