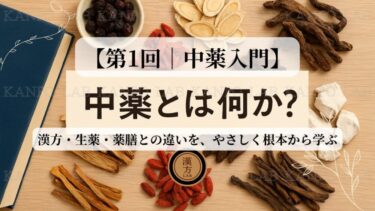🌸 杏仁(きょうにん)|咳と便秘に働く、肺と腸の潤いの種
杏仁(きょうにん)は、アンズの種子から得られる生薬で、中医学では「止咳平喘」と「潤腸通便」の二つの効能で知られます。
乾燥による空咳や喘息、あるいは腸の潤い不足からくる便秘に、やさしくも確かな力で働きかける存在として、古くから重用されてきました。
🧾 基本情報
- 名称:杏仁(きょうにん)
- 英名:Apricot Kernel
- 学名:Prunus armeniaca
- 使用部位:種子(仁)
- 性味:苦・微温(または微寒)
- 帰経:肺・大腸経
- 分類:止咳平喘薬
🌿 主な効能と中医学的働き
杏仁は「苦で降、潤で通」──つまり苦味が肺気を下げ、油性成分が腸を潤すという、二重の効能を持っています。
- 止咳平喘: 肺気が上逆することで起きる咳嗽や喘息に対し、肺気を下げることで鎮静。
- 潤腸通便: 肺と大腸の経絡関係(表裏関係)を利用し、腸の乾燥による便秘を改善。
特に乾燥性の咳(燥咳)や、風寒・風熱の表証に合併する咳に用いられ、配伍により対応範囲が広がります。
📚 応用される処方例と役割
- 麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう): 風熱による咳・喘息に。麻黄と配合し、肺気を下げて呼吸を整える。
- 杏蘇散(きょうそさん): 風寒咳嗽・鼻水・痰が多いタイプに。杏仁が潤肺作用を強化。
- 清肺湯(せいはいとう): 肺熱による乾咳に。杏仁が清熱潤肺を助ける。
- 麻子仁丸(ましにんがん): 高齢者や虚弱者の便秘に。潤腸通便作用で杏仁が補助役。
これらの処方では、杏仁が「君薬」「臣薬」いずれの役割も担い、他の生薬と調和して働くように設計されています。
🧪 成分と現代医学的知見
杏仁に含まれる主要成分はアミグダリン(Amygdalin)で、体内で分解されて微量の青酸を生じます。これにより中枢性の鎮咳作用が発揮されるとされます。
ただし、この作用は用量依存的であり、過量では中毒の危険があります。通常の漢方製剤に含まれる範囲では安全ですが、生用には注意が必要です。
また、現代では杏仁オイルが保湿・抗炎症作用をもつ植物油として美容やアロマにも用いられ、伝統と現代が交差する応用が進んでいます。
📖 古典における記載
『神農本草経』では杏仁を「上品」とし、「咳逆上気、喀血、風寒に効あり」と記述。
『本草綱目』では肺気の降を促し、表寒を取る要薬として繰り返し登場します。
その苦味と潤性の両立が古来より高く評価されてきた証です。
⚠️ 注意点と禁忌
- 用量は通常3~9g。過量摂取は青酸中毒の恐れがあるため厳禁。
- 小児・妊婦・虚寒タイプの方には慎重投与または回避が望ましい。
- 安全のため、生用せず湯通しまたは加熱加工したものを使用するのが基本。
📝 まとめ
杏仁は、肺と大腸という「上と下」「気と通」を同時に整える、非常にバランスの取れた中薬です。
咳止めとして知られる一方で、潤い不足の便秘にも対応できる柔軟さをもち、乾燥体質・陰虚傾向の方に特に適します。
漢方の処方設計では、杏仁の「苦・潤・下行」という性質を生かして、寒熱・虚実に応じた使い分けがなされてきました。
用途は多岐にわたりますが、毒性リスクへの配慮を忘れず、配伍・加工・用量のすべてが整った上でこそ、真価を発揮する生薬です。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。杏仁の働きについて少しでも理解が深まりましたらうれしいです。
よろしければ、ぜひもう一つ別の記事もご覧ください。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
気になる記事から、さらに漢方の世界を深めていただければ幸いです。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
また漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿