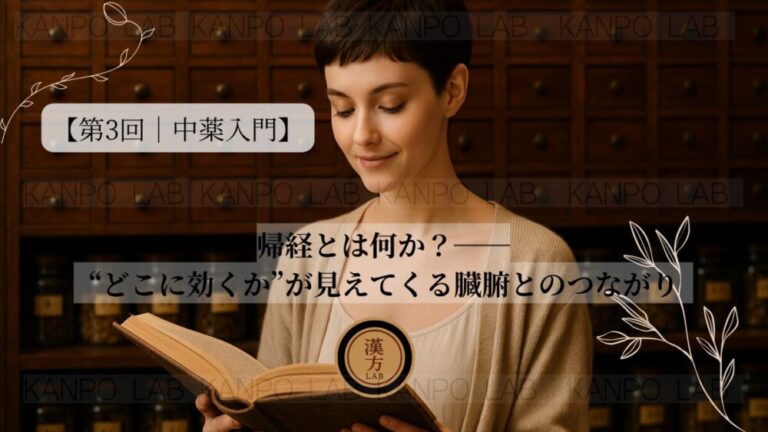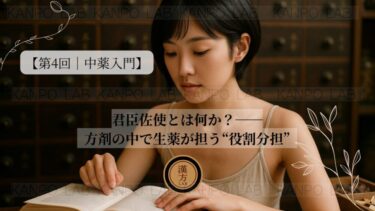【第3回|中薬入門】帰経とは何か?──“どこに効くか”が見えてくる臓腑とのつながり
「この生薬、どこに効くの?」
そう尋ねられたとき、あなたはどう答えるでしょうか。
中薬の世界では、その答えの鍵を握るのが「帰経(きけい)」という考え方です。
この記事では、帰経の意味・臓腑との関係・五味や方剤とのつながりをやさしく解説いたします。
📖 はじめに:体に「効く場所」があるという視点
たとえば「咳が止まらない」と言われたとき、西洋医学では気管支や肺を中心に考えます。
中医学でも「肺」に注目しますが、そのアプローチは少し違います。
中薬の世界では、それぞれの薬が“どの臓腑に届くか”=帰経という視点を持って処方されます。
つまり、「帰経」とは、“薬が効く経絡・臓腑の方向性”を示す中医学の独自理論なのです。
🧭 帰経とは何か?──臓腑と経絡を結ぶ“ルート指定”
「帰経(きけい)」とは、中薬が体のどの経絡・臓腑に作用するかを示した概念です。
単に「胃に効く」「肝に届く」といった効果範囲の目安ではなく、診断・処方の組み立てにおける指針として活用されます。
たとえば──
- 補気の「人参」は ➤ 脾・肺に帰経
- 解熱の「黄連」は ➤ 心・肝・胃・大腸に帰経
- 鎮静の「竜骨」は ➤ 心・肝・腎に帰経
このように、同じような効能を持つ中薬でも、帰経が異なることで適応や使い分けが生まれるのです。
📚 帰経と五臓の関係──それぞれの“臓”の性格を知る
帰経は、「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」+「六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)」に分類されます。
ここでは、五臓を中心に簡単にまとめましょう。
| 臓腑 | 主な働き | 帰経する代表中薬 |
|---|---|---|
| 肝 | 血・気の流れ、情緒 | 柴胡、当帰、牡丹皮 |
| 心 | 血の巡り、精神 | 黄連、竜骨、酸棗仁 |
| 脾 | 消化・吸収・気血の生成 | 人参、白朮、茯苓 |
| 肺 | 呼吸、水の代謝、皮膚 | 杏仁、麻黄、桔梗 |
| 腎 | 成長、生殖、水分代謝 | 地黄、杜仲、山茱萸 |
この分類により、体のどこに効かせたいかを見極めて薬を選ぶという思考が可能になります。
🔗 五味・四気とのつながり──複合的に考える「証」
帰経は「どこに効くか」を示しますが、「どう効くか」は五味・四気と組み合わせて考えます。
- 🍬 甘(補う)+ 脾・肺に帰経 ➤ 人参:元気を補う
- ☕ 苦(清熱)+ 心・胃に帰経 ➤ 黄連:熱を冷ます
- 🌶️ 辛(発散)+ 肺に帰経 ➤ 麻黄:風寒を追い出す
つまり、「味 × 温度 × 帰経」= 中薬の立体的な性格が決まるのです。
🧪 方剤における帰経の使われ方
帰経は、処方全体のターゲットを明確にする設計図のような役割を果たします。
例として、補中益気湯では以下の帰経を意識しています:
- 脾に帰経:人参、白朮、黄耆 ➤ 補気作用
- 肺に帰経:陳皮、柴胡 ➤ 昇提・気の巡り
- 胃に帰経:当帰、生姜 ➤ 調和と吸収補助
このように、症状の出ている臓腑+本質的に補うべき臓腑の両方に薬を配置するのが中薬処方の基本設計です。
🎯 帰経を知ると、薬が「選べる」ようになる
「なんとなく効く」ではなく、「なぜこの生薬なのか」「どの臓腑に届けたいのか」が見えてくるのが帰経の魅力。
薬を“処方”する側にとっても、“選ぶ”側にとっても、強力な羅針盤になります。
また、帰経は方剤だけでなく、薬膳や経絡ケアにも応用できる考え方です。
📘 次に読むべき記事|「君臣佐使」とは?──方剤を支える“薬の役割分担”
次回は、「構成」そのものに焦点を当てます。
どの薬が中心で、どの薬が支えるのか──方剤の設計思想「君臣佐使」について、詳しく解説いたします。
▶️ 第4回|君臣佐使とは?記事へ進む
この記事の分類
- シリーズ分類:【中薬入門シリーズ】
- 五臓六腑分類:三焦 上焦 中焦 下焦