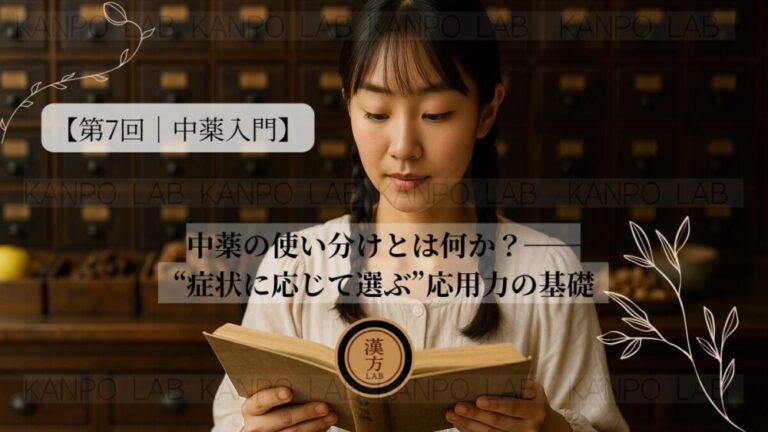目次
【第7回|中薬入門】中薬の使い分けとは何か?──“症状に応じて選ぶ”応用力の基礎
「同じ症状でも処方が違うのはなぜ?」
それは、“症状の裏にある体質や状態(証)”によって、中薬の使い分けがされているからです。
この記事では、実例をもとに中薬・方剤の使い分けの考え方をやさしく解説いたします。
🎬 はじめに:「この症状にはこの薬」が通用しない?
頭痛・腹痛・冷え・のぼせ──
こうした症状に対して、西洋医学では原因臓器や病名に応じて治療薬が決まります。
しかし漢方では、「その人の体質や状態(証)に合った薬を選ぶ」ことが基本です。
つまり、“同じ症状でも処方が違う”のが漢方の特徴。
この考え方の核となるのが、中薬の「使い分け」です。
📘 「使い分け」とは?──証に応じた中薬・方剤の選択
中薬の「使い分け」とは、症状の背景にある証(体質や病態)に応じて、中薬や方剤を選び分けることです。
この判断には、四診(望・聞・問・切)による診察と、弁証論治(証を見極め治療方針を決める)が欠かせません。
🧪 実例①|頭痛に使う中薬の違い
| タイプ | 証 | 主な中薬・方剤 |
|---|---|---|
| 風寒型 | 外感による頭痛・寒気 | 川芎、羌活、麻黄 → 川芎茶調散 |
| 風熱型 | のぼせ・喉の腫れ・目の充血 | 菊花、連翹、薄荷 → 銀翹散 |
| 瘀血型 | 慢性頭痛・刺痛 | 丹参、桃仁、紅花 → 血府逐瘀湯 |
このように、「頭痛」という1つの症状でも、背景によって使う薬はまったく異なるのです。
🧪 実例②|冷えに使う中薬の違い
| タイプ | 証 | 主な中薬・方剤 |
|---|---|---|
| 陽虚型 | 全身の冷え・倦怠 | 附子、乾姜、人参 → 四逆湯、真武湯 |
| 血虚型 | 手足の冷え・顔色不良 | 当帰、芍薬、地黄 → 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 気虚型 | 疲労感・息切れ・食欲不振 | 黄耆、人参、白朮 → 補中益気湯 |
🧭 使い分けの指針:何を見て分けるのか?
- ① 主訴(症状):最も困っていること(例:咳、便秘、冷え)
- ② 体質:虚実・寒熱・陰陽など(例:疲れやすい・のぼせる)
- ③ 経過:急性か慢性か、発作的か持続的か
- ④ 全体像:舌診・脈診・顔色・声の調子・食欲などを総合的に判断
これらをもとに、症状に対して“どの証か”を絞り込み、それに合う中薬・方剤を選ぶのが使い分けの流れです。
📚 方剤での使い分け|似た処方の違いを見る
| 比較処方 | 違いのポイント |
|---|---|
| 補中益気湯 vs 六君子湯 | どちらも補気剤。 前者は気虚による脱力・下垂に、後者は胃気虚+痰湿に。 |
| 葛根湯 vs 麻黄湯 | どちらも風寒に使うが、前者は表寒+首肩こり、後者は悪寒・無汗の急性表寒に。 |
| 当帰芍薬散 vs 温経湯 | どちらも婦人科向け。前者は血虚+水滞、後者は血虚寒凝による月経不順に。 |
🧠 まとめ:中薬の使い分けは“理解の応用”
分類・帰経・君臣佐使・配伍──これまで学んだ要素を踏まえ、
症状や証に応じて中薬・方剤を「選べる」ことが、使い分けの本質です。
「この薬はなぜ選ばれたのか?」
「別の薬でもっと合うものはないか?」
そんな視点を持つことで、中医学の理解は一段と深まります。
📘 次に読むべき記事|中薬の学びを生活に活かすには?
次回はいよいよ「中薬との付き合い方」へ。
学んだ知識を、薬局・セルフケア・薬膳など、日常の中で活かす視点をお伝えします。
▶️ 第8回|中薬との付き合い方へ進む
この記事の分類
- シリーズ分類:【中薬入門シリーズ】