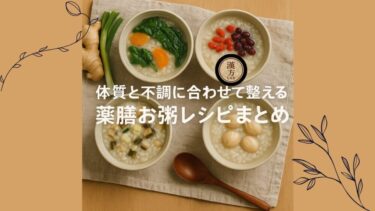目次
🦶 高尿酸血症と痛風:数値よりも“体の内側”を見直す
「尿酸値が高めですね」──健康診断でそう指摘されたことのある方は少なくありません。高尿酸血症は放置すると「痛風」へ進行するだけでなく、腎臓病や高血圧、動脈硬化のリスクにもつながります。
現代医学では主に「尿酸値7.0mg/dL以上」で診断されますが、数値だけを見て薬を飲むだけでは根本解決にはなりません。
「なぜ尿酸がたまるのか?」を体の内側から見直すこと──それが中医学(東洋医学)のアプローチです。
本記事では、現代医学と中医学の違いを整理しながら、湿熱・瘀血・脾虚・腎虚などの体質別に漢方・薬膳・生活習慣で整える方法をご紹介します。
🧪 現代医学における高尿酸血症の定義と治療
- 尿酸値:7.0mg/dL以上で高尿酸血症と診断
- 無症候性でも腎機能障害や動脈硬化のリスクが増加
📉 主な原因
- プリン体の過剰摂取(ビール・肉類など)
- 腎機能の低下による排泄障害
- 肥満・糖尿病・ストレス・高血圧との関連
💊 治療法
- 尿酸生成抑制薬(アロプリノール等)
- 尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロン等)
- プリン体制限・水分補給・節酒などの生活改善
🧭 中医学での見立て:湿・熱・血・腎の乱れ
中医学では、高尿酸血症や痛風の原因を「腎」「脾」「肝」のバランス失調や「湿熱」「瘀血」などの証で捉えます。
- 湿熱:関節に炎症や腫れが現れる原因
- 瘀血:血の巡りが悪くなり老廃物が停滞
- 脾虚:代謝機能の低下により湿が溜まりやすい
- 腎虚:慢性化・加齢に伴う排泄機能の低下
👤 体質別にみる高尿酸血症の特徴
🔥 湿熱型
- 関節が腫れて熱感あり・口の苦み・尿が濃い
- 赤ら顔・舌苔が黄色でべっとり
🩸 瘀血型
- 刺すような痛み・慢性的な関節痛
- 舌や唇が暗紫色・夜間に痛みが強くなる
🍚 脾虚型
- 疲れやすい・食欲がない・軟便傾向
- 舌に歯痕があり、白く湿った苔
❄️ 腎虚型
- 足腰のだるさ・尿が出にくい・夜間頻尿
- 慢性疾患・加齢との関連が強い
💊 証に合わせた代表的な漢方処方
🔥 湿熱型
- 竜胆瀉肝湯:関節の腫れ・赤み・イライラ傾向に
- 茵陳蒿湯:肝胆の湿熱+黄疸傾向・苦味
🩸 瘀血型
- 疎経活血湯:血行不良+関節痛
- 桂枝茯苓丸:血の滞りと下半身症状に
🍚 脾虚型
- 防己黄耆湯:むくみ+だるさ
- 参苓白朮散:胃腸虚弱・痰湿体質
❄️ 腎虚型
- 八味地黄丸:腰の冷え・尿トラブル
- 牛車腎気丸:腎虚+むくみ+代謝低下
🥗 体質別の薬膳食材と食養生
🔥 湿熱型
- 緑豆、はと麦、苦瓜、冬瓜、どくだみ茶
🩸 瘀血型
- 黒豆、紅花、玉ねぎ、梅干し、青魚
🍚 脾虚型
- 山芋、なつめ、雑穀、生姜、米粥
❄️ 腎虚型
- 黒ごま、クルミ、にら、山薬、海藻類
📍 経絡セルフケア:痛風発作予防と巡りの改善
- 太渓:腎経を強化し下肢の冷えや痛みに
- 陰陵泉:脾経・湿の排出を助ける
- 三陰交:脾腎肝を総合的に補う
- 血海:瘀血体質の改善に
📝 まとめ:体の声を聞き、内側から整える
高尿酸血症・痛風は、食事や体質、代謝バランスの乱れのサイン。薬に頼るだけではなく、体質ごとの証に合わせて調整していくことで、再発予防や生活の質の向上につながります。
今の自分はどのタイプか? まずはそこから見直し、内臓から整える漢方養生を取り入れてみませんか。
📣 最後に:もう一記事読んでみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
下へスクロールしていただくと、他の中薬や処方に関する投稿一覧が表示されております。
気になる記事をぜひご覧ください。
🙌 クリック応援ありがとうございます!
漢方LABでは、より多くの方に中医学の魅力を伝えるために、
ブログ村や人気ブログランキングにも参加しております。
もしよろしければ、以下のバナーをクリックして応援していただけると励みになります🌿