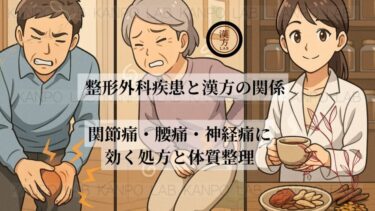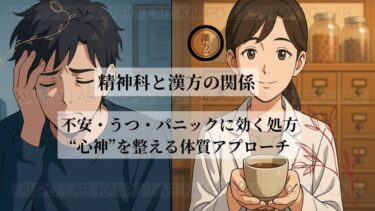目次
疲れ・だるさの東洋医学的アプローチ
「休んでも疲れが取れない」「朝から体が重い」——そんな不調、感じていませんか?
現代人の多くが悩む慢性的な“疲れ”や“だるさ”は、西洋医学では原因が不明とされることもありますが、東洋医学(中医学)では明確な原因と改善法が存在します。本記事では、薬剤師 × 国際中医師の視点から、東洋医学的な疲労のタイプと、その解決アプローチについてわかりやすく解説いたします。
東洋医学における「疲労」とは?
中医学では、疲労感は「気・血・津液(水分)」のバランスの乱れからくるものとされ、特に以下のタイプに分類されます。
① 気虚(ききょ)タイプ
“元気”の源である「気」が不足した状態。疲れやすく、息切れしやすいのが特徴。
- 朝からだるい・起きられない
- 少し動いただけで息切れする
- 風邪をひきやすい、回復が遅い
② 脾虚(ひきょ)タイプ
“脾(ひ)”とは中医学での消化吸収の要。脾虚になると栄養がうまく巡らず、疲れやだるさが慢性化します。
- 食後すぐに眠くなる
- 食欲がない・下痢しやすい
- むくみがち・冷えやすい
③ 気滞(きたい)タイプ
気の巡りが滞るタイプ。ストレスや自律神経の乱れが背景にあることが多く、精神的疲労が中心。
- 気分が落ち込む・やる気が出ない
- お腹が張る・ゲップが出やすい
- 肩こり・頭痛が慢性的にある
タイプ別|おすすめの漢方処方
自分の疲労タイプを見極めることで、より適切な方剤を選ぶことができます。
- 補中益気湯:気虚・脾虚の代表的な処方。元気と胃腸の働きを補う
- 六君子湯:脾虚で食欲不振があるときにおすすめ
- 加味逍遥散:ストレス・気滞に伴う疲労感に
- 十全大補湯:気血両虚のタイプに。全身疲労が強い場合
薬膳で補う「疲れに効く食材」
- なつめ:脾を補い、心の疲れもケア
- 山芋:胃腸の働きを整え、気を補う
- 黒ごま:腎の力を高め、慢性疲労にも
- 鶏肉・鰻:補気・補血食材の代表
疲労タイプ別|おすすめの薬膳レシピ
- 山芋と鶏肉のスープ
- 黒ごま入りおかゆ
- なつめとクコの実の煮物
私からのひとこと
東洋医学は「未病(みびょう)」の状態を重視します。「疲れているけど病気じゃないから大丈夫」と我慢していると、知らぬ間に体調を崩してしまうこともあります。
その前に、自分の体質を知り、体に合ったケアを取り入れることが重要です。