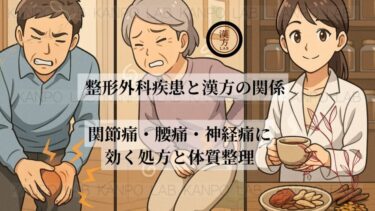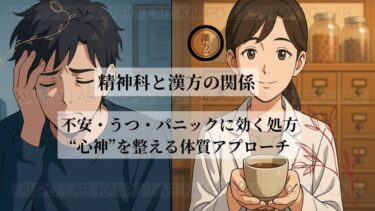脂質異常症は数値の病気?それとも体質の警告?
健康診断で「LDLコレステロールが高いですね」「中性脂肪が増えてますよ」と言われた経験はありませんか?
脂質異常症は、日本人の生活習慣病の中でも非常に多く、放置すると動脈硬化や心疾患、脳血管障害などに進展するリスクをはらんでいます。
しかし──
- 薬を飲んでも下がらない
- 食事に気をつけているのに改善しない
- そもそも、なぜ自分だけ数値が高いのかがわからない
そんなお悩みを抱える方も少なくありません。
中医学では、脂質異常症は単なる“血の中の脂”ではなく、「痰濁(たんだく)」や「瘀血(おけつ)」、「肝鬱気滞(かんうつきたい)」といった体質の偏りから生じると考えます。
本記事では、現代医学と中医学それぞれの視点から脂質異常症を理解し、体質別の漢方処方や薬膳食材、日常ケアのヒントまでをご紹介します。
現代医学での脂質異常症の分類と治療方針
脂質異常症とは、血液中の脂質(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)のバランスが崩れた状態を指します。
主な分類:
- 高LDLコレステロール血症:「悪玉コレステロール」とされ、動脈硬化の大きなリスク
- 低HDLコレステロール血症:「善玉コレステロール」が少ない状態。血管保護が低下
- 高トリグリセリド血症:中性脂肪が多く、メタボや糖尿病と関連
治療の基本は「食事+運動+薬」
厚生労働省のガイドラインでは、以下のような治療が推奨されています:
- 脂質バランスの改善(飽和脂肪酸の制限、DHA・EPAの摂取)
- 食物繊維の摂取・糖質制限・アルコール制限
- 運動習慣(有酸素運動、筋トレ)
- スタチン系薬剤・フィブラート系薬剤などの内服治療
ただし、生活指導を守っていても効果が出にくい人や、副作用で薬が合わない人も存在します。
こうした方にこそ、中医学の「証(体質)」に着目した視点が、補完療法として活かされる可能性があります。
中医学での見立て|瘀血・痰濁・肝鬱から紐解く
中医学では、脂質異常症という病名は存在しませんが、「痰濁」「瘀血」「肝鬱気滞」などに分類される病理状態として理解されます。
- 痰濁(たんだく):代謝の乱れにより、不要な水分や脂質が停滞する体質
- 瘀血(おけつ):血の流れが滞り、血管内の汚れ・粘度が増した状態
- 肝鬱気滞(かんうつきたい):ストレスや情緒の抑圧で気の巡りが悪くなり、消化吸収に影響
これらの背景には、「脾(ひ)」の弱りが関わっています。脾は食物を気血に変える消化器官であり、脾の失調は痰湿の生成を助長し、脂質異常につながるのです。
体質別に見る脂質異常症の主なタイプと特徴
1. 痰濁中阻タイプ
特徴:肥満、胸苦しさ、めまい、舌苔が厚い、口の粘り、体が重だるい
2. 瘀血阻絡タイプ
特徴:肩こり、唇や舌が紫色、刺すような痛み、慢性の動悸
3. 肝鬱気滞タイプ
特徴:イライラ、怒りっぽい、胸脇の張り、不眠、便秘傾向
4. 脾虚湿盛タイプ
特徴:疲れやすい、軟便、食後の眠気、腹部膨満感、甘いもの好き
このように中医学では「脂質が高い」という結果ではなく、「なぜそうなったのか」という体質の偏りを見極めて対応します。
証に基づく漢方処方の選び方(代表方剤紹介)
● 痰濁中阻タイプ
- 平胃散:脾胃を整え、湿をさばく
- 防已黄耆湯:肥満+むくみに
● 瘀血阻絡タイプ
- 血府逐瘀湯:上半身の血の滞りを改善
- 桂枝茯苓丸:女性に多い瘀血体質に
● 肝鬱気滞タイプ
- 柴胡疎肝散:情緒の安定と気の巡り
- 逍遥散:PMSやストレス体質に
● 脾虚湿盛タイプ
- 参苓白朮散:脾胃を補いながら湿を除く
- 六君子湯:胃腸虚弱+消化不良タイプに
薬膳と日常ケアの工夫:五味・経絡・食材によるサポート
痰濁を改善する薬膳素材
- 大根、はとむぎ、昆布、冬瓜、山楂子
瘀血を流す薬膳素材
- 黒豆、玉ねぎ、紅花、丹参、ブルーベリー
肝鬱を解く薬膳素材
- 陳皮、ミント、菊花、しそ、大葉、ジャスミン茶
脾を補う薬膳素材
- 山薬、なつめ、小豆、生姜、さつまいも
「食べ方」や「食べる時間帯」も重要です。朝は温かい汁物を、夜は油控えめで胃腸にやさしく。
まとめ|“血”と“痰”と“気”のバランスを整えるという視点から
脂質異常症は「コレステロールの問題」ではなく、体質の乱れが数値に現れている状態と捉えることで、新たな改善の糸口が見えてきます。
肝の気を整える、血の巡りを良くする、脾を補う──
中医学の知恵は、予防と生活改善に強く寄与します。
数値に一喜一憂するのではなく、自分の体が今、どんな偏りを訴えているのかを読み取って、漢方や薬膳を活用してみませんか?