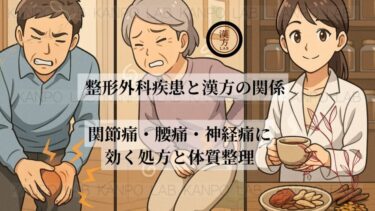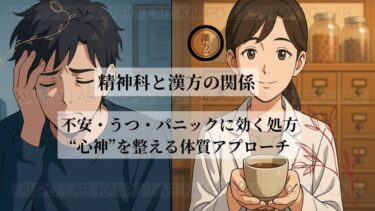目次
中医学から読み解く“冷え症”のタイプ分類と治療戦略
「冷え症」は患者がしばしば訴える症状でありながら、現代医学においては明確な疾患概念や治療ガイドラインが存在せず、診療における介入の難しさがある領域です。
特に女性や高齢者においては、冷えが月経不順、不妊、消化機能低下、うつ状態などと併発することも少なくありません。
中医学では、冷えを単なる“感覚”ではなく、「陽気(体内の熱をつくり巡らせる力)の失調」として病機的に分類し、それに応じた弁証・処方が行われます。
本稿では、冷え症の中医学的タイプ分類と臨床への応用法を解説いたします。
中医学における「冷え」の定義
中医学で冷えは、「寒証(かんしょう)」に属し、陽気の不足や寒邪(外因の冷え)による体内の温煦機能の障害として捉えます。
特に以下の3つの要因が複合することが多く、それぞれ弁証分類が異なります。
- 陽虚:体内で熱を生み出す力の低下(内因性)
- 瘀血:血流不全により熱が末端に届かない状態
- 気滞:ストレスや緊張による気の鬱滞で冷感が生じる
冷え症の中医学的タイプ分類
以下は、臨床的によくみられる冷えのタイプを中医学的に分類したものです:
| 証型 | 主な症状 | 処方例 |
|---|---|---|
| 陽虚(腎陽虚・脾陽虚) | 全身の冷え、疲労感、浮腫、夜間頻尿、顔色不良、舌淡 | 八味地黄丸、真武湯、附子理中湯 |
| 血虚 | 手足末端の冷え、めまい、不眠、顔色蒼白、月経量少 | 当帰芍薬散、帰脾湯、十全大補湯 |
| 瘀血 | 刺すような痛み、下腹部冷え、しもやけ体質、経血に塊 | 桂枝茯苓丸、温経湯、当帰建中湯 |
| 気滞 | 冷えとほてりの交互、月経前の情緒不安定、胸脇の張り | 加味逍遙散、香蘇散 |
| 外寒侵襲 | 急激な冷え、悪寒、関節痛、風邪のひきはじめ | 麻黄附子細辛湯、桂枝湯 |
タイプ別・症候別の処方戦略
■ 陽虚タイプ(高齢者・冷え+浮腫・頻尿)
- 代表処方:八味地黄丸(腎陽虚)、真武湯(脾腎陽虚+浮腫)
- 適応例:腰痛、冷感、夜間頻尿、温めると改善
■ 瘀血タイプ(慢性疼痛・婦人科疾患・しもやけ)
- 代表処方:桂枝茯苓丸、温経湯
- 適応例:月経痛、瘀点、紫舌、慢性肩こりなど
■ 気滞タイプ(情緒不安・交互の冷えと熱)
- 代表処方:加味逍遙散、香蘇散
- 適応例:PMS、不安感、冷えのぼせ、便通不安定
診療科ごとの活用視点
- 婦人科:不妊、月経困難症、PMS→瘀血・気滞・血虚型冷え
- 整形外科・リハビリ:腰痛・神経痛→陽虚・瘀血型冷え
- 精神科・心療内科:うつ・不安→気滞+血虚型冷え
- 高齢者医療・在宅:フレイル、ADL低下→脾腎陽虚型冷え
保険適用の処方と注意点
冷えに対する漢方薬の多くは、エキス製剤として保険適用があります:
- 桂枝茯苓丸(ツムラ25)/当帰芍薬散(23)/加味逍遙散(24)
- 真武湯(ツムラ18)/八味地黄丸(7)/温経湯(31)
注意点:
- 甘草含有製剤は電解質管理に注意(偽アルドステロン症)
- 附子含有(真武湯・附子理中湯など)は心疾患・浮腫に慎重投与
- 加味逍遙散・香蘇散は虚実の見極めが重要
終わりに
冷え症は一見すると「気のせい」として見過ごされがちな訴えですが、実際には生命活動の根幹にかかわる「陽気」の低下や「血流」の失調を反映した重要な病態です。
中医学の視座を加えることで、同じ冷えという症状の背後にある病機を分類し、構造的にアプローチする診療が可能になります。
本稿が、患者の訴えに寄り添いながら、冷えに対してより解像度の高い診断と治療を実践する一助となれば幸いです。