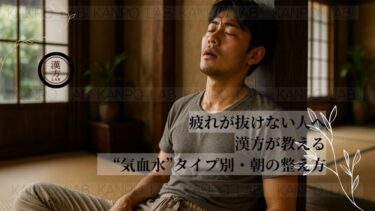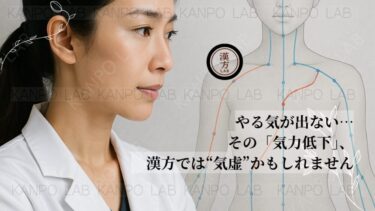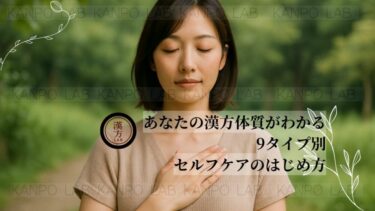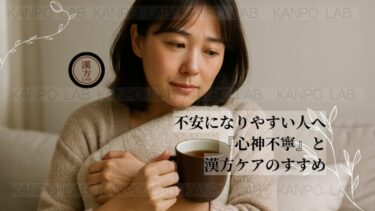目次
気持ちが乱れるのは体のせい?|漢方で整える“感情と体質”の関係
「なんだか情緒が安定しない」「ちょっとしたことで涙が出る」「自分が自分じゃないみたい」──
そんな風に感じるとき、私たちは“心”だけに目を向けがちです。
けれど、漢方では気持ちの乱れは、体質や巡りの乱れからくるものと捉えます。
この記事では、漢方の視点から感情の不安定さを引き起こす“気滞体質”を中心に、心と体の整え方をご紹介いたします。
感情の波は“肝”と“気”のアンバランスから
中医学では、「五臓六腑」と感情は密接に関係しています。
特に“肝”は「怒(いかり)」をつかさどり、全身の気の流れを調整する司令塔でもあります。
ストレスや過労、感情の抑圧によってこの肝のはたらきが乱れると、気滞(きたい)という状態になり、感情面にも影響を及ぼします。
“気滞体質”に見られやすいサイン
- イライラ・怒りっぽい・ため息が多い
- 喉のつかえ感(梅核気)
- 月経前症候群(PMS)が強い
- 胸やお腹の張り、便秘傾向
- 眠れない・夢が多い
タイプ別感情不調×体質のヒント
| 感情の傾向 | 関連体質 | 対応アプローチ |
|---|---|---|
| イライラ・怒りやすい | 気滞・肝火 | 芳香食材・深呼吸・太衝ツボ |
| 涙もろい・寂しさ・不安感 | 心脾両虚・陰虚 | 百合根・甘味・安神のツボ |
| 無気力・やる気が出ない | 気虚・血虚 | 補気食材・規則正しい食事 |
感情のセルフケア|“巡らせる・緩める・整える”
① 食事で香りと巡りを意識する
- しそ、セロリ、春菊、みかんの皮(陳皮)など芳香性の食材
- グレープフルーツ・ゆず茶などの香りも◎
② ツボ押しで気を巡らせる
- 太衝(たいしょう):足の甲、親指と人差し指の間を上にたどった交点 → 肝の調整
- 内関(ないかん):手首から指3本下、腕の中央 → 情緒安定・ストレス緩和
③ 心をゆるめる習慣をつくる
- 「休む」をタスクにする(休む時間をあらかじめ予定に入れる)
- 香り・音・触感など五感を癒すアイテムを持つ
- 「怒り」「涙」も自然なサインと受け止める
まとめ:気持ちが揺れるのは「体からの声」
「情緒不安定」は、決して気のせいではありません。
漢方は、感情は体から生まれるものと教えてくれます。
心が揺れる日は、体をやさしく整えることから。
“わたし”を責めるより、“わたし”の中のバランスを整えてあげることが、いちばんの近道かもしれません。