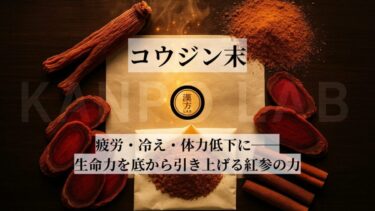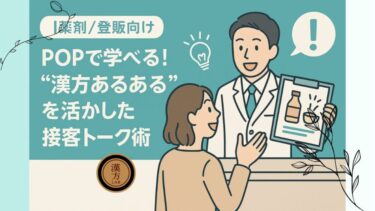目次
消風散|皮膚のかゆみ・じゅくじゅく・湿疹──“風湿熱”を取り除く皮膚疾患の清解方
かゆみが強い、湿っている、赤みがある──それは「風湿熱」のサインかもしれません。
消風散(しょうふうさん)は、皮膚のかゆみ・炎症・湿潤性湿疹に対し、風を散じ、湿を取り、熱を冷ます代表的処方です。
本記事では、薬剤師向けに構成・証・製剤情報・服薬指導・鑑別などを多角的に解説いたします。
🧠 処方名の由来
「消風」とは“風邪(ふうじゃ)を消す”ことを意味し、皮膚表面に侵入した風湿熱によるかゆみ・発赤を鎮めることを目的とした処方名です。
📘 基本情報と構成生薬
- 名称:消風散(しょうふうさん)
- 出典:『外科正宗』
- 分類:祛風止痒・清熱除湿
- 構成生薬:荊芥、防風、牛蒡子、胡麻、知母、石膏、蒼朮、苦参、木通、蝉退、地黄、当帰、甘草
🔍 主治と治法
- 主治:皮膚湿疹、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、汗疹、かぶれ、掻痒性皮膚疾患
- 治法:祛風止痒・清熱除湿・養血潤燥
🧪 ユニット構造と配合意図
- 荊芥・防風・蝉退:祛風止痒
- 知母・石膏・苦参:清熱瀉火・燥湿
- 蒼朮・木通:利湿除痒・通絡
- 地黄・当帰:養血潤燥・調血
- 牛蒡子・胡麻:宣肺解毒・滋潤
- 甘草:調和・抗炎
皮膚表層の“風熱湿毒”と、血虚による瘙痒を同時に整える構成です。
🔬 配合理論と証の成立
- 君薬:荊芥・防風(祛風止痒)
- 臣薬:知母・石膏・苦参・蒼朮(清熱燥湿)
- 佐薬:牛蒡子・胡麻・蝉退・木通(通絡止痒)
- 使薬:地黄・当帰・甘草(養血潤燥・調和)
- 証型:風湿熱侵肌・血虚風燥
📌 証と適応判断
- 適応:皮膚の赤み、かゆみ、じゅくじゅく、掻破後の湿潤、汗で悪化、乾燥肌の併存
- 舌:紅・苔薄黄または黄膩/脈:数・やや弦滑
- NG:陰虚・乾燥傾向が強すぎる場合や冷え・虚証主体の皮膚症状
📊 和漢製剤と中医学の違い
日本では湿疹・アトピー・蕁麻疹の標準処方として使用され、体質や症状に応じて加減されます。
中医では「風湿熱」「血虚風燥」「衛外失調」などの病証に基づき弁証使用されます。
📦 製剤別の比較とOTC入手
- 医療用製剤:あり(ツムラ22番、コタロー、オースギ)
- OTC製剤:あり(第2類医薬品、ドラッグストア・Amazon・漢方薬局にて入手可能)
💊 副作用と注意点
- 石膏:冷え性・胃弱者では腹部不快感が出る場合あり
- 甘草:長期投与時は偽アルドステロン症の確認
- 利湿・清熱性が強いため、乾燥体質・虚寒証では誤投与リスク
🔁 他処方との鑑別・類方比較
- 十味敗毒湯:膿・発赤・湿潤中心、実証性が高い場合
- 当帰飲子:乾燥・血虚中心の慢性皮膚炎、かさつきや掻破痕が多いとき
- 温清飲:血熱中心の赤み+かゆみ+のぼせ傾向があるとき
👨⚕️ 服薬指導のポイント
- 「汗で悪化する」「湿っていてかゆい」「掻き壊すと浸出液が出る」などがポイント
- 清熱・利湿・養血のバランスで構成されているため、食事指導(甘味・脂質・香辛料)との併用が効果的
- 外用薬やスキンケアとの併用で再発予防を図る
🧾 使用例と処方医の意図
- アトピー性皮膚炎:赤み・湿潤・掻破・季節性悪化のある例
- 蕁麻疹:風熱湿による突発性のかゆみ発作
- かぶれ・接触性皮膚炎・汗疹など湿潤性皮膚トラブル
🔚 まとめ|風湿熱+瘙痒性皮膚症状の定番清解方
消風散は、赤み・湿潤・かゆみ・熱感を伴う皮膚症状に対し、清熱・祛風・除湿・養血を統合した信頼性の高い処方です。
薬剤師としては、症状の部位・質・時期を見極め、スキンケア+生活指導+服薬の多面的アプローチを提案することが求められます。