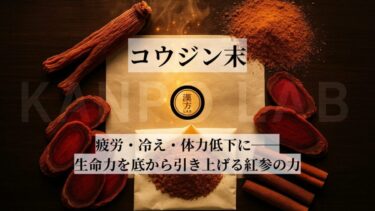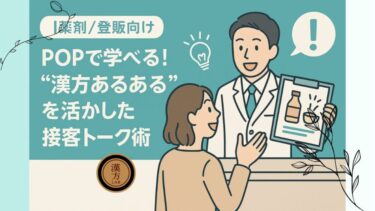目次
“証”ってなに?薬剤師が知るべき中医学の基本
漢方薬を取り扱ううえで避けて通れないのが「証(しょう)」という概念。
でも、「なんとなく“体質”のこと?」「症状の組み合わせ?」と曖昧なまま使っていませんか?
本記事では、若手薬剤師でも理解しやすいように、“証”の基本構造と、日常業務に活かすための実践ノウハウを整理します。
📘 そもそも“証”とは?
中医学における「証」とは、身体の状態を全体としてとらえた“診断単位”のことです。
西洋医学でいう「病名」とは異なり、症状・体質・感受性・生活背景を含んだ動的な概念です。
- 風邪でも「寒証」か「熱証」かで処方は変わる
- 疲れやすい人でも「気虚」「陰虚」「血虚」で対応が異なる
証は「今、この瞬間の身体状態の捉え方」であり、弁証論治(証にもとづく治療方針)という中医学の中心概念と結びついています。
🔍 薬剤師が押さえておくべき“証”の分類
基本的には次の5軸で構成されます:
- 陰陽:寒熱傾向、代謝レベルのバランス
- 表裏:病位の浅さと深さ(外感/内傷)
- 虚実:エネルギーの充実度(虚弱 or 過剰)
- 寒熱:冷え・熱感などの体感と病態
- 気血水:体内物質と流れのバランス
たとえば「気虚+寒+裏+虚」と判断されれば、それに対応する補気温中の処方(例:補中益気湯など)が適応されます。
💊 服薬指導で“証”をどう活かす?
証を知っていると、以下のようなケースで患者対応が変わります:
- 同じ処方でも「実証の人」に出すと悪化することがある
- 補剤を出す前に「脾虚」か「湿困脾」を見極める必要がある
- 副作用(眠気・下痢・動悸)は“証のズレ”で起こることも
つまり、薬剤師が“証”を理解していれば、添付文書以上の服薬指導ができるのです。
🧭 現場で使える“証”チェックのヒント
現場で簡単に確認できる「証」の目安を以下に示します:
- 舌が白くふやけている → 「寒」や「湿」傾向
- 脈が沈で弱い → 「虚証」や「気虚」傾向
- 顔色が赤く脈が数 → 「熱証」「実証」傾向
こうしたポイントを使えば、薬局でも簡易的な“証の見立て”が可能になります。
もちろん確定診断ではありませんが、服薬指導の質と信頼性が大きく変わります。
📌 まとめ|証を理解することは「患者を観る力」につながる
“証”は決して難解な専門用語ではなく、患者さんの“今”を多面的にとらえるためのフレームワークです。
若手薬剤師こそ、「証=患者を観る目」として身につければ、副作用の予防・処方の意図理解・患者との信頼構築に繋がります。
ぜひ、今日から一歩ずつ“証の目”を養ってみてください。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ