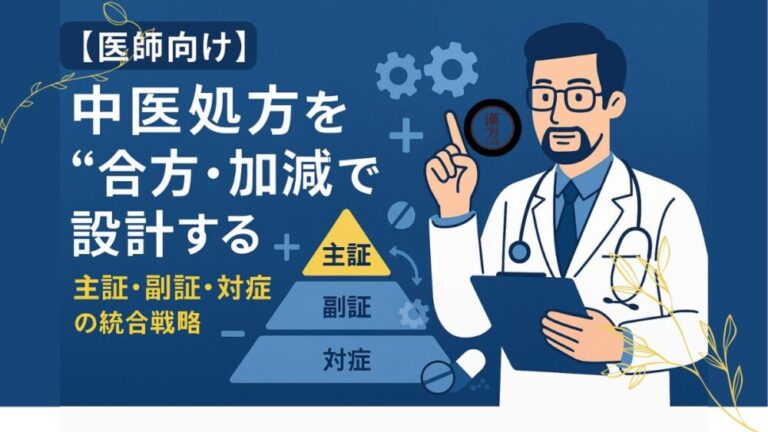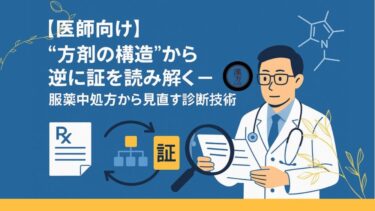目次
中医処方を“合方・加減”で設計する──主証・副証・対症の統合戦略
臨床現場では、患者の訴えが1つの証で説明しきれない場面は少なくありません。
疲労と膨満、冷えとほてり、不眠と便秘──このような症状の併存に対し、中医学では合方(ごうほう)・加減(かげん)という処方構築技法で対応します。
本稿では、中医臨床における処方設計の基礎である「合方・加減」の考え方と、主証・副証・対症をどう統合的に処理するかの戦略を具体的に解説いたします。
1. 合方・加減とは何か?
合方:2つ以上の処方(方剤)を目的別に併用・統合する方法。
加減:基礎方剤に対して、症状や証の状況に応じて生薬を追加・削除する方法。
これらは、弁証論治において「証が重層化・錯雑化している場合」に用いられる最も重要な戦術です。
2. 合方・加減を使うべき臨床状況
- 主証とは異なる副証がある(例:気虚+瘀血)
- 方剤単独では処理しきれない複数病態がある
- 体質に応じて補正が必要(冷えや虚熱など)
- 急性症状(咳・腹痛・月経痛など)の同時併存
単一証にこだわらず、病機構造を柔軟に分解・再構成する技術が求められます。
3. 合方・加減の臨床パターンと処方設計例
| 主証 | 副証・対症 | 処方設計例 |
|---|---|---|
| 脾気虚 | 痰湿 | 六君子湯+温胆湯 |
| 気血両虚 | 瘀血・月経痛 | 十全大補湯+桂枝茯苓丸 |
| 肝鬱気滞 | 血虚・不眠 | 加味逍遙散+酸棗仁湯 |
| 心脾両虚 | 虚熱・寝汗 | 加味帰脾湯+知柏地黄丸(加減) |
| 腎陽虚 | 関節痛(寒湿痺) | 八味地黄丸+疎経活血湯 |
4. 合方・加減の原則と安全な応用法
- ① 方剤の目的を明確にする:主証対応/副証対応/対症処理
- ② 構成生薬の重複・過剰に注意:特に補剤・瀉剤・清熱薬の二重使用に注意
- ③ 薬味数を絞る:15味を超える場合は目的が曖昧な処方構造となる可能性
- ④ 短期評価を行う:加味後の変化を1〜2週間で確認し、過剰反応を避ける
合方・加減は“証構造の動的変化”を反映する技術であり、処方固定ではなく、経時的再構築を前提とします。
5. 臨床ケース:合方処方による症状統合戦略
症例:PMS+抑うつ+月経困難症
- 主証:肝鬱気滞
- 副証:瘀血・虚熱
- 処方:加味逍遙散(疏肝理気)+桂枝茯苓丸(活血化瘀)+知柏地黄丸(加減)
- 結果:月経周期に合わせて段階的に減薬・切替
症例:術後倦怠・不眠・便秘・腹部膨満
- 主証:気血両虚
- 副証:脾虚+痰湿+気滞
- 処方:十全大補湯(補気補血)+温胆湯(化痰)+香蘇散(理気)
- 戦略:体調回復に伴い温胆湯・香蘇散を漸減
終わりに
合方・加減による処方設計は、方剤を“部品”として再構成する技術であり、中医学的診断(証)を処方に落とし込む実務的スキルです。
弁証が重層化しやすい現代の多症状患者にこそ、この柔軟な構造設計力が問われます。
本稿が、臨床現場で方剤を安全かつ精緻に構成し、主証・副証・対症を一体的に捉える診療設計の一助となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ