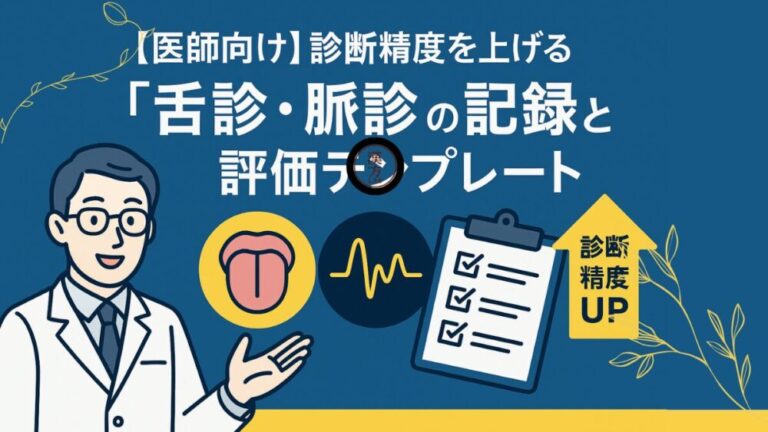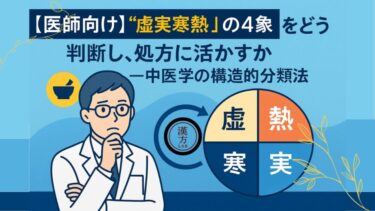目次
診断精度を上げる“舌診・脈診”の記録と評価テンプレート
舌診と脈診は、中医学における最も象徴的な診断技術であり、証(しょう)の構造判断において重要な位置を占めています。
しかし、臨床において「見てはいるが、どう記録し、どう処方に活かすかが曖昧」という課題も少なくありません。
本稿では、舌診・脈診の評価ポイントを体系化し、診断に活かすための記録テンプレートとともに、医師が再現性をもって活用できるよう実践的に解説いたします。
1. 舌診・脈診の役割とは何か
舌診は“内臓の鏡”、脈診は“気血の反映”とされ、いずれも証の構造を外から可視化する手段です。
- 舌診:臓腑・気血・津液の状態を視覚的に把握
- 脈診:五臓の気血・寒熱・虚実を動的に評価
この2つの情報は、主観に左右されやすい問診と異なり、診断の客観性を補完する指標としても極めて重要です。
2. 舌診の分類構造と評価項目
舌診は大きく分けて以下の5項目で観察されます。
| 観察項目 | 主な分類 | 診断的意義 |
|---|---|---|
| 舌色 | 淡/淡紅/紅/紅絳/紫 | 虚証/平証/実熱/陰虚火旺/瘀血 |
| 舌形 | 胖/裂紋/痩/歯痕 | 水滞/陰虚/血虚/脾虚 |
| 舌苔の色 | 白/黄/灰/黒 | 寒証/熱証/内実/陽極 |
| 苔の厚さ | 薄/厚/剥落 | 表証・虚証/痰湿・食積/陰液損傷 |
| 苔の性状 | 膩/乾/滑/剥 | 湿・痰/陰虚/胃熱/気陰両傷 |
このように、舌診は寒熱・虚実・気血・湿痰・瘀血すべての病機を反映します。
3. 脈診の分類構造と評価項目
脈診は以下のようなリズム・速度・力感などから病機を読み取ります。
| 脈状 | 特徴 | 臨床的示唆 |
|---|---|---|
| 浮脈 | 表層で感じる | 表証・外邪侵襲 |
| 沈脈 | 深く押して初めて触れる | 裏証・内臓機能低下 |
| 数脈 | 速い脈 | 熱証・実熱/陰虚熱 |
| 遅脈 | 遅い脈 | 寒証・陽虚 |
| 滑脈 | つるつる滑らか | 痰湿・実証・妊娠 |
| 弦脈 | 緊張・張りつめ | 肝鬱・気滞・痛症 |
| 細脈 | 細く弱い | 気血両虚・陰虚 |
4. 舌診・脈診を診断構造に活かす技術
問診だけでは診断が確定しないとき、舌・脈は以下のような判断補助になります。
- 虚実の鑑別:細脈/舌淡 → 虚証 / 滑弦/舌紅・厚苔 → 実証
- 寒熱の判定:遅脈・白苔・冷え → 寒証 / 数脈・黄苔・舌紅 → 熱証
- 気血津液の状態:舌裂・乾 → 陰虚 / 舌痩・淡 → 血虚
- 痰湿瘀血の存在:舌膩・滑脈 → 痰湿 / 舌紫・弦脈 → 瘀血
舌脈所見を診断構造にひも付けることで、処方が論理的に構築できます。
5. 舌診・脈診記録テンプレート
以下のようなテンプレートを導入することで、診断の再現性と評価性が高まります。
【舌診】 ・舌色:淡紅 ・舌形:胖、裂紋あり ・苔色:白膩 ・苔厚さ:中等度 ・苔性状:膩、やや乾 【脈診】 ・脈位:浮中 ・脈力:虚 ・脈状:滑、やや弦 ・速度:中等 【診断構造への反映】 → 脾気虚(舌淡・胖・白膩) + 痰湿(苔膩・滑脈) + 肝鬱気滞(弦脈・膨満感あり)
6. 臨床ケースで学ぶ記録と判断
■ 症例1:慢性疲労・抑うつ・不眠
- 舌診:淡紅・裂紋・苔少
- 脈診:細・緩・虚
- 診断:心脾両虚+陰虚
- 処方:加味帰脾湯+麦門冬湯
■ 症例2:月経困難・顔面紅潮・口渇
- 舌診:紅・瘀点・黄苔
- 脈診:弦・数
- 診断:肝鬱化火+瘀血
- 処方:加味逍遙散+桂枝茯苓丸
7. 舌診・脈診をチーム医療に活かす
舌・脈情報は、主観の入りやすい診察において“可視化と共有”ができる利点があります。
- 舌写真の記録 → 経過比較・指導素材に
- 脈の特徴を言語化 → 他職種と共有可能(例:滑・弦・虚)
- テンプレートで学習支援 → 研修医・学生教育に活用
8. 終わりに
舌診・脈診は“感覚”ではなく、構造的に読み解くべき診断技術です。
それをカルテに記録し、診断と処方の間に橋をかけることで、中医学的診療はより再現性をもって活用できます。
本稿が、診断精度の向上とチーム内共有・再評価・教育における「舌脈情報の標準化」に向けた一助となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ