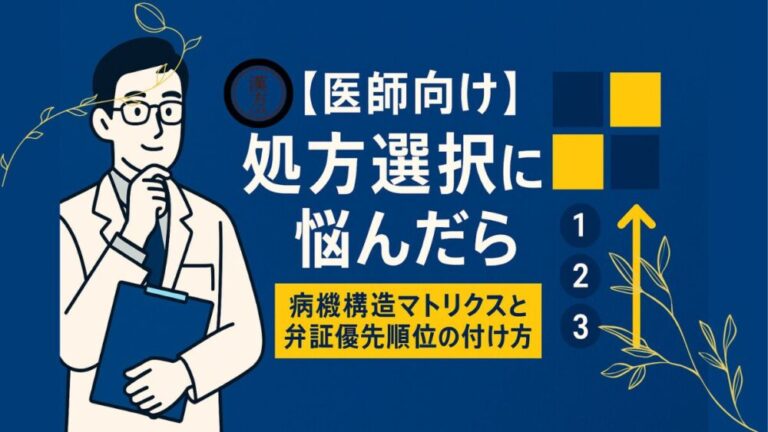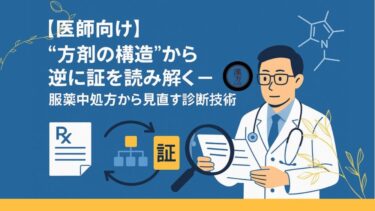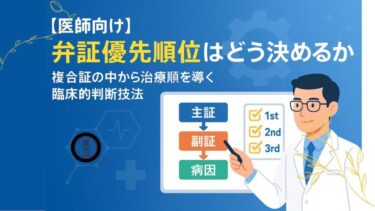目次
処方選択に悩んだら──病機構造マトリクスと弁証優先順位の付け方
漢方治療において「診断は立てられたが、どの処方を選べばよいか分からない」という壁にぶつかることは多くあります。
特に、気虚・瘀血・痰湿・肝鬱など複数の証が同時に存在するとき、その優先順位の決定は処方設計の核心です。
本稿では、中医学的な病機をマトリクス的に整理し、主証・副証・誘因因子を構造化したうえで、弁証に基づく処方優先順位の決定法を紹介します。
1. 病機構造とは何か──症状の背後にある“力学的構図”
中医学における“病機”とは、体内の機能・物質の偏りと流れの破綻を意味します。
主に以下の5軸で整理されます:
- 気血津液の虚実(気虚・血虚・陰虚・陽虚・気滞・瘀血)
- 寒熱(寒証/熱証/虚熱)
- 表裏(発症期・体表症状 or 臓腑深部病機)
- 臓腑の失調(肝・心・脾・肺・腎の機能不調)
- 病因因子(風・寒・湿・痰・瘀・食積など)
複数の証が併存する場合には、それぞれの病機を「構成要素」として抽出し、どれを主証とし、どこから処理するかを判断します。
2. 病機構造マトリクスの作り方
以下のように、症状・所見・舌脈をベースに5軸で整理します。
| 病機分類 | 主な所見 | 解釈 |
|---|---|---|
| 気虚 | 疲労感・軟便・声が小さい・舌淡 | 脾気虚 |
| 痰湿 | 胃もたれ・舌膩苔・脈滑 | 脾陽虚による水湿停滞 |
| 瘀血 | 月経血塊・下腹部刺痛・舌下怒張 | 肝鬱血瘀 |
| 気滞 | 腹部膨満・ため息・脈弦 | 肝気鬱結 |
→ このように整理すると、「気虚+痰湿」を主証、「瘀血+気滞」を副証と見なす判断が導けます。
3. 処方選択のための“弁証優先順位”を決める技法
- ① 生命活動の土台を先に処理:虚証(気血陰陽)→実証(邪実)
- ② 炎症・痛みなど急性症状を優先:清熱・活血・通便は初期に配置
- ③ 病因因子の除去が鍵:痰湿・瘀血が強ければ主証でなくとも初期に処理
- ④ 中心症状に最も貢献する証から選定:主訴と証構造の整合性を最重視
4. 臨床ケース:マトリクス→優先→処方決定の流れ
症例:疲労感+下腹部痛+食欲不振+月経異常
- マトリクス分析:
- 脾気虚(倦怠・軟便・食欲不振)
- 瘀血(月経痛・血塊・舌紫暗)
- 気滞(腹部張り・イライラ)
- 優先順位:
- ① 脾気虚 → 六君子湯系
- ② 瘀血 → 桂枝茯苓丸 or 温経湯
- ③ 気滞 → 香蘇散 or 加味逍遙散
- 処方例:
- 六君子湯+桂枝茯苓丸(合方) → 経過により加味逍遙散を追加検討
5. 弁証優先順位を診療に落とし込むテンプレート例
【主訴】疲労・月経不順・膨満感 【主証】脾気虚(六君子湯)+瘀血(桂枝茯苓丸) 【副証】気滞(未対応)/舌:淡+膩苔+瘀点/脈:滑・細 【処方戦略】補気+活血を先行。副証は改善が不十分な場合に再評価
終わりに
中医処方は「証に基づく」ものでありながら、現実には複数の証が混在したり、明確に主従が分けられないこともあります。
そのようなときにこそ、病機構造をマトリクスとして整理し、主証・副証・対症の優先順位を構造的に捉える技術が有効です。
本稿が、「何を治すか」「今はどこから処理するか」を構造的に判断する処方設計の技法として、臨床現場での漢方活用を支える一助となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ