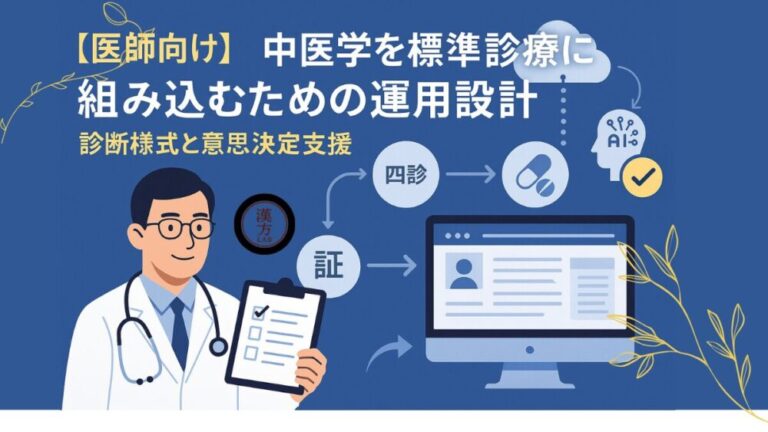中医学を標準診療に組み込むための運用設計──診断様式と意思決定支援
漢方は一部の医師にとって“経験と感覚の医療”である一方、他方では「科学的根拠に基づかない」「記録と再現が困難」と敬遠される場面も少なくありません。
中医学を現代の標準診療に組み込むには、診断様式の整備と意思決定の共有化が不可欠です。
本稿では、診断構造・カルテ記載・処方支援・診療プロトコルといった観点から、現代医療の中で中医学を運用するための設計技術を提案します。
1. 中医学を“再現性のある診療”にするには
中医診療が再現されにくい理由は以下の通りです。
- 診断に“用語のブレ”がある(例:気虚?脾虚?)
- 診察所見(舌・脈)が主観的かつ記録されない
- 処方が“術者の経験”に依存している
- カルテ記載が標準化されていない
これらを克服するには、診断構造を明文化し、意思決定プロセスを標準化する運用設計が必要です。
2. 中医的診断様式の標準構造
中医学の診断様式は、次の5階層構造で構成されます:
- 四診情報:望・聞・問・切
- 証分類:八綱・気血津液・臓腑・病因
- 証型表現:例:脾気虚・肝鬱気滞・瘀血阻絡など
- 治法:補気・活血・清熱・疏肝など
- 方剤設計:処方名+加減構造
この構造を明確にすれば、診断から処方までの一貫性が担保され、カルテ記載・共有・教育が容易になります。
3. 電子カルテ(EMR)での診断構造記録モデル
以下のようなテンプレートをEMRに統合することで、診療フローと連動した運用が可能です。
【四診所見】 望診:舌淡胖・苔白膩/聞診:声低・口臭なし 問診:倦怠、食欲低下、便溏/切診:脈滑細 【弁証分類】 八綱:虚・寒/臓腑:脾/気血:気虚 【証型】 脾気虚+痰湿内停 【治法】 補気健脾・化湿利水 【方剤】 六君子湯+温胆湯(合方設計)
カスタム項目として「中医弁証」「証型」「治法」などをカルテ内に設けることで、診療所内の共有と振り返りが容易になります。
4. 処方支援:意思決定支援(CDSS)の導入構想
中医的CDSS(Clinical Decision Support System)は以下の要素から構成されます。
- 入力:主訴・舌診・脈診・四診構造
- 演算:病機構造マッピング(AI or フレームベース)
- 出力:推定証/治法候補/処方候補(構造付き)
📌 例:入力→候補出力イメージ
【入力】 主訴:慢性倦怠・膨満・便溏・舌:白膩・脈滑 【推定】 証:脾気虚+痰湿阻中 治法:補気健脾・化湿 処方候補:六君子湯+温胆湯
AIではなくても、構造フローチャートをCDSS的に設計すれば、
若手医師や他職種の処方選定サポートとして極めて有効です。
5. 中医学を“標準診療フロー”に組み込む戦略
現場導入においては以下のような段階的構成が現実的です。
- ① 医師個人レベル:中医カルテテンプレートの導入(PDF/Word)
- ② チームレベル:四診記録・証分類共有テンプレートの使用
- ③ 医療機関全体:EMR連携カスタム項目の作成/院内教育資料整備
- ④ 外部連携:中医的記録をPDF出力→他院/薬局と情報共有
中医学が“感覚の医学”から“構造的診療体系”へと位置付け直されることで、
漢方はあらゆる診療科で運用可能な治療選択肢となります。
6. 診療教育・研修における標準化の意義
医師の経験や理解度に依存せず、中医学を再現可能な診療構造として普及させるには、テンプレートと意思決定支援が不可欠です。
- 症例ベース学習における構造テンプレートの活用
- 電子カルテ入力訓練とPDF記録への応用
- 診断→治法→方剤の一貫性チェック訓練
診療教育に標準構造を導入することで、中医学は“属人的な知識”から“組織的なスキル”へと進化します。
7. 中医学の構造実装に必要な4つの基盤
- 1. 診断構造の階層化:四診→弁証→証型→治法→処方
- 2. 所見記録の標準化:舌・脈・症状テンプレート
- 3. 意思決定フローの視覚化:構造図 or チャート
- 4. EMR・CDSSへの統合可能性:柔軟な実装設計
8. 終わりに
中医学は現代診療において“選択肢”ではなく、“再現可能な診断体系”として標準化されることで、その価値を最大限に発揮します。
そのためには、属人的な経験則から脱し、構造的診断・可視化された意思決定・共有可能な記録技術が求められます。
本稿が、中医学の未来に向けた診療設計の実装支援となり、現代医療と漢方の橋渡しとなれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ