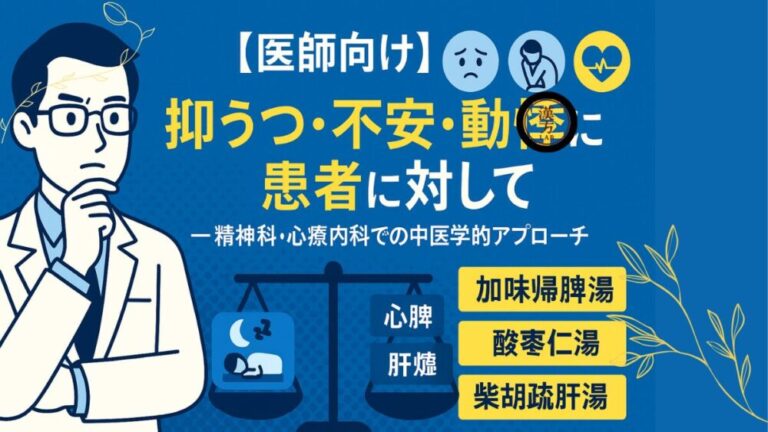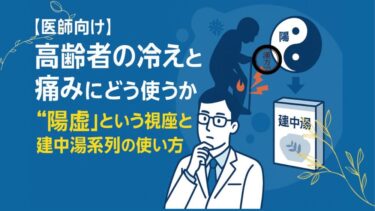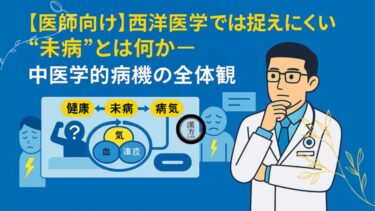抑うつ・不安・動悸に悩む患者に対して──精神科・心療内科での中医学的アプローチ
精神科・心療内科の診療現場では、「気分の落ち込み」「不安」「動悸」などの訴えが続き、既存の治療に反応が乏しい、または副作用の問題で薬剤調整が難航する例が少なくありません。
明確な診断名がついていても、「本人が納得できる改善感が得られていない」「説明しきれない不調が残る」状況は、臨床上よく経験されることと思われます。
中医学では、こうした心身の不調を「心神不寧(しんしんふねい)」「肝気鬱結(かんきうっけつ)」「脾気虚(ひききょ)」など、証に基づいた構造的な病機として捉え、方剤を選択する体系を持っています。
本稿では、精神症状を呈する患者に対する中医学的診立てと臨床応用の一端をご紹介いたします。
中医学における情志病の考え方
中医学では「五臓(心・肝・脾・肺・腎)」と「情志(感情)」は密接に関連し、特に「心・肝・脾」のバランスが情動の安定に関与しているとされます。
これに基づき、精神科的な症状も単一臓器に由来するものではなく、複数の臓腑機能の失調とみなしてアプローチが行われます。
| 証(しょう) | 主な症状 | 舌脈所見 |
|---|---|---|
| 心脾両虚 | 抑うつ、不眠、動悸、集中力低下、食欲不振 | 舌淡・苔薄/脈細弱 |
| 肝気鬱結 | イライラ、不安感、胸脇部張感、月経前悪化 | 舌やや紅・苔薄/脈弦 |
| 陰虚火旺 | 焦燥感、寝つきの悪さ、口渇、夢が多い | 舌紅少苔/脈細数 |
| 痰気内擾 | 思考の鈍さ、健忘、食欲低下、舌苔厚膩 | 舌胖・苔膩/脈滑 |
| 心胆気虚 | びくびくする、驚きやすい、不安、不眠 | 舌淡/脈虚 |
臨床での処方と適応例
- 加味帰脾湯:心脾両虚タイプに適応。抑うつ、不眠、動悸、胃腸虚弱を伴う患者に。
- 柴胡加竜骨牡蛎湯:肝気鬱結+痰火。焦燥感、怒り、不眠、便秘などが目立つ場合に。
- 酸棗仁湯:虚弱で繊細な体質、不眠、不安感に。過鎮静なく穏やかに働く。
- 天王補心丹:陰虚火旺に基づく不眠、動悸、夢が多く熟眠感のない症例に。
- 温胆湯:痰湿による思考の曇り、気力低下、胃腸症状を伴う抑うつ症状に。
いずれの処方も、単に「抑うつに効く」という選び方ではなく、症状の構成と体質、舌脈所見、消化機能、精神的背景までを総合的に判断して適応を検討します。
精神科薬物との併用・補助的役割
中医学処方は、必ずしも向精神薬の代替を意図するものではなく、西洋薬でコントロールしきれない症状の緩和や、離脱期の補助として併用されることが多いです。
- SSRI/SNRI併用時:開始初期の焦燥・不眠に対し、加味帰脾湯や酸棗仁湯が併用されるケースあり
- ベンゾジアゼピン減量時:不安感・不眠に対し、天王補心丹・帰脾湯で補助的に支援する例も
- 治療抵抗性うつ状態:痰湿の視点から温胆湯を加え、全身症状の改善を図る戦略
これらの併用においては、薬剤相互作用よりも、症状構成のズレを補正する“医学的視野の補完”としての役割が大きいと考えられます。
実際の処方導入と注意点
- 甘草・人参・当帰などの補剤成分:電解質異常、出血傾向のある症例には注意
- 継続投与が前提となるため、服薬アドヒアランスを高める工夫が求められる
- 舌診・脈診の代替として問診での冷え・のぼせ・口渇・食欲の有無などを丁寧に聞き取る
終わりに
抑うつや不安、動悸といった訴えは、多くの場合、情緒と身体が交錯した複雑な状態にあります。
中医学はこうした“構造化しにくい不調”を、気・血・津液・五臓のバランスという視点から整理し、個別化された介入につなげる理論体系を提供しています。
西洋医学と中医学はいずれも患者のQOL改善を目指す医療であり、補完的に用いることで、患者自身が「納得できる回復」を実感できる機会が増える可能性があります。
精神科・心療内科においても、こうした“もうひとつの見立て”が臨床の支えとなることを願っております。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ