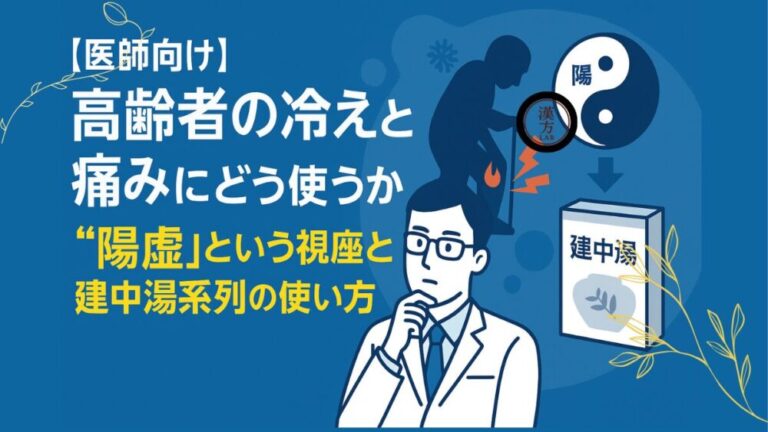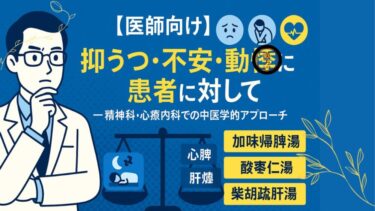高齢者の冷えと痛みにどう使うか──“陽虚”という視座と建中湯系列の使い方
高齢の患者が訴える「冷え」や「痛み」は、画像や血液検査で器質的な異常が見られないことも多く、治療方針に悩まれるケースがあります。
関節リウマチ、神経痛、脊柱管狭窄、循環不全などとの鑑別はもちろん重要ですが、加齢に伴う生理的低代謝・循環低下を背景とした症候であることも少なくありません。
中医学では、こうした状態を「陽虚(ようきょ)」という視座で捉え、体内の温煦(おんく)機能や血行動態の低下に着目します。
本稿では、とくに高齢者の冷えと慢性疼痛に焦点を当て、「建中湯系列」を中心とした処方活用の考え方をご紹介いたします。
陽虚とは何か──“あたためる力”の不足
陽虚は、中医学でいう「陽気(ようき)」が不足している状態を指します。陽気は体を温め、気血の流れを推進する力とされており、その減退は“冷え”や“痛み”といった症状として現れます。
加齢、慢性疾患、長期の活動低下などが陽虚の背景となることが多く、以下のような症状が見られる傾向があります。
- 四肢・腹部の冷え
- 慢性的な腰痛・関節痛・神経痛
- 動作緩慢、足元の不安定さ
- 軟便・下痢・夜間頻尿・浮腫
- 舌が淡く、脈が沈・遅・弱
中医学ではこうした病態に対し、「温補(おんぽ)」という治療戦略がとられます。これは、冷えを直接温めるだけでなく、身体の“熱を作る力”を高めるアプローチです。
建中湯系列の構造と適応
「建中湯(けんちゅうとう)」系列の処方は、陽虚による冷えと疼痛、さらに体力低下や消化力の衰えを伴う症例に用いられます。
以下は代表的な3処方の構成と使い分けです。
| 方剤名 | 主な適応 | 構成・特徴 |
|---|---|---|
| 小建中湯 | 小児・高齢者の虚弱・腹部冷痛・慢性疲労 | 芍薬・桂皮・膠飴で胃腸を温めつつ緊張を緩める |
| 大建中湯 | 術後・冷え・腹痛・下腹部の重だるさ | 附子・乾姜・人参で強力に温中散寒/腸蠕動促進効果あり |
| 当帰建中湯 | 冷え症・月経不順・血虚による痛み | 当帰を加え補血しつつ温中/瘀血傾向を伴う冷えに |
臨床応用例:高齢者の冷えと痛みへの対応
- 背部痛・慢性腰痛+冷え:当帰建中湯(瘀血・虚寒が併存するタイプに)
- 高齢女性・慢性便秘+冷え:大建中湯(腸蠕動促進を意識しつつ温補)
- 低体重・食欲低下+神経痛:小建中湯(補中+疼痛緩和)
- 関節リウマチ治療中・冷えが著明:桂枝加苓朮附湯との使い分けも検討
いずれも、「冷え」だけでなく、その背景にある体力や消化機能、血行動態、痛みの性状(鈍痛/刺痛)などを総合的に評価することが重要です。
服薬上の留意点と実地対応
- 小建中湯:甘味が強いため糖尿病・便秘傾向には注意。少量分割投与も選択肢。
- 大建中湯:附子含有のため心疾患・浮腫のある患者では慎重に。高齢男性での冷え症例に多用。
- 膠飴:膨満感や嘔気がある場合には消化機能が回復してから導入。
- 他剤併用時:鎮痛薬や利尿薬による脱水・低Kへの配慮。ACE阻害薬併用時は電解質バランスの確認を。
終わりに
高齢者の冷えと慢性的な痛みは、必ずしも器質的異常と一致しないまま長期化することが多く、治療の“すきま”に入り込む症状とも言えます。
こうした症状に対し、中医学の「陽虚」という視座を加えることで、見落とされがちな代謝力・循環機能の低下を評価・介入する道筋が見えてくる場合があります。
建中湯系列の処方は、温補と痛み緩和を同時に実現する処方群であり、高齢者の慢性症状に対する柔軟な対応を可能にします。
食欲・栄養状態・消化機能・ADLなどを総合的に判断しつつ、必要に応じてこうした“あたためる処方”を選択肢に加えていただければ幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ