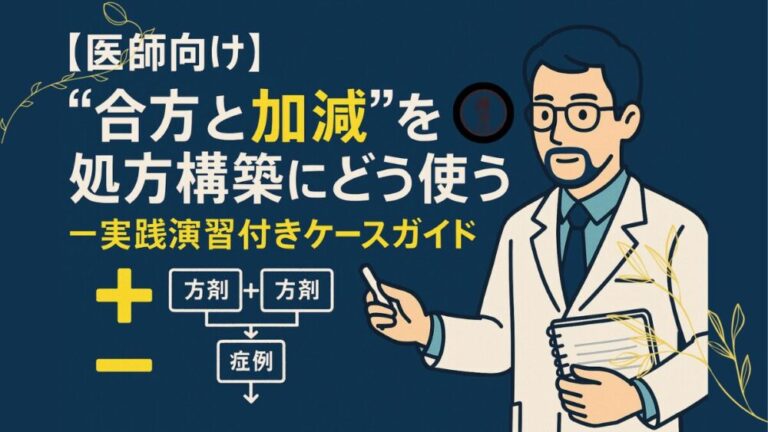目次
“合方と加減”を処方構築にどう使うか──実践演習付きケースガイド
現代の漢方診療では、「1つの証では治療しきれない」「処方単体では不十分」という症例が多く見られます。
こうした複合病態に対し、中医学では「合方(ごうほう)」と「加減(かげん)」という2つの処方構築技法が体系的に用いられてきました。
本稿では、合方・加減の基本理論、構造的判断法、そして臨床症例に基づく演習を通じて、
複雑な病機に対する中医学的処方構築力を高める技法を解説いたします。
1. 合方と加減の違いと目的
- 合方:2つ以上の既成処方を併用・統合する設計(例:六君子湯+温胆湯)
- 加減:既成処方に生薬を追加または削除する設計(例:加味逍遙散+酸棗仁)
合方は複数の証が併存する場合に用いられ、加減は処方の方向性を微調整する場合に適します。
2. 合方・加減を使うべき臨床状況
- 主証と副証が明確に分かれている(例:気虚+瘀血)
- 治療目標が段階的に変化する(例:補気 → 活血 → 理気)
- 市販・保険処方の単体では対処が難しい複合症状
- 体質補正(虚熱・寒湿・陰陽バランス)への調整
3. 処方構造の“役割別レイヤー化”
処方を構成する各生薬を「目的別」に分類し、設計図として明文化します。
【例:六君子湯+桂枝茯苓丸(合方)】 補気:人参・白朮・茯苓・甘草 化痰:半夏・陳皮 活血:桃仁・牡丹皮 理気:桂枝・茯苓 → 構造仮説:脾気虚+痰湿+瘀血
このように、病機に対応した“治法レイヤー”を可視化することで、論理的かつ柔軟な処方構築が可能となります。
4. 病機別:合方設計の代表パターン
| 病機構造 | 合方例 | 処方意図 |
|---|---|---|
| 気虚+痰湿 | 六君子湯+温胆湯 | 補気健脾+化痰清熱 |
| 肝鬱+血虚+瘀血 | 加味逍遙散+桂枝茯苓丸 | 疏肝理気+活血調経 |
| 腎陰虚+虚熱+不眠 | 知柏地黄丸+酸棗仁湯 | 滋陰清熱+養心安神 |
| 脾腎陽虚+水滞 | 真武湯+苓桂朮甘湯 | 温補陽気+利水化飲 |
5. 症例で学ぶ:処方構築の演習ガイド
■ 症例1:疲労+下腹部痛+月経異常
- 主訴:月経不順・PMS・冷え・倦怠
- 所見:舌淡・脈細滑・瘀点
- 弁証:脾気虚(主)+瘀血(副)+軽度肝鬱
- 治法:補気・活血・疏肝
- 合方例:六君子湯+桂枝茯苓丸+加味逍遙散(部分合方)
■ 症例2:不眠+焦燥感+寝汗
- 主訴:睡眠不良、焦燥、寝汗、虚熱
- 所見:舌紅・脈数・裂紋舌
- 弁証:心腎不交/陰虚火旺
- 加減例:知柏地黄丸+酸棗仁・夜交藤を加味
6. 合方・加減時の注意点と調整技術
- 味数制限:15味以上になると処方がぼやけやすい
- 薬味の重複:同一機能の生薬は統合・精選(例:茯苓・白朮)
- 毒性・相互作用:附子・大黄などの併用には留意
- 段階的導入:副証対策は症状軽減後に追加可能
7. 合方設計のテンプレート記載例
【主訴】疲労・膨満・月経痛 【弁証】脾気虚+痰湿+瘀血 【治法】補気健脾・化湿・活血 【合方】六君子湯+温胆湯+桂枝茯苓丸 【構成意図】 ・補気(人参・白朮・茯苓・甘草) ・化湿(半夏・陳皮・茯苓・生姜) ・活血(桂枝・牡丹皮・桃仁) 【評価指標】PMS軽減・腹部所見・苔厚・舌色
8. 合方を学ぶ上での思考手順(演習用)
- 主訴・症状群から仮説証を設定する
- 構造的病機(主証・副証)を分解する
- 治法を列挙し、必要な処方ユニットを決定
- 合方/加減の構成と順序を設計
- 診断仮説→処方構成→方剤説明まで言語化
演習課題例:
【課題】主訴:慢性胃痛・軟便・冷え/舌:淡+膩苔/脈:滑・弱 → 病機仮説・治法・処方候補・構成意図を整理せよ
9. 終わりに
合方と加減は、中医学の処方設計における“構造的柔軟性”の核心です。
それは単なる処方の足し引きではなく、診断構造と治療目的を翻訳する設計技法に他なりません。
本稿が、実臨床において複雑な病機に対峙する医師にとって、「論理と応用の両輪」で処方を構築する指針となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ