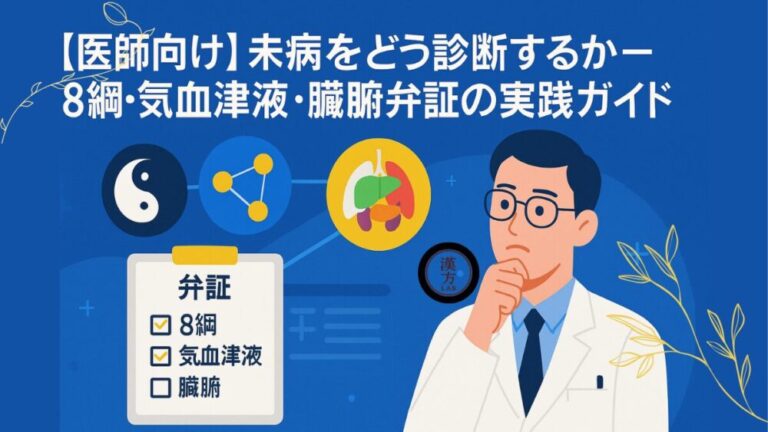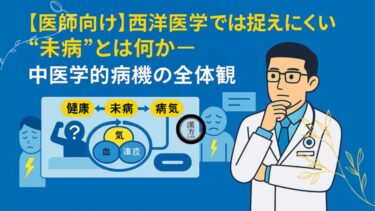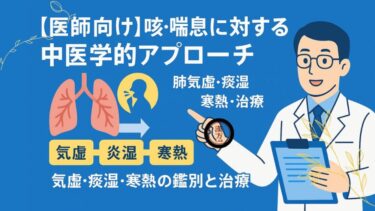未病をどう診断するか──8綱・気血津液・臓腑弁証の実践ガイド
「不定愁訴」と呼ばれる訴えは、現代医学において診断や治療の指針を持ちにくい領域です。
疲労、冷え、不眠、食欲不振、便通異常、月経前の不快感といった症状があるにもかかわらず、明確な疾患単位に分類できないことは少なくありません。
中医学では、こうした状態を「未病(みびょう)」と捉え、体内の機能的失調を“証(しょう)”として整理し、治療や生活指導の方向性を導き出します。
本稿では、中医学的弁証の基本構造(8綱、気血津液、臓腑)を通じて、未病状態をどう評価し、どのように診療に活かすかを解説いたします。
1. 弁証論治とは──中医学の診断体系
弁証論治(べんしょうろんち)とは、中医学における診断と治療設計の中核概念であり、症状や舌脈所見などを統合して病機(=証)を導き出し、方剤や生活指導の方向性を決めるプロセスです。
弁証は「病態構造の見立て」であり、論治は「それに基づく治療戦略」を指します。
2. 八綱弁証──病態の枠組みを立てる基本構造
8綱とは、以下の4対8項目の病態の方向性を分類する枠組みです:
- 陰・陽:全体的な病性(寒・熱、内・外、虚・実の総合)
- 表・裏:病変部位(体表か、臓腑・深部か)
- 寒・熱:冷え・のぼせ、発熱・冷感などの寒熱状態
- 虚・実:正気(身体の力)と邪気(病因)の力関係
例:冷え性・疲労・顔色不良 → 「裏寒虚(=陽虚)」と判断。
これにより、単なる症状ではなく“温煦機能の低下した体内の病機構造”として治療戦略を組むことができます。
3. 気血津液弁証──構成要素の量と流れを診る
中医学では人体を構成する基本物質として「気・血・津液」があり、それぞれの量・質・流れの異常が未病の背景にあるとされます。
| 分類 | 主な症状 | 代表処方例 |
|---|---|---|
| 気虚 | 倦怠感・風邪をひきやすい・息切れ | 補中益気湯・六君子湯 |
| 血虚 | 不眠・めまい・月経量少・皮膚乾燥 | 当帰芍薬散・帰脾湯 |
| 気滞 | イライラ・胸脇部の張り・便秘傾向 | 加味逍遙散・香蘇散 |
| 瘀血 | 慢性痛・冷え・月経血塊・暗紫舌 | 桂枝茯苓丸・温経湯 |
| 痰湿 | 頭重・浮腫・胃もたれ・苔膩 | 平胃散・半夏白朮天麻湯 |
これらの弁証は、“何が不足し、何が巡っていないか”という構造的理解に役立ち、生活指導・栄養指導とも連動しやすい特徴があります。
4. 臓腑弁証──症状を内臓機能の失調として捉える
臓腑弁証では、五臓六腑の機能異常を整理し、症状を構造的に紐づけます。特に、肝・心・脾・肺・腎の失調は多くの未病に関与します。
- 肝鬱:ストレス・月経前不調・気滞傾向
- 心血虚:不眠・動悸・集中困難
- 脾虚:食欲不振・疲労・浮腫・軟便
- 肺気虚:感冒反復・皮膚乾燥・呼吸浅
- 腎虚:冷え・頻尿・足腰のだるさ・性機能低下
各臓器に対応する“気血津液の異常”を組み合わせることで、証の立体構造が明確になります。
5. 未病への介入:診断と治療設計
弁証によって証が明確になれば、対応すべき方向性が定まります。以下は一例です:
- 脾気虚+痰湿 → 六君子湯
- 肝鬱血虚 → 加味逍遙散
- 腎陽虚+瘀血 → 八味地黄丸+桂枝茯苓丸
- 気虚+陰虚 → 補中益気湯+知柏地黄丸
同じ「不眠」でも、心血虚・肝鬱・陰虚・痰熱など背景によって処方は異なり、これが弁証論治の本質です。
終わりに
中医学の弁証は、病名の代替ではなく、患者の訴えを構造的に捉え、身体全体のバランスを評価する補助軸です。
臨床において「診断はあるが、治療が響かない」「訴えに説明がつかない」場面において、弁証による見立ては診療の幅を広げる可能性があります。
「未病を治す」とは、予防だけでなく、患者自身の身体感覚に意味を与える医療でもあります。
ぜひ診療の一助として、弁証論治の視座をご活用いただければ幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ