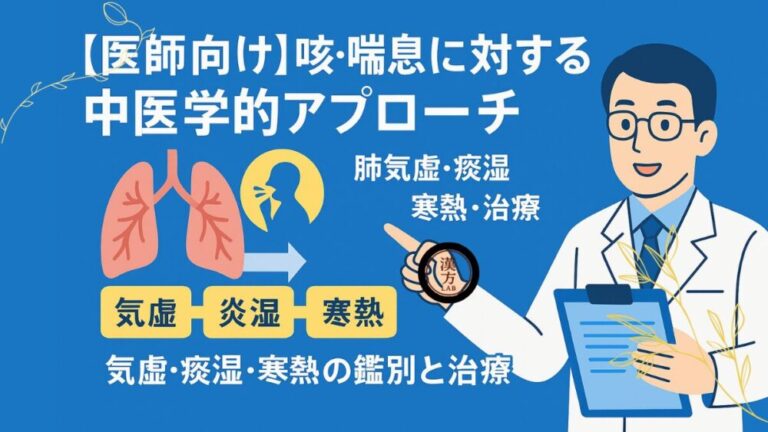目次
咳・喘息に対する中医学的アプローチ──肺気虚・痰湿・寒熱の鑑別と治療
咳嗽や喘鳴は、呼吸器疾患だけでなく心因性やアレルギー性、感染後遷延など多様な病態に関与する症状です。
現代医学的にはICS(吸入ステロイド)や抗アレルギー薬による制御が標準ですが、いずれの治療でも奏功しない“慢性咳”“非器質性喘鳴”は臨床でしばしば遭遇します。
中医学では、咳は「肺失宣降」「邪犯肺系」の結果とされ、肺の宣発粛降機能の失調によって引き起こされると考えます。
本稿では、咳嗽・喘息の症候を肺気虚、痰湿、寒熱の3軸から病機的に整理し、代表処方と臨床適応を解説します。
中医学における「咳」の分類と発症機構
中医学では「肺は気を主り、声を司る」とされ、肺の気機が乱れると咳嗽や喘鳴が生じるとされます。
以下は主な発症病機の分類です:
- 肺気虚:肺の防御力・粛降機能低下(易感冒・慢性咳)
- 痰湿阻肺:脾虚や外湿が痰となり肺気を塞ぐ(湿咳・咳痰)
- 風寒犯肺:外感寒邪による急性咳(悪寒・透明痰)
- 風熱犯肺:外感熱邪(発熱・黄痰・咽痛)
- 陰虚燥熱:乾咳・夜間咳・声枯れ(肺陰虚)
同じ“咳”であっても、その背景病機により診断と治療戦略は大きく異なります。
病機別の臨床像と代表処方
| 病機 | 主症状 | 処方例 |
|---|---|---|
| 肺気虚 | 息切れ、声が小さい、風邪をひきやすい、慢性咳 | 補中益気湯、玉屏風散、麦門冬湯 |
| 痰湿阻肺 | 咳とともに白色の痰、胃もたれ、頭重感 | 二陳湯、温胆湯、半夏白朮天麻湯 |
| 風寒犯肺 | 発熱なし/悪寒強、咳、水様鼻汁、透明な痰 | 麻黄湯、三拗湯、麻黄附子細辛湯 |
| 風熱犯肺 | 発熱・咽頭痛・黄痰・咳嗽 | 銀翹散、麻杏甘石湯、桑菊飲 |
| 肺陰虚(燥咳) | 乾いた咳、声枯れ、寝汗、頬紅 | 麦門冬湯、百合固金湯、滋陰降火湯 |
慢性咳・喘息における活用例
■ 感冒後の遷延性咳嗽(風寒 → 肺気虚)
- 初期:麻黄湯・葛根湯などで寒邪を祛す
- 遷延:補中益気湯+麦門冬湯で肺気を補う
■ 小児喘息・反復性咳嗽
- 体質:脾肺気虚+痰湿傾向
- 処方:玉屏風散(予防)+二陳湯または温胆湯(発作期)
■ 高齢者の夜間咳・声枯れ
- 背景:肺陰虚・虚熱
- 処方:麦門冬湯、滋陰降火湯、天王補心丹
処方選択の実際と注意点
保険適用される処方のうち、代表的なもの:
- 麦門冬湯(ツムラ29)…乾咳・虚弱者の咳に
- 麻杏甘石湯(27)…実熱の咳(喘息にも応用)
- 温胆湯(ツムラ74)…痰湿+胃内停水に
- 補中益気湯(41)…肺気虚を伴う慢性咳・虚弱児
留意点:
- 痰熱が優位な例に補剤を使用すると悪化する場合あり
- 甘草・麻黄含有の処方は高齢者・心疾患で用量調整を
- 複数処方の併用は、証の整合性を重視(例:麦門冬湯+補中益気湯)
終わりに
咳嗽・喘鳴は、現代医学においても病因が不明確なケースが多く、標準治療で反応しない“診療のすき間”にあたることがあります。
中医学の視点では、咳の背後にある「肺の宣発粛降機能の失調」を弁証し、個別の病機に応じた処方を選択することで、治療の幅を拡げることが可能です。
肺気虚・痰湿・寒熱といった視座は、症状を“現象”ではなく“構造”として捉える手段であり、難治性の咳・喘息に対する補完的診療の一助となり得ると考えます。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ