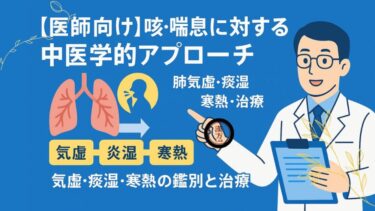“虚実の混在”をどう扱うか──多症状・多病態患者への中医学的統合戦略
現代臨床では、高齢者や慢性疾患を有する患者において、複数の症状・病態が同時に存在し、診断・治療の方針が複雑化する場面が少なくありません。
「疲れやすく冷える一方で、腹部膨満やイライラもある」「下痢と便秘を繰り返す」「精神不安と過敏性が混在する」といった例では、西洋医学的に原因を一本化することが困難なケースもあります。
中医学では、こうした病態を「虚実錯雑(きょじつさくざつ)」と捉え、虚(不足)と実(過剰)の病機が同時に存在する状態として診立てます。
本稿では、虚実混在の診断と治療をどのように構造的に整理し、処方選択に落とし込むかを解説いたします。
虚実錯雑とは何か──2つの病態が重なる構造
中医学では、「虚」=正気の不足、「実」=邪気の停滞・充満を意味します。
虚実錯雑とは、例えば「気虚がベースにあるが、気滞や瘀血が上乗せされている」ような状態を指します。
よくある虚実錯雑の組み合わせ:
- 気虚 + 気滞(例:疲労+腹部張満+抑うつ)
- 血虚 + 瘀血(例:めまい・不眠+月経痛・肩こり)
- 脾虚 + 痰湿(例:食欲低下+咳痰・めまい・重だるさ)
- 腎虚 + 陰虚内熱(例:夜間頻尿+寝汗・のぼせ)
- 陽虚 + 寒凝瘀血(例:冷え+慢性痛・関節拘縮)
臨床での鑑別ポイントと組み立て
診断時には、まず「どこに虚があり、どこに実があるか」を明確にします。
- 全身所見:疲労、冷え、食欲、睡眠など → 虚証の有無
- 局所症状:痛み、張り、咳、痰、便秘など → 実証の程度
- 舌脈所見:舌淡・無苔・脈細 → 虚、舌紫・苔膩・脈弦滑 → 実
虚実が拮抗している場合は「虚実同治」、虚が優位であれば「補を主とし瀉を佐とする」、実が優位なら「瀉を主とし補を佐とする」という治則を使います。
処方設計の基本戦略:虚実同治
虚実が混在する場合、単一処方では対応困難なため、複数方剤の組み合わせが有効です。
| 証構成 | 処方組み合わせ例 | 適応臨床像 |
|---|---|---|
| 気虚+気滞 | 補中益気湯 + 香蘇散 | 疲労+腹満+食欲不振+抑うつ傾向 |
| 血虚+瘀血 | 帰脾湯 + 桂枝茯苓丸 | 冷え性・不眠・月経不順・慢性痛 |
| 脾虚+痰湿 | 六君子湯 + 温胆湯 | 食欲低下+痰咳+めまい+浮腫 |
| 腎虚+内熱 | 六味丸 + 知柏地黄丸 | 高齢・慢性疾患・寝汗・口渇・のぼせ |
実臨床での応用例
■ 高齢者のADL低下+慢性便秘+イライラ
→ 気血両虚+気滞 → 十全大補湯+香蘇散
■ 更年期の不眠・抑うつ+月経痛・冷え
→ 心脾両虚+瘀血 → 加味帰脾湯+桂枝茯苓丸
■ 生活習慣病合併患者の疲労+胃内停水+動悸
→ 脾気虚+痰湿 → 六君子湯+半夏厚朴湯
注意点:虚実の“優劣”と使用タイミング
- 補剤(人参・当帰・地黄など)使用時、消化機能低下・痰湿傾向には注意
- 瀉剤(実証用)の長期使用は虚証を悪化させうる
- 初期:虚実両方が強いときは「和解」処方から導入(例:加味逍遙散)
- 後期:証が明瞭になれば単剤へ収束可能
終わりに
複数の症状を持つ患者に対し、中医学の「虚実錯雑」の視座を導入することで、それぞれの訴えを病機的に分類し、治療戦略を立てることが可能になります。
補剤・理気剤・活血剤・燥湿剤などを、病機に応じて組み合わせることで、現代医学が“まとめきれない”多様な症候群に対応する補完医療として、中医学的アプローチは大きな可能性を持っています。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ