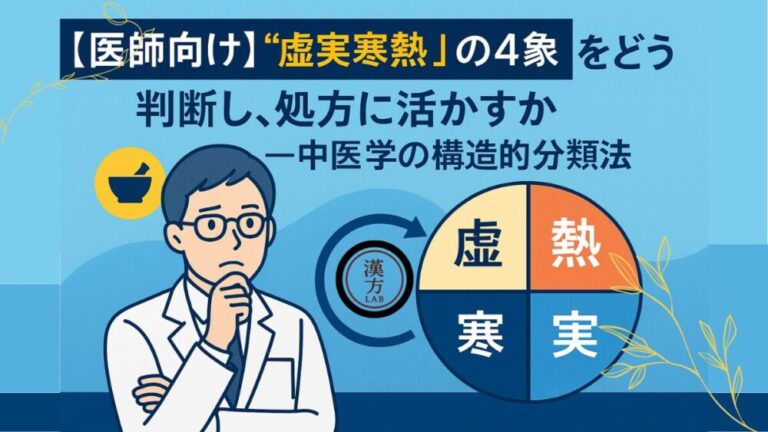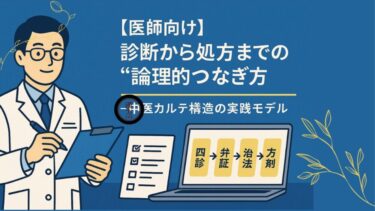“虚実寒熱”の4象をどう判断し、処方に活かすか──中医学の構造的分類法
「この患者は虚証なのか?」「寒熱どちらを主体に診るべきか?」──
中医学診療を行う医師にとって、虚・実・寒・熱の4象(ししょう)は診断と処方をつなぐ根幹にあたる構造判断軸です。
しかし、複雑な現代の患者では「虚中の実」「寒熱交錯」「実証だが慢性」など、明確な4象分類が難しいケースも多く見られます。
本稿では、四象の構造的理解と診断技術、さらに処方構成との論理的接続法を、
臨床の観点からわかりやすく整理し、症例ベースで活用法まで展開いたします。
1. なぜ“四象”が中医学診断の基本構造なのか
中医学では、病の本質を「虚」「実」「寒」「熱」の4つの状態として把握します。
これがいわゆる「四象」であり、以下のように区分されます。
- 虚証:正気(体力・恒常性)の不足による病態(気虚・血虚・陰虚・陽虚)
- 実証:邪気(病因)の亢進・停滞による病態(痰湿・瘀血・気滞・熱邪など)
- 寒証:機能低下・代謝鈍化・冷え(陽虚・外寒侵襲など)
- 熱証:亢進・炎症・口渇・のぼせ(実熱・虚熱いずれも含む)
中医診断の基本は、まずこの4象を判断し、その後に気血津液・臓腑病機などの詳細へ進みます。
逆に言えば、四象の判断が狂えば、すべての診断と処方がズレてしまいます。
2. 各象の特徴と誤診されやすいパターン
| 分類 | 主な所見 | 誤診されやすい例 |
|---|---|---|
| 虚証 | 倦怠感、食欲低下、軟便、息切れ、寝汗、舌淡、脈細 | 元気そうな人に見える虚(気虚・陰虚) |
| 実証 | 膨満、疼痛、怒りっぽさ、痰が多い、苔厚、脈滑・実 | 虚実交錯や慢性経過の実証を虚と誤る |
| 寒証 | 四肢冷、白色分泌物、清涼志向、便溏、脈遅 | 陽虚と寒邪の鑑別誤り |
| 熱証 | 発熱、口渇、便秘、尿濃、舌紅、脈数 | 虚熱と実熱の混同 |
3. 判断のための四診情報整理法
虚実寒熱の判断は、問診と舌・脈診によって構造的に把握されます。
- 問診:冷熱感、疲労の有無、疼痛の性質、便通、睡眠、情緒
- 舌診:色(淡=虚/紅=熱)、苔(白=寒/黄=熱)、形状(胖=虚/瘀点=瘀血)
- 脈診:細=虚、弦=気滞、滑=痰湿、遅=寒、数=熱
特に虚実は「反応性(強さ)と残存機能(体力)」のバランスで判断し、
寒熱は「代謝方向と局所所見(舌・便・尿・分泌物)」で判断します。
4. 四象マトリクスによる処方選定モデル
診断の四象と処方の機能分類を結びつけて考えます。
| 象 | 主な治法 | 代表的処方 |
|---|---|---|
| 虚 | 補気・補血・養陰・温陽 | 補中益気湯、十全大補湯、六味丸、八味丸 |
| 実 | 瀉火・清熱・化痰・理気・活血 | 黄連解毒湯、温胆湯、桂枝茯苓丸、柴胡疎肝散 |
| 寒 | 温裏・散寒・温陽 | 附子理中湯、真武湯、桂枝湯 |
| 熱 | 清熱・涼血・瀉火・養陰 | 白虎加人参湯、黄連解毒湯、知柏地黄丸 |
5. 複合証における象の階層化
多くの症例では「虚熱」「実寒」などが混在し、四象の単独分類では処理しきれません。
この場合、階層構造(主象/副象)を明示し、どの象を中心に治療を構築するかを明らかにする必要があります。
■ 例:腎陰虚+虚熱+瘀血
- 主象:虚証(腎陰虚)
- 副象:熱証(虚熱)+実証(瘀血)
- 治法:滋陰清熱+活血(六味丸+知柏+桂枝茯苓丸)
6. 症例で学ぶ“象”の使い方
■ 症例1:虚実交錯(気虚+瘀血)
→ 主証:気虚、補中益気湯を軸に、桂枝茯苓丸を併用
■ 症例2:実証急性型(熱証)
→ 主証:熱、銀翹散、黄連解毒湯などで清熱瀉火
■ 症例3:虚寒+痰湿
→ 真武湯+温胆湯を合方(温補と化痰を併用)
■ 症例4:陰虚+実熱
→ 主証:陰虚、六味丸+知柏で虚熱処理、急性期には白虎湯系で熱下げる
7. 終わりに
中医診断のすべては「虚実寒熱」の構造判断から始まります。
四象を見誤れば、どんな詳細な弁証も、どれだけ適切な方剤知識も、空回りしてしまいます。
本稿が、日々の臨床において「まず四象から」という判断リズムを取り戻すきっかけとなり、処方選定の精度と説明力を高める一助となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ