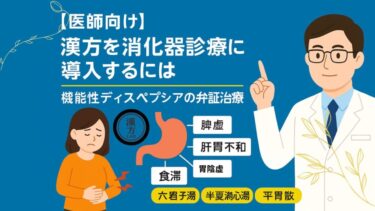月経トラブルとPMSへの介入──“気血失調”としての中医学的戦略
月経不順や月経随伴症状、さらには月経前症候群(PMS)は、多くの女性が経験する身近な症状でありながら、その訴えの多様性と変動性から、標準化された介入が困難な領域でもあります。
臨床では、低用量ピル(LEP製剤)や抗うつ薬、漢方薬が選択されることもありますが、いずれも効果には個人差があり、治療の継続性や満足度には課題も残されています。
中医学では、月経異常やPMSを「気血の失調」による病態として位置づけ、気・血・肝・脾・腎の連関から構造的に捉え直すアプローチがとられます。
本稿では、PMSおよび月経関連症状に対する中医学的な分類と、臨床応用可能な方剤の概要をご紹介いたします。
中医学における「気血失調」と女性の生理
中医学では、「女子は以血を本とす」とされ、血の充実と円滑な運行が月経の調和を支える基盤と考えられています。
一方で、血は単独で循環せず、気の推動作用(動かす力)や固摂作用(漏れを防ぐ力)に支えられています。
PMSや月経不順が生じる背景には、「気滞」「血虚」「血瘀」「脾虚」「腎虚」といった失調が複合的に関与しており、症状の訴え方や時期によって変化するため、病機の見立てが重要とされます。
PMSと月経異常の中医学的分類
| 証(しょう) | 典型症状 | PMS分類との対応 |
|---|---|---|
| 肝気鬱結 | 月経前の胸脇部張痛、怒りっぽさ、ため息 | PMS-A(情緒不安・易怒) |
| 血虚 | 月経量少、顔色不良、不眠、集中困難 | PMS-D(抑うつ・疲労) |
| 気滞血瘀 | 月経困難症、下腹部の刺痛、血塊 | PMS-M(混合型) |
| 脾気虚 | 出血過多、倦怠感、食欲低下、浮腫傾向 | 月経過多型、慢性PMSの基盤として |
| 腎虚(腎陽・腎陰) | 周期の乱れ、冷え、腰膝のだるさ、不妊傾向 | 40代以降、PMS様症状の持続例に |
中医学的証に対応する代表処方
- 加味逍遙散:肝気鬱結に基づく情緒変動、月経前のイライラ、不安感、冷えのぼせを伴うタイプに。
- 当帰芍薬散:血虚と水湿の停滞が関与するめまい・倦怠感・むくみ。体力低下型のPMSや月経不順に。
- 桂枝茯苓丸:下腹部痛、経血に塊、下腹部抵抗が明らかな瘀血証に。月経痛の訴えが強い場合に検討。
- 帰脾湯:心脾両虚に対応。不眠・健忘・抑うつ傾向・月経過多など、PMS-Dタイプに応用。
- 温経湯:寒冷と血瘀を伴う月経不順、不妊、慢性骨盤痛に。冷えが著明な場合に適応。
証の見立ては、PMS分類の補助線として活用でき、特にPMS-A(怒り型)とPMS-D(抑うつ型)の鑑別においては処方選択に直結します。
婦人科治療との併用における留意点
- LEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬)使用例では、肝代謝・甘草含有製剤(例:加味逍遙散)の長期投与に留意。
- 鉄剤処方中のケースでは、当帰・熟地黄などの補血薬との併用による便秘リスクへの配慮が求められます。
- 排卵誘発中/体外受精準備中の不妊治療中患者には、周期に応じた方剤選択と適切な中止タイミングの判断が重要。
- 市販漢方薬(女性保健薬など)との重複服用が想定される場合、医師主導の処方である旨を明確に説明する必要があります。
終わりに
月経関連症状やPMSは、ホルモン療法で一律に対応できるものではなく、患者個人の訴えや体質・生活背景に即した診療が求められます。
中医学の「気血」の視点を導入することで、訴えの多層性を構造化し、方剤による個別対応の道筋が見えてくることもあります。
PMS-A、PMS-Dといった西洋医学的分類に対し、中医学は補完的な分類軸として、診断や薬物選択の精度を高める可能性があります。
とくにLEP開始前、または精神科治療導入前の段階において、安全性と受容性の高い処方戦略として検討いただければ幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ