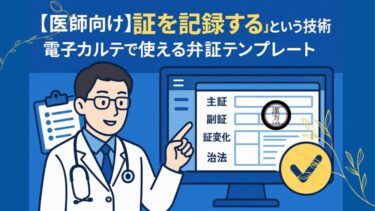目次
中医的診断に慣れない医師のための“証の読み方”初期ガイド
「漢方薬を使ってみたいが、どう“証”を読めばよいか分からない」「中医学の診断は曖昧で主観的に思える」──
そう感じる医師は少なくありません。
しかし、中医学における「証(しょう)」とは、単なる印象や症状の組み合わせではなく、臓腑・気血・寒熱・虚実といった病機構造の組織的な診断単位です。
本稿では、初学者でも中医的診断を読み取れるよう、証の構造・見立て・導入プロセスをやさしく分解し、「中医学の診断を使い始めるための最初の道筋」をご案内します。
1. 中医の「証」とは何か?──診断名ではなく“病機構造”
中医学では、証とは「今、この患者の中で起きている病理の構造的な状態」を指します。
たとえば「脾気虚」という証は、以下のような所見が集まった状態として構成されます:
- 主訴:疲れやすい、食後の膨満、便がゆるい
- 舌診:舌が淡く、やや胖大、白膩苔
- 脈診:虚弱、緩
これらの所見を「脾の運化作用が弱り、気の生成が低下している」と構造的に解釈し、「脾気虚」という証が成立します。
2. “証の読み方”5ステップ──初診での基本フロー
以下の手順で、初心者でも証を見立てることが可能です:
① 主訴を3軸で分類する
主訴・随伴症状を以下に当てはめる:
- 冷熱軸:冷え、のぼせ、発熱、悪寒
- 虚実軸:疲労感、腹満、便秘、痛み
- 気血水軸:動悸、めまい、浮腫、口渇、皮膚の乾燥
② 舌と脈の観察
- 舌診:色(淡紅/紅/紫)、苔(白/黄/膩/剥落)
- 脈診:細・滑・虚・数・遅・弦など(触れやすさ・速さ・張り)
③ 情報を“証の構造”にマッピング
分類表で統合する:
主訴:疲労感+軟便 舌:淡胖+白苔 脈:虚・滑 → 構造仮説:脾気虚+痰湿
④ 仮証として処方設計(診断確定ではなく“仮説”)
例:六君子湯(脾気虚+痰湿)を2週間試行し、反応を見る。
⑤ 再診で証を再評価・修正
症状の変化、舌苔・脈の動きから、証の推移や副証の顕在化を捉え、処方を再設計。
3. “証の型”から入る診断支援一覧(初心者用)
| 代表的証 | 主症状 | 処方例 |
|---|---|---|
| 気虚 | 疲労、食欲不振、声が小さい | 補中益気湯、六君子湯 |
| 血虚 | めまい、顔色不良、不眠 | 当帰芍薬散、加味帰脾湯 |
| 陰虚 | 寝汗、口渇、のぼせ | 麦門冬湯、知柏地黄丸 |
| 痰湿 | 重だるい、舌苔が厚い、咳痰 | 温胆湯、半夏白朮天麻湯 |
| 瘀血 | 刺痛、月経血塊、舌下怒張 | 桂枝茯苓丸、温経湯 |
4. 初学者がつまずきやすいポイントと対策
- “病名=証”と思い込まない:診断名ではなく「体の状態構造」を読む
- 主訴だけで証を即断しない:随伴症状と舌脈の統合が必須
- 副証や混合証に無理に対応しない:まず主証だけを捉えて処方→次に副証を処理
- “効かなかった処方”を失敗と見なさない:証の再評価→修正が中医の本質
終わりに
中医学の診断は、“証を読む”という構造的診断思考に他なりません。
それは、症状の背景にある全体の病理構造を仮説として描き、それに応じて治療戦略を立て、反応をみて修正するという“動的な診断プロセス”です。
本稿が、中医的診断に初めて触れる医師にとって、“証”を捉える第一歩の技術となり、今後の診療の幅を広げるきっかけとなれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ