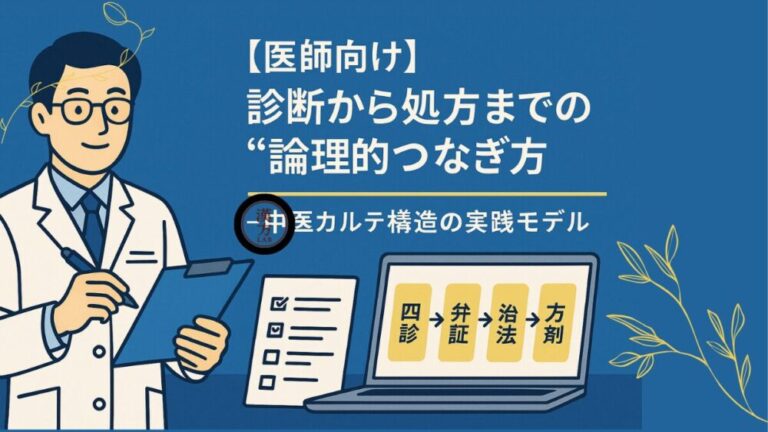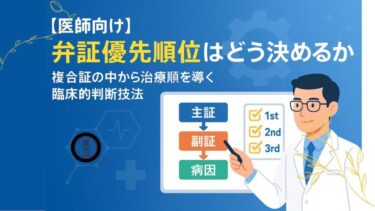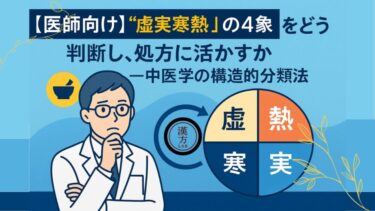診断から処方までの“論理的つなぎ方”──中医カルテ構造の実践モデル
漢方診療において、「診断(弁証)はあるが、なぜその処方になるのか説明しにくい」──
このような課題は、臨床現場でも研修教育の場でも頻繁に生じます。
中医学では、問診・舌脈・体表所見から得られる情報をもとに証(病機構造)を立て、
そこから治療方針(治法)を導き、最終的に処方(方剤)へと論理的につなげていく診療構造が前提となっています。
本稿では、四診→弁証→治法→方剤という中医学の診療構造を、
実際のカルテ構造にどう落とし込むかという視点で体系的に解説し、診断から処方までの論理的橋渡しを実践的に示します。
1. 診断と処方が“飛び地”になっていないか?
多くの臨床現場では、症状の羅列と処方の選択がカルテ上で断絶しています。
弁証は行われていても、そこから「なぜこの処方か」が記録されていないため、処方の妥当性・再評価・教育的共有が困難になっています。
そこで必要なのが、診断構造そのものを記録し、処方との論理接続を明確にする“中医カルテ構造”です。
2. 中医学の診療フロー:四診 → 弁証 → 治法 → 方剤
- 四診:望診・聞診・問診・切診による情報収集
- 弁証:八綱・気血津液・臓腑・病因弁証などで構造を仮説化
- 治法:補・瀉・疏・清・温・養などの治療方針の設定
- 方剤:治法を実現するための処方設計(既存方・加減・合方)
このプロセスを踏むことで、「診断→処方」が直線的に結ばれた、再現性の高い診療記録となります。
3. カルテに記録すべき“診断構造”の5要素
- ① 主訴+随伴症状:主訴と症状の相関を明記
- ② 証構造(主証・副証):併存する証を整理
- ③ 舌・脈所見:弁証の根拠として記録
- ④ 治法:治療方針を構文レベルで記述(例:補気健脾・化湿)
- ⑤ 方剤構成:処方名+目的別加減の意図を明記
【主訴】疲労感、膨満感、月経困難 【証】脾気虚+痰湿+瘀血 【舌脈】舌淡胖+白膩苔+瘀点/脈滑細 【治法】補気健脾・化湿・活血 【処方】六君子湯+桂枝茯苓丸(合方)+陳皮加味
4. 実例:診断から処方までを論理的につなぐ
■ 症例:
30代女性/主訴:月経不順、イライラ、不眠、冷え、疲労感
■ 四診情報:
- 問診:月経周期延長・精神不安定・食欲不振・冷え症
- 舌診:淡紅、薄白苔、瘀点あり
- 脈診:細弦
■ 弁証:
- 主証:肝鬱気滞+血虚
- 副証:瘀血・軽度の脾虚
■ 治法:
疏肝理気・補血安神・活血
■ 方剤:
- 加味逍遙散(疏肝+補血+安神)
- 桂枝茯苓丸(活血・理気)
- 麦門冬湯より酸棗仁を加味(安神・滋陰)
■ カルテ記録例:
【主訴】月経遅延・情緒不安・不眠 【証】肝鬱気滞+血虚+瘀血 【治法】疏肝理気・補血安神・活血 【方剤】加味逍遙散+桂枝茯苓丸+酸棗仁(加味) 【評価指標】月経周期・PMS・睡眠の質・苔と脈の変化
5. 処方の“目的別構成”を明示する技術
診断が論理的であっても、処方が“ごちゃ混ぜ”になっていると伝わらず、教育的にも曖昧になります。
そのため、処方構成は以下のように「目的別パート」に分けて記述することが推奨されます。
【補気】:人参、白朮、茯苓、甘草(→脾気虚) 【化湿】:陳皮、半夏(→痰湿) 【活血】:桃仁、牡丹皮(→瘀血) 【安神】:酸棗仁(→血虚+不眠)
このように、方剤構成を診断構造にひも付けて明示すれば、処方は“診断の翻訳”として理解されます。
6. 再診時の“診断更新”とカルテ構造の運用
中医学は“固定的な診断名”を用いないため、再診時には診断構造の再評価(再弁証)が必須です。
その際、初診時カルテに弁証構造が明記されていれば、変化点をピンポイントで確認→処方の加減を調整することができます。
■ 例:再診時の更新カルテ
【再評価】月経周期改善/PMS軽減/苔がやや乾燥 【変化点】血虚が改善、軽度の陰虚化あり 【新証】肝鬱気滞+虚熱傾向 【新治法】疏肝・清熱・安神 【処方変更】加味逍遙散 → 加味逍遙散+知柏地黄丸(加味)
7. 中医カルテテンプレートの応用提案
下記のようなフォーマット化されたカルテ構造を導入すれば、診療の質・教育性・記録の再現性が向上します。
【主訴】 【随伴症状】 【舌・脈】 【弁証(証構造)】 【治法】 【方剤】 【目的別構成】 【評価指標・再診方針】
これにより、診断→治法→処方という「論理の流れ」が明文化され、指導・再処方・他者共有・学習にも活用可能になります。
8. 終わりに
「診断から処方がつながらない」──これは診断精度の問題ではなく、構造的な記録と処方設計の連動不足であることが多いのです。
本稿が、カルテ記載において「四診・弁証・治法・処方」が一本の論理線として結ばれる構造モデルを提供し、臨床の質と再現性を高める一助となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ