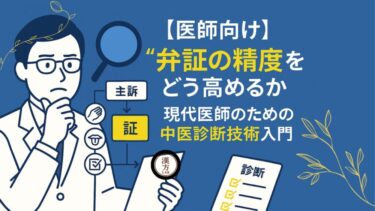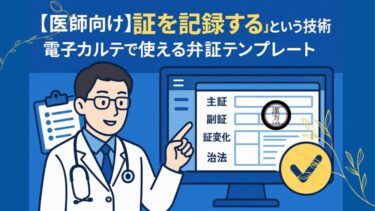目次
舌診から“証の変化”を読み解く──中医学的モニタリングの技術
舌診(ぜっしん)は、中医学における重要な診察技法の一つであり、体内の病機構造を可視的に捉える手段として位置づけられています。
特に、治療経過における「証の変化」を観察するモニタリングツールとして、舌診の精度は中医臨床の質を大きく左右します。
本稿では、舌診の基本所見とその読み方に加え、“治療前後でどこを見るか”という視点から、モニタリング技術としての舌診の活用法を整理いたします。
1. 舌診とは“内証の鏡”である
舌診は望診の一部として行われ、舌体(色・形・潤い)と舌苔(色・厚さ・性質)の観察により、気血津液・臓腑の状態を判断します。
舌は「心の苗」「脾の外候」「全身の縮図」とされ、静的な情報だけでなく、動的変化にも敏感に反応します。
2. 舌診の観察項目と解釈基準
| 観察項目 | 代表所見 | 臨床的解釈 |
|---|---|---|
| 舌体の色 | 淡紅/淡白/紅/紫暗 | 虚証/陽虚/熱証/瘀血 |
| 舌体の形 | 胖大/裂紋/痩小/歯痕 | 水滞/陰虚/血虚/脾虚 |
| 苔の色 | 白/黄/灰黒 | 寒証/熱証/実熱・寒凝 |
| 苔の厚さ | 薄/厚/剥落 | 表証・虚証/実証・痰湿/陰液損傷 |
| 苔の性状 | 膩苔/乾燥/滑潤/剥苔 | 痰湿/津液不足/湿潤充実/胃陰傷耗 |
3. 舌診で証の“変化”を読む:治療前後の観察ポイント
舌診を“変証モニタリング”として使うためには、以下の変化に注目します。
- 舌色の変化:淡→淡紅→紅→紫暗のシフトで、寒から熱、瘀血化を示唆
- 苔の厚さ:厚膩→薄白→消失で痰湿・食積の改善
- 潤いの変化:乾燥→潤沢への移行は陰液回復を示唆
- 裂紋の変化:拡大=津液消耗、縮小=補陰・滋養成功
- 瘀点・瘀斑の出現/消退:瘀血の動態把握に有用
4. 舌診によるモニタリング実例
【例1】補中益気湯を投与した虚証患者
- 初診:舌淡胖+白膩苔(脾気虚+痰湿)
- 2週間後:舌淡紅・苔減少 → 脾気回復傾向
- 治療変更:温胆湯で痰湿をさらに処理
【例2】桂枝茯苓丸による瘀血治療
- 初診:舌紫暗・瘀点多数・舌下静脈怒張
- 1か月後:舌紅暗・瘀点減少 → 活血奏功
- 治療変更:加味逍遙散へ移行(肝鬱主証へ)
5. 舌診記録と連携するモニタリング体制
- 写真記録:自然光下、朝起きてすぐ、毎週1回
- 電子カルテ連携:舌診テンプレート・経過シートとの統合
- 他職種共有:管理栄養士・看護師と連携して変化を共有
- 患者との共有:舌の画像変化を見せることで理解・継続支援に活用
終わりに
舌診は“証を読む技術”であると同時に、“証の変化を追うモニタリング技術”でもあります。
舌は、主観的訴えが得にくい高齢者・在宅患者・認知機能障害のある患者でも使用可能であり、中医学的評価の客観性を支える柱です。
本稿が、診療における“弁証の再評価・修正・適応”のための視覚的・構造的な補助線として、舌診をさらに活かすきっかけとなれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ