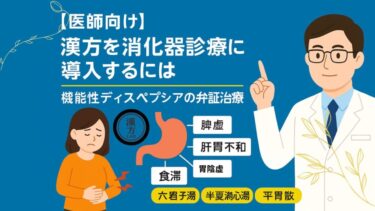不眠症の診方が変わる──“証”によって異なる漢方処方戦略
不眠は現代社会において極めて頻度の高い症候であり、睡眠薬、抗うつ薬、漢方薬などが併用されることも多くなっています。
しかしながら、症状名としての「不眠症」が同一であっても、背景にある身体的・精神的病態は多岐にわたり、治療反応にも個人差が大きいのが実情です。
中医学では、「不眠」を単一の疾患概念ではなく、さまざまな病機(証)によって分類・鑑別し、それに応じて処方戦略を変えるという立場をとります。
本稿では、臨床的にもよくみられる不眠のタイプをいくつか取り上げ、それぞれに対応する方剤の特徴を整理いたします。
“不眠”という症状を分解する視点
中医学的には、「なかなか寝付けない」「途中で目が覚める」「夢が多く熟眠感がない」「眠っても疲れが取れない」などの主訴から、証(体内病態)の鑑別が始まります。
不眠は多くの場合、「心神(しんしん)不寧」と呼ばれる病態に関与しており、五臓六腑のうち「心」「肝」「脾」「腎」のいずれかまたは複数の失調が背景にあると見立てます。
臨床で遭遇しやすい代表的な“証”と処方戦略
| 証(しょう) | 典型的な病態・主訴 | 代表方剤 |
|---|---|---|
| 心脾両虚(しんぴりょうきょ) | 疲労・食欲不振・夢多く浅眠・健忘・動悸 | 帰脾湯(きひとう) |
| 肝鬱化火(かんうつかか) | イライラ・怒りっぽい・胸脇の張り・入眠困難 | 加味逍遙散(かみしょうようさん) |
| 陰虚火旺(いんきょかおう) | 寝つきが悪い・のぼせ・口渇・五心煩熱 | 天王補心丹(てんのうほしんたん) |
| 痰熱内擾(たんねつないじょう) | 夢が多く眠りが浅い・胸苦しさ・痰・苔黄膩 | 黄連温胆湯(おうれんうんたんとう) |
| 心胆気虚(しんたんききょ) | びくっと驚きやすい・不安感・不眠・めまい | 温胆湯、酸棗仁湯 |
こうした分類により、「同じ不眠でも、なぜ異なる漢方が必要になるのか」が構造的に整理されます。
また、問診・舌診・脈診などの情報が証の判別をより確実にする要素となります。
方剤の適応選択と応用例
- 帰脾湯:心脾両虚に用いられる補気補血の代表処方。倦怠感・動悸・不安感が目立つ虚証に適応。
- 加味逍遙散:肝鬱気滞+軽度の熱化。ストレス反応型の不眠や月経前後の睡眠障害に。
- 天王補心丹:陰虚・火旺による中高年女性の不眠。精神疲労・虚熱傾向を伴う場合に用いられる。
- 黄連温胆湯:痰熱内盛。痰の多い人、胸部の不快感、苔厚膩などを伴う場合。
- 酸棗仁湯:虚煩・心神不安・夢多く眠れない。虚弱で感受性の高い患者に検討される。
いずれの方剤も、その適応は単なる「不眠の有無」ではなく、全身の状態や心身のバランス、虚実寒熱の見立てに基づくため、応用にあたっては慎重な問診と見極めが求められます。
終わりに──中医学が提供するもう一つの“見立て”
不眠は、「症状」としては同じでも、病態の背景には多くのバリエーションが存在します。
中医学の“証”に基づく診立ては、そうした多様な背景を構造的に分類する補助的ツールとなり得ます。
西洋薬と漢方薬の併用が一般化しつつある今、医師が「なぜその処方が適応されるのか」を証レベルで理解しておくことは、治療選択の合理性と説明責任の裏付けにもつながります。
本稿が、日常診療における睡眠障害へのアプローチを見直す一助となれば幸いに存じます。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ