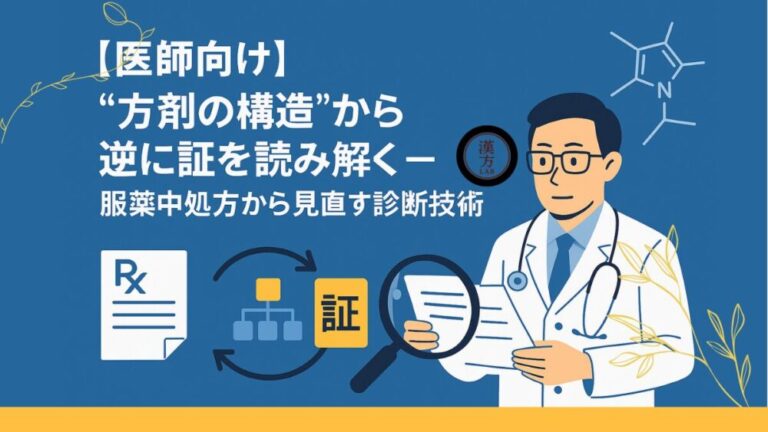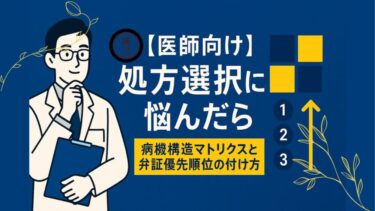目次
“方剤の構造”から逆に証を読み解く──服薬中処方から見直す診断技術
漢方治療においては、「診断(弁証)→処方」という順序が原則です。
しかし、実際の臨床では他院で処方されている漢方薬を引き継いだり、患者自身が自己判断で服用していることもあり、すでに処方が決まっている状態から診断を再構築する必要に迫られることがあります。
本稿では、漢方処方(方剤)の構成生薬・薬理特性から、「この処方が前提としている証(しょう)は何か?」を逆解析し、診断の妥当性を評価・修正する技術を解説します。
1. 方剤構造と証は“セットで構築されている”
中医学において、方剤とは“病機構造に応じて組まれた処方モデル”であり、それ自体が証の写像でもあります。
よって、構成生薬を分析することで、「どのような病機を想定しているか」を読み取ることが可能です。
例:六君子湯(人参・白朮・茯苓・甘草・半夏・陳皮)
- 補気健脾(人参・白朮・茯苓) → 脾気虚
- 燥湿化痰・理気(半夏・陳皮) → 痰湿
- → 仮想証:脾気虚+痰湿(気滞要素軽度)
2. 方剤から証を逆読みする手順
① 構成生薬を分類する
- 補気:人参・黄耆・白朮
- 補血:当帰・地黄・芍薬
- 理気:陳皮・香附子・柴胡
- 活血:川芎・桃仁・牡丹皮
- 化痰:半夏・茯苓・竹茹
- 清熱・瀉火:石膏・黄連・山梔子
② 生薬群から想定される“治法”を明確化する
- 補気+化痰 → 六君子湯型 → 脾気虚+痰湿
- 疏肝理気+補血 → 加味逍遙散型 → 肝鬱+血虚
- 活血+補気 → 桂枝茯苓丸+十全大補湯型 → 瘀血+気虚
③ 治法から想定される証構造を言語化
例:補中益気湯 → 脾肺気虚+中気下陥
3. 処方別:逆読みで見直す代表的な証構造
| 処方名 | 想定される証 | 注意すべきズレ |
|---|---|---|
| 補中益気湯 | 脾肺気虚+中気下陥 | 痰湿が混在していると悪化 |
| 当帰芍薬散 | 血虚+水滞+瘀血軽度 | 実証・瘀血が主であれば逆効果 |
| 加味逍遙散 | 肝鬱+血虚+軽度の虚熱 | 舌膩・痰湿があれば不適合 |
| 十全大補湯 | 気血両虚+寒証+瘀血軽度 | 内熱体質や瘀血主体では重すぎる |
| 桂枝茯苓丸 | 瘀血+血虚+実寒傾向 | 冷えがない・虚証主体では過剰反応 |
4. 処方反応から“隠れ証”を補正する技術
服薬中に現れた副反応・未改善症状を分析し、「足りていない証/合っていない証」を補う視点が重要です。
- 不眠・のぼせ → 補気剤過剰 → 陰虚+虚熱
- 膨満・食欲不振 → 補剤不適 → 胃内停水・痰湿
- 便秘・腹痛 → 活血剤不適 → 実証 or 補血不足
- 咳・痰の残存 → 肺熱未処理 → 清熱化痰の必要性
5. 臨床ケース:方剤から証を読み直した再処方戦略
症例:当帰芍薬散を服用中の月経異常
- 服薬中:冷え・月経血塊・腹痛 → 効果不十分
- 分析:補血+利水は適切、だが瘀血が主証
- 修正:桂枝茯苓丸+芎帰膠艾湯(活血+補血)へ変更
症例:加味帰脾湯で不眠悪化
- 証仮説:心脾両虚
- 所見:舌紅+寝汗+脈細数 → 陰虚+虚熱あり
- 修正:麦門冬湯 or 生脈散を併用(補陰補気)
終わりに
中医診療では「診断から処方を組む」ことが基本ですが、実際の現場では「すでに決まっている処方」からスタートする場面が多くあります。
その際、方剤の構造を冷静に分解・分析し、「この処方はどんな証に対するものか?」を逆に読み解く技術は、再弁証・診断修正・治療評価のすべてに活用できます。
本稿が、方剤を“診断の手がかり”として再活用するための視点を提供し、より構造的な診療設計の一助となれば幸いです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ