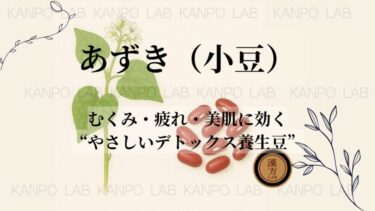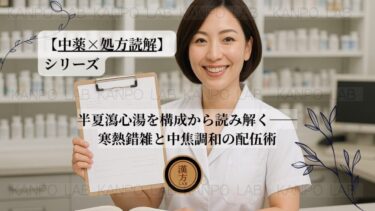目次
中医学的診断テンプレート──問診・舌・脈から証を導くために
中医学では「証(しょう)」に基づく診断が治療方針の根幹を成しますが、その診断には四診(望・聞・問・切)という身体全体を捉える技法が使われます。
本稿では、臨床で活用しやすい「問診・舌診・脈診」の要点を整理し、証の導出に役立つテンプレートとしてまとめました。
1. 中医学における診断の基本:四診とは
- 望診:顔色、舌、体格、動作、皮膚の状態などを観察
- 聞診:声の調子、呼吸音、体臭、口臭など
- 問診:主訴に加え、冷え・のぼせ・食欲・睡眠・便通・月経など全身の状態
- 切診:脈診、腹診、触診
特に問診・舌診・脈診は、証を導くうえで非常に重要な判断材料となります。
2. 問診テンプレート:証を絞り込む7つの視点
- 冷熱:寒がり/のぼせ、冷え性/熱感、冷飲・温飲の好み
- 虚実:疲れやすい/元気すぎて眠れない、舌・脈に変化
- 気血津液:疲労、動悸、めまい、むくみ、口渇、汗、皮膚の乾燥
- 消化機能:食欲、腹部の張り、便通(軟便/便秘)、嘔気
- 睡眠・精神状態:寝つき・夢の有無・途中覚醒、抑うつ・イライラ・不安
- 月経(女性):周期・量・色・塊・痛み・PMSの有無
- 既往・生活背景:疲労蓄積、ストレス、体質・家族歴など
3. 舌診のポイント:色・形・苔から診る
| 所見 | 解釈される証 |
|---|---|
| 舌淡・胖・歯痕 | 気虚・陽虚・水滞 |
| 舌紅・乾燥・裂紋 | 陰虚・熱証 |
| 舌紫暗・瘀点 | 瘀血 |
| 苔白膩 | 痰湿・寒湿 |
| 苔黄厚 | 実熱・湿熱 |
照明は自然光に近いものを使用し、舌先・中央・根本を観察します。
4. 脈診の基本パターン(六部定位)
脈は寸・関・尺に分け、左右で6部位を観察します(例:左寸=心・右寸=肺)。以下は代表的な脈象です。
| 脈象 | 意味 | 関連する証 |
|---|---|---|
| 沈細無力 | 虚証・気血両虚 | 帰脾湯、十全大補湯など |
| 弦 | 緊張・気滞・肝鬱 | 加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蛎湯 |
| 滑 | 痰湿・食滞 | 温胆湯、半夏瀉心湯 |
| 数・洪 | 熱証・実熱 | 黄連解毒湯、白虎湯系 |
5. 活用例:よくある症例別パターン
- 更年期+不眠+焦燥:肝腎陰虚 → 知柏地黄丸、天王補心丹
- PMS+便秘+月経痛:気滞血瘀 → 加味逍遙散+桂枝茯苓丸
- 食欲低下+倦怠感+浮腫:脾気虚+痰湿 → 六君子湯、平胃散
問診・舌・脈から得た情報を「証」に落とし込むと、対応する処方の選定がスムーズになります。
7. 終わりに
中医学における診断技法は、臨床現場において「病気ではないが、明らかに不調がある」状態を整理し、説明し、介入するための優れた補助線となり得ます。
本テンプレートが、診療の一助として、医師と患者の間の理解を深める一端となれば幸いです。