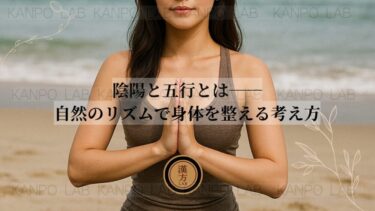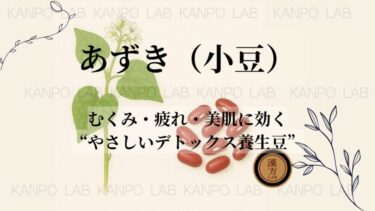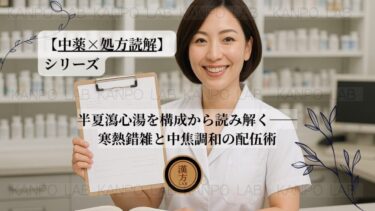「証」ってなに?漢方で体質を見立てる考え方
漢方では、「この病気にはこの薬」という考え方はしません。
かわりに重視されるのが、その人の「証(しょう)」です。
体の状態・体質・不調のパターンをまとめて読み取る「証」という見立て方を知ることで、漢方の世界が一気に分かりやすくなります。
「証(しょう)」とは?
「証」とは、中医学における診断の単位です。
同じ症状でも人によって体質や原因が異なるため、その人ごとに体全体のバランスを見て「証」を立てます。
証の定義(簡潔に)
- 体のバランス状態(気・血・水・陰陽など)
- どこに問題があるのか(臓腑・経絡など)
- どのように病気が進んでいるのか(表裏・寒熱・虚実など)
つまり、証とは「あなたのいまの体の状態」を中医学の言葉で整理したものなのです。
なぜ「証」が重要なの?
漢方では「証」に合った処方を使わないと、効果が出にくいとされます。
たとえば、同じ「冷え性」でも以下のように分かれます:
- 気虚タイプ: エネルギー不足で冷える → 補気の処方(例:補中益気湯)
- 陽虚タイプ: 熱が作れず冷える → 温陽の処方(例:八味地黄丸)
- 血虚タイプ: 血が足りず手足が冷える → 補血の処方(例:当帰芍薬散)
症状だけで判断すると処方を誤りやすく、だからこそ証の見立てがとても大切になるのです。
「証」の基本分類(初心者向け)
中医学では「証」を見立てるために、次のような分類を組み合わせて整理します。
| 分類軸 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 寒熱 | 体が冷えているか熱っぽいか | 寒証/熱証 |
| 虚実 | 体力が不足しているか、過剰な状態か | 虚証/実証 |
| 表裏 | 表面的な症状か、内側の問題か | 表証/裏証 |
これに加えて、「気・血・水」や「臓腑の偏り」「陰陽バランス」なども総合して見立てます。
体質と証の違いって?
「証」は今の体の状態、「体質」は生まれ持った傾向や日常的な傾向を指します。
つまり「証」は変化するもの、「体質」はベースにあるもの、と考えるとわかりやすいです。
例:
体質が「陽虚タイプ」で冷えやすい人でも、夏場に冷たいものを摂りすぎて「寒邪の表証」になることもあります。
まとめ:証を知ることが、漢方を正しく使う第一歩
「自分の証を知る」ことは、漢方のはじめの一歩です。
薬膳・ツボ・養生法すべてにおいて、この「証」が指針になります。
まずは証という“体の見立て軸”を知ることで、漢方はグッと自分ごとになります。
▶ 続けて読む:【体質チェック】9タイプの体質を診断してみよう
【体質チェック】9タイプの体質を診断してみよう 漢方では「この症状にはこの薬」ではなく、その人の体質(=証)に合わせた処方が大切になります。 でも「体質」って何?どうやって調べるの?──そう思った方も多いのではないでしょうか。 ここで[…]