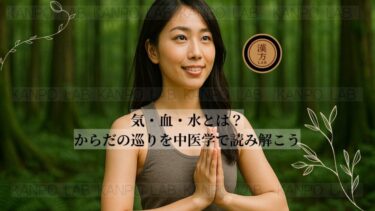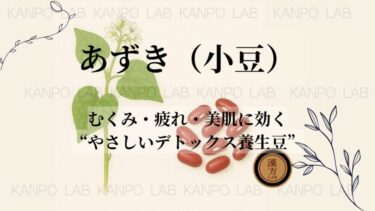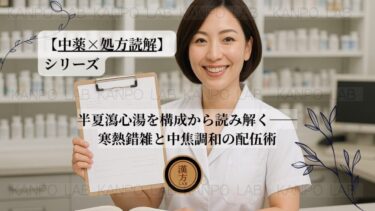慢性炎症と“気虚”──免疫調整としての補中益気湯の臨床応用
慢性炎症を伴う疾患は、現代臨床において極めて多岐にわたります。気管支喘息、アトピー性皮膚炎、潰瘍性大腸炎、リウマチ、がんの術後疲労まで、多くの患者が「病勢はコントロールされているが、回復しきらない」「微熱やだるさが持続する」といった訴えを持ち続けています。
中医学では、こうした状態を「気虚(ききょ)」という視座から捉え、生体の防御力・回復力の低下と見なします。とくに「肺脾気虚」「衛気虚弱」「気陰両虚」などが該当し、全身の恒常性が崩れた状態と理解されます。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)は、こうした“気虚”に対応する代表的な補剤であり、近年では免疫調整の観点からも再評価されています。
本稿では、その臨床適応と作用機序、具体的な使用例を整理いたします。
中医学における“気虚”とは
「気」は、現代的にいえばエネルギー代謝・神経内分泌・免疫系の広義の統合体であり、生命活動を維持する基本要素とされます。
「気虚」とは、この気が「不足」または「機能低下」を起こしている状態で、以下のような所見を伴うことが多くあります。
- 倦怠感・易疲労・脱力感
- 息切れ・食欲不振・軟便
- 風邪をひきやすい(易感染性)
- 声が小さい・話すと疲れる
- 顔色不良・舌淡・脈虚弱
中医学では、「肺は気を主り、脾は気を生む」とされ、肺脾気虚は免疫的防御力の低下と深く関係するとされます。
補中益気湯の構成と薬理的特徴
補中益気湯は『内外傷弁惑論』(李東垣)に由来する処方で、以下のような構成を持ちます:
- 主薬:人参、黄耆、白朮、甘草(補気)
- 助薬:当帰、陳皮(理気・補血)
- 昇陽薬:柴胡、升麻(中気下陥を改善)
現代薬理では以下のような報告があります:
- マクロファージ活性化、NK細胞機能促進、IgA分泌促進
- 副腎皮質ホルモン様作用(ただし穏やか)
- 疲労回復・抗酸化作用・IL-6などのサイトカイン制御
漢方薬の中でも、“抗炎症”と“免疫増強”を同時に実現しうる処方として注目されています。
臨床における適応パターンと症例
■ ① 感染後遷延疲労・咳嗽(例:新型コロナ回復期)
「陰影は改善しているが、咳と疲れが残る」「話すとすぐ息切れがする」
→ 肺脾気虚証。補中益気湯+麦門冬湯の併用も。
■ ② 炎症性腸疾患(軽症維持期の補助)
寛解導入後の慢性疲労、体重減少、下痢便などが持続
→ 補中益気湯単剤または六君子湯との組み合わせ。
■ ③ アトピー性皮膚炎・慢性蕁麻疹の免疫調整
虚弱体質・冷え性・皮膚バリアの回復が遅い例に
→ 小建中湯、十全大補湯との使い分けが鍵
■ ④ 高齢者の慢性疲労・サルコペニア傾向
「検査では異常がない」フレイル初期の疲労・低体温
→ 補中益気湯+八味地黄丸/加味帰脾湯などと組み合わせ
保険適応と使用上の留意点
補中益気湯はツムラ41番として保険収載され、以下の適応病名が活用可能です:
- 虚弱体質、疲労倦怠、食欲不振
- 病後・術後の回復促進
- 感冒後の長引く微熱や咳
使用上の留意点:
- 甘草量がやや多いため、長期使用時はKモニタリングを(特に高齢者・利尿薬併用)
- 湿熱・実熱傾向(赤ら顔・便秘・苔厚黄)の例では注意
- 気虚+陰虚や痰湿併存例では他剤との併用が必要
終わりに
補中益気湯は、単なる「元気をつける漢方」ではなく、免疫低下・炎症遷延・回復力不全という現代医療が苦手とする“半病態”に介入する構造を持っています。
気虚という見立ては、症状をエネルギー代謝・恒常性の機能障害として整理するもう一つの言語であり、抗炎症治療の延長線上における“戻す医療”として、中医学的処方の意義が再評価されつつあります。
本稿が、補中益気湯の臨床的価値と、慢性炎症への中医学的アプローチを検討する一助となれば幸いです。