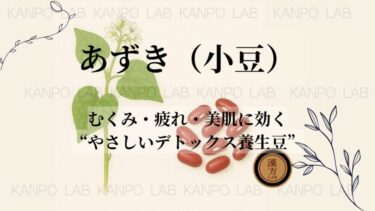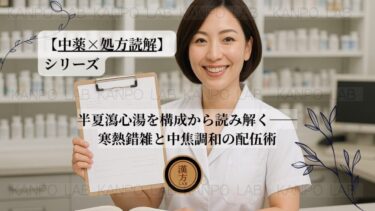目次
診療科:皮膚科|にきび・湿疹・アトピーに使う漢方の体質別アプローチ
肌の不調は、単なる「表面のトラブル」ではなく、体の内側からのサインかもしれません。
にきびが治っても繰り返す、湿疹が季節の変わり目で悪化する、アトピーが治りきらない…。
そんな悩みに対し、塗り薬やステロイドに頼るだけでなく、体質=証に合わせた内側からのケアが必要です。
本記事では、皮膚科領域の代表的な症状であるにきび・湿疹・アトピーに対して、
中医学の体質分類(証)に基づく漢方処方と薬膳養生をご紹介いたします。
中医学における『皮膚』と五臓六腑の関係
皮膚は「肺・脾・肝・腎」の状態を反映すると考えられています。
- 肺主皮毛(はいしゅひもう):皮膚の健康は肺の働きと密接
- 肝血が皮膚を養う:肝の疏泄作用と血の循環が肌の栄養に
- 脾が湿を運ぶ:水分代謝の乱れは湿疹・むくみ・かゆみの原因に
- 腎陰・腎精の不足:皮膚の潤い・弾力を支える根本要素
つまり皮膚の症状は「外因(風・熱・湿・寒)」と「内因(気血津液の失調)」が複雑に関係しており、
表面だけでなく内側から整える体質アプローチが必要になります。
症状別にみる体質分類と証の解説
① にきび(尋常性痤瘡)
にきびは「熱毒」「瘀血」「肝鬱」などが関与することが多く、特に思春期〜20代に多い「実証タイプ」と、
大人に多い「虚実挟雑タイプ」で処方が変わります。
- 熱毒タイプ:顔が赤く、炎症が強く、膿をもつにきび → 清上防風湯、荊芥連翹湯
- 瘀血タイプ:にきびの跡が残る、月経不順あり → 桂枝茯苓丸、桃核承気湯
- 肝鬱+熱タイプ:イライラしやすく吹き出物が出る → 加味逍遥散、竜胆瀉肝湯
② 湿疹・じんましん
痒み・ジュクジュク・赤みなどが目立つ症状で、風湿・湿熱・血虚などが関与します。
- 風湿タイプ:全身に痒みが広がり、湿疹が出たり引っ込んだりする → 消風散
- 湿熱タイプ:赤みや腫れが強く、触れると熱感がある → 竜胆瀉肝湯、黄連解毒湯
- 血虚風燥タイプ:乾燥肌・かゆみ・掻き傷・不眠 → 当帰飲子
③ アトピー性皮膚炎
慢性化・繰り返す・掻破痕が残る…などが特徴。
複数の証が重なることも多いため、「外から抑える」ではなく「内から整える」ことが大切です。
- 湿熱タイプ:じゅくじゅく・黄汁・掻破後の赤み → 黄連解毒湯、消風散
- 肝腎陰虚タイプ:夜間の痒み・乾燥・肌の赤黒さ → 温清飲、滋陰降火湯
- 脾虚湿盛タイプ:下肢や関節の皮膚が厚くなる → 補中益気湯+消風散
代表処方の比較と使い分け
| 処方名 | 適応体質 | 主な症状・対象 |
|---|---|---|
| 清上防風湯 | 熱毒+実証 | 赤く腫れたにきび、炎症性皮膚疾患 |
| 荊芥連翹湯 | 風熱・実証 | 化膿性にきび、慢性化した赤みに |
| 消風散 | 風湿・血虚 | 全身のかゆみ、湿疹、じんましん |
| 当帰飲子 | 血虚風燥 | 乾燥肌・夜間の強い痒み・掻き傷 |
| 温清飲 | 陰虚火旺 | 慢性の痒み・肌の赤黒さ・更年期以降 |
| 竜胆瀉肝湯 | 肝火・湿熱 | 顔面部の吹き出物・脂性肌・赤み |
薬膳素材・生活養生のポイント
熱を冷ます素材(炎症・赤み)
- 苦瓜・蓮の葉・緑豆・ドクダミ茶・山芋・菊花
潤いを補う素材(乾燥・かゆみ)
- 白きくらげ・松の実・くるみ・黒ごま・なつめ・はちみつ
湿を取り除く素材(じゅくじゅく・にごり肌)
- はとむぎ・とうもろこしのひげ・冬瓜皮・陳皮
生活習慣アドバイス:
・睡眠不足は肝血を消耗し、皮膚の回復を妨げます。
・乳製品・甘いもの・揚げ物の摂り過ぎは「湿熱」を増やします。
・ストレスは肝鬱化火を招き、皮膚症状を悪化させます。
まとめ|肌は内臓の鏡。内側からの“証”アプローチを
肌の症状は「見える不調」でありながら、「内臓の乱れ」「体質のアンバランス」のサインでもあります。
塗り薬や保湿ケアだけでなく、根本から整える=証を整えることが、真の改善につながります。