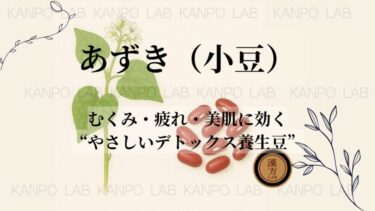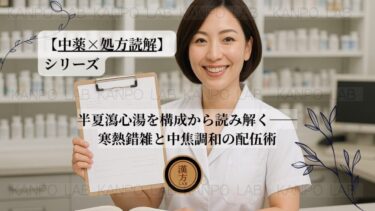目次
呼吸器科|咳・痰・喘息に効く漢方の使い分け
「咳がなかなか止まらない」「痰が絡んで息がしづらい」「季節の変わり目に喘息が悪化する」
これらの悩みに対し、吸入薬や去痰薬だけで根本的に改善されないケースも多く見られます。
実は、これらの症状には体質=中医学でいう「証(しょう)」が深く関わっています。
西洋医学では見えにくい「巡りの悪さ」や「潤いの不足」が原因となっていることもあるのです。
本記事では、呼吸器科に対応する咳・痰・喘息症状を中心に、体質別の漢方処方・薬膳・生活養生を解説いたします。
中医学における『肺』と呼吸器の不調の捉え方
中医学において、「肺」は“気”の循環・防御を司る最もデリケートな臓腑です。
肺が弱ると、外からの風邪(ふうじゃ)や寒さ(かんじゃ)を受けやすく、
内部では「痰」「熱」「乾燥」といった症状が生じやすくなります。
- 肺は嬌臓(きょうぞう):冷えや乾燥、ストレスの影響を受けやすい
- 肺は気を主る:呼吸・皮膚・免疫に関わる
- 肺と脾・腎との連携:痰・水分代謝・陰陽の調和に関係
つまり、咳や痰といった一見単純な症状も、「肺だけの問題」とは限らず、
脾胃や腎との関連、冷え・熱・乾燥などのバランスから読み解く必要があるのです。
症状別にみる体質分類(証)と漢方処方
① 肺熱咳嗽(はいねつがいそう)
症状:黄色い痰・咳が激しい・口が乾く・喉が赤い・微熱傾向
- 麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう):喘息・急性の咳嗽に。
- 五虎湯(ごことう):麻杏甘石湯に陳皮を加え、より喘鳴に特化。
- 清肺湯(せいはいとう):痰が多く、喫煙者や慢性咳嗽に。
② 痰湿阻肺(たんしつそはい)
症状:痰が多い・重だるい・胸がつかえる・朝に症状が強い
- 竹茹温胆湯(ちくじょうんたんとう):痰がべたつくタイプに有効。
- 平胃散(へいいさん):湿気体質で消化機能が落ちている人に。
③ 肺陰虚(はいいんきょ)
症状:空咳・乾燥感・声枯れ・のどの乾き・寝汗・微熱
- 麦門冬湯(ばくもんどうとう):乾いた咳・痰が少ない虚弱タイプ。
- 滋陰降火湯(じいんこうかとう):陰虚+熱症状がある人に。
④ 腎虚咳嗽(じんきょがいそう)
症状:長引く咳・高齢者・足腰のだるさ・疲れやすい
- 八味地黄丸(はちみじおうがん):腎陽虚による冷え+咳に。
- 六味地黄丸(ろくみじおうがん):陰虚+虚熱タイプに。
⑤ 風寒束肺(ふうかんそくはい)
症状:寒気・発熱・透明な痰・くしゃみ・鼻水
- 小青竜湯(しょうせいりゅうとう):水様性鼻汁+咳に。
- 杏蘇散(きょうそさん):風邪の初期+咳にやさしい処方。
代表処方の比較と適応パターン
| 処方名 | 適応体質 | 対象となる主訴 |
|---|---|---|
| 麻杏甘石湯 | 実証・肺熱・喘鳴 | 喘息、風邪後の強い咳 |
| 五虎湯 | 実証・肺熱+気逆 | 咳+ゼーゼー呼吸、声が出にくい |
| 清肺湯 | 痰湿・慢性肺炎 | 粘つく痰・喫煙者の咳・膿性痰 |
| 麦門冬湯 | 虚証・肺陰虚 | 空咳・乾燥咳・声枯れ |
| 滋陰降火湯 | 陰虚+虚熱 | のぼせ・寝汗・咳・口渇 |
| 竹茹温胆湯 | 痰湿・気滞 | 痰が切れない・胃腸虚弱+咳 |
薬膳素材と生活養生のポイント
潤いを補う素材(肺陰虚・乾燥)
- 白きくらげ・梨・百合根・はちみつ・杏仁
痰を排出・巡らせる素材(痰湿・気滞)
- 金柑・大根・陳皮・ミョウガ・ねぎ
温めて肺を守る素材(風寒・冷え)
- 生姜・シナモン・紫蘇・胡椒・にんにく
基本原則:冷たいもの・乳製品・脂っこい食事は痰湿を悪化させるため控えめに。
まとめ|呼吸器トラブルは「体質から」ケアする選択肢も
咳や痰、喘息といった症状に、「この薬を飲めばOK」という絶対的な答えはありません。
なぜなら、その背景にある「体の状態=証」が人によって異なるからです。
だからこそ、自分の体質を知り、それに合った処方や食養生を選ぶことが、
根本的な改善への一歩になると、私は考えています。