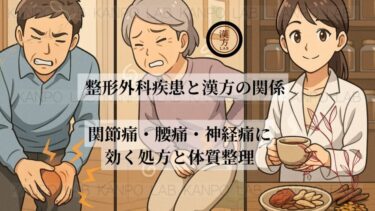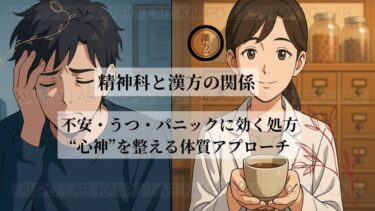認知症予防に注目される漢方とは?|脳の衰えを緩やかに支える東洋医学の知恵
高齢社会が進む中、認知症予防への関心はますます高まっています。
「物忘れが増えてきた」「会話の中で言葉が出てこない」「同じ話を何度もしてしまう」――
そんな“ちょっとした違和感”が、本人やご家族の不安に繋がります。
西洋医学では明確な治療薬がまだ少ない中、東洋医学(中医学)では体質や脳のエネルギー低下を整えるという観点から、早期予防や進行抑制に活用されてきました。
この記事では、認知症の東洋医学的な捉え方、漢方による体質ケア、そして毎日の生活で実践できる薬膳やセルフケアについてご紹介します。
中医学から見た「認知症」とは?
中医学では、認知機能の低下は「脳のエネルギー源(精・気・血)」の不足や巡りの悪化によって起こると考えます。
主な原因と証
- 腎精不足(じんせいぶそく):加齢に伴い脳や神経の働きが衰える
- 気血不足:脳への栄養が不足し、ぼんやり・物忘れが起こる
- 痰濁内停:脳内に老廃物や“痰”が溜まり、意識が曇る
- 瘀血内阻:脳血流が悪くなり、記憶力や判断力が低下する
このように、中医学では「脳の老化=体全体の老化の一部」としてとらえ、体質の調整を通じて脳の働きを守るという発想に立っています。
認知機能を支える代表的な漢方処方
① 杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)
腎精・肝血を補い、目と脳を養う処方。
白髪・視力低下・耳鳴り・健忘がある高齢者に適しています。
② 七福飲(しちふくいん)
高齢者の物忘れや判断力低下、疲れやすさを改善。
市販の健脳漢方としても注目されています。
③ 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
イライラ・落ち着きのなさ・怒りっぽさを和らげ、脳の過敏を鎮める。
BPSD(周辺症状)の緩和にも使われる処方です。
④ 加味帰脾湯(かみきひとう)
記憶力・集中力・精神疲労・不眠など、「気血不足+心脾両虚」に対応。
意欲の低下やうつ傾向にも使われます。
薬膳でできる脳のアンチエイジング
脳を潤し、気血を補う食材
- 黒ごま・黒豆:腎精を補い、脳・骨・髪を強化
- クルミ:補腎+健脳作用の代表食材
- 卵・豚肉・長芋:血と精を補う
- なつめ・クコの実:気血を補い、精神安定に
おすすめメニュー
- 黒豆と長芋の炊き込みご飯
- くるみとクコの実の黒ごま粥
- 鶏むねと山芋の薬膳スープ
生活習慣のポイント
1. 睡眠とリズム
- 23時前の就寝で腎精を養う
- 朝は光を浴びて脳を活性化
2. 運動と巡り
- 1日15分以上の歩行・散歩で血流を促す
- ラジオ体操や太極拳で柔らかく動かす
3. 脳の刺激と養生
- 会話・手仕事・読書などで脳を活性化
- 深呼吸・瞑想でストレスを緩和
まとめ|“まだ大丈夫”と思っている今が、予防のチャンス
認知症の予防において、「早めの体質ケア」こそ最大の備えです。
漢方では、脳を支える腎・脾・心の働きを整えることで、自然に「記憶」「思考」「感情」のバランスを安定させていきます。
「なんとなく最近ぼんやりする…」
「家族のことで気になっている…」
そんな時こそ、漢方と薬膳でできる脳のケアを取り入れてみませんか?