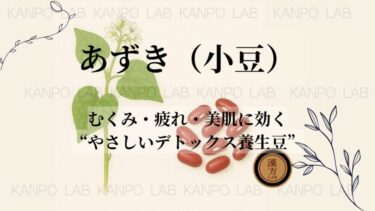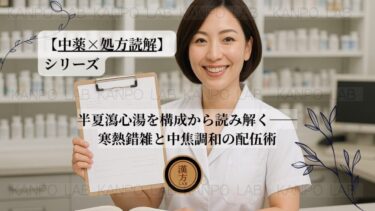不眠が続いています。市販薬と漢方、どちらがよいですか?
「寝つけない」「夜中に目が覚める」「朝すっきり起きられない」──こうした不眠のお悩みは、多くの方にとって深刻な日常の問題です。
ご相談でも特に多いのが、「市販薬を試してみようか迷っているけれど、できれば漢方で改善したい」という声。
この記事では、不眠のタイプと原因を整理したうえで、市販薬と漢方の違い・使い方・選び方を丁寧にご紹介いたします。
まずはご相談内容の背景
30代女性の方より、こんなご相談がありました:
相談:「ここ数ヶ月、寝つきが悪く、夜中も何度も目が覚めてしまいます。
病院に行くほどではないけれど、このままでは日常生活に支障が出そうで…。
ドラッグストアで不眠対策の市販薬を見かけましたが、漢方のほうが体にやさしそうで気になっています。」
このようなケースは決して珍しくありません。不眠は人それぞれに原因が異なり、「眠れない」という表面的な症状だけを抑えても、根本改善にはつながらないことが多いのです。
市販薬の不眠対策:どんな特徴がある?
一般的な不眠用の市販薬(ドリエル、ネオディなど)は、抗ヒスタミン系や精神安定作用のある成分が含まれており、一時的に眠気を誘発することを目的としています。
こんな特徴があります:
- 即効性がある(30分~1時間以内で眠気がくる)
- 短期的な対症療法向き
- 翌朝の眠気や倦怠感が残ることも
- 継続的な使用は推奨されない
「今夜だけは寝たい」「一時的なストレスで眠れない」といった場面には有効ですが、体質や根本原因へのアプローチは行われません。
漢方による不眠の改善アプローチ
中医学では不眠は「心(しん)」の乱れ、「肝(かん)」の鬱滞、「陰虚」「気虚」などの失調が背景にあるとされます。
つまり、心身のバランス全体を整えることで、自然な眠りを取り戻すというのが漢方の基本的な考え方です。
代表的な漢方方剤と体質別アプローチ
- 抑肝散(よくかんさん):神経が高ぶりやすいタイプに。小児の夜泣きにも。
- 加味逍遥散(かみしょうようさん):女性のイライラ・PMSを伴う不眠に。
- 酸棗仁湯(さんそうにんとう):心の不安・夢が多い・眠りが浅いタイプに。
- 桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう):緊張やストレスが原因の不眠に。
これらの処方は、「不眠」という共通の症状に対しても、人によって全く異なるアプローチが必要であることを示しています。
漢方 vs 市販薬:選び方のポイント
| 比較項目 | 市販薬 | 漢方薬 |
|---|---|---|
| 即効性 | ◎ あり(30~60分) | △ 継続的に効果が出る |
| 体質対応 | × 画一的 | ◎ 個人の体質に合わせる |
| 副作用 | △ 倦怠感・眠気残り | ◎ 比較的少ない(まれに胃もたれ等) |
| 継続性 | × 推奨されない | ◎ 体質改善に向く |
セルフケアも取り入れてみましょう
不眠の改善は、生活習慣・食事・心のケアといった複合的な取り組みが重要です。以下のようなセルフケアも併用すると効果的です:
- 毎朝の光浴(体内時計のリセット)
- 夕食は就寝3時間前までに済ませる
- スマホ・PCのブルーライトを避ける
- 白湯・はちみつ・ナツメ茶などで心を整える
- 薬膳素材:百合根、ナツメ、酸棗仁など
私の立場から、あなたに伝えたいこと
薬剤師 × 国際中医師の立場から私がいつも意識しているのは、「その方の生活と体質にあった提案をすること」です。
不眠はただの症状ではなく、心身の声です。だからこそ「とりあえず市販薬」ではなく、「なぜ眠れないのか?」を一緒に探ることが大切だと思っています。
まとめ|市販薬と漢方、それぞれの役割を知る
- 市販薬は短期的に「眠らせる」作用
- 漢方薬は中長期的に「眠れる体に整える」作用
- 体質と生活習慣を見直すことが、根本改善につながる
「眠れない夜に振り回される毎日」から、「自然に眠りにつける体質」へ。
ご自身の状態に合った対策を選び、無理のない方法で一歩ずつ改善していきましょう。