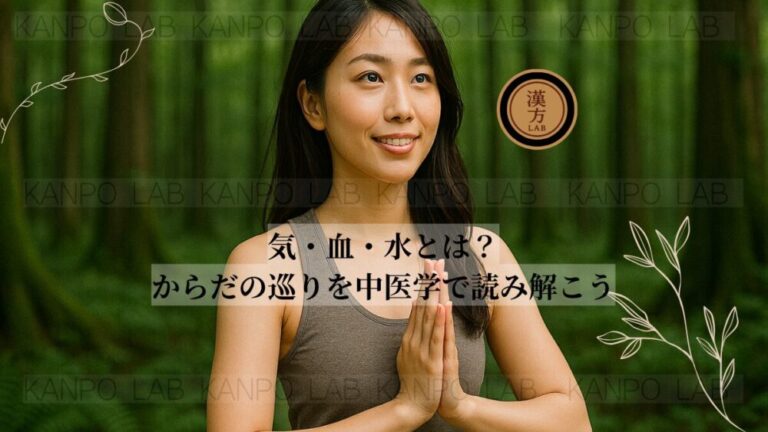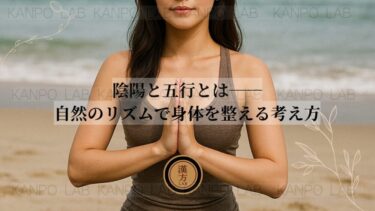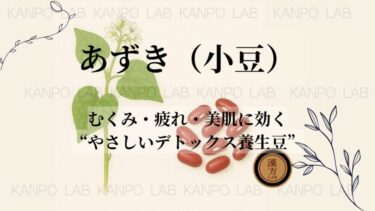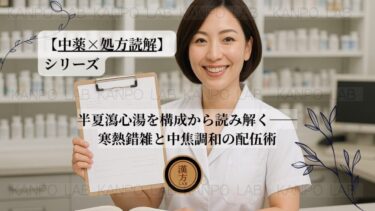気・血・水とは?からだの巡りを中医学で読み解こう
「漢方では“気・血・水”のバランスが大切と聞いたけど、実際どういう意味なの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、ここでは中医学の基本三要素「気・血・水」について、役割とバランスの崩れがもたらす不調の例をやさしく解説します。
気(き)とは:からだと心を動かすエネルギー
「気がめいる」「元気」「やる気」など、私たちの日常にも「気」という言葉はたくさん登場します。
中医学における「気」は、からだを動かすエネルギーそのもの。見えないけれど、生命活動のすべてを支える重要な存在です。
気の主な働き
- 体温を維持する
- 血や水を巡らせる
- 病気を防ぐバリア機能(衛気)を担う
- 臓腑や器官を動かす原動力になる
気が不足すると…
- 疲れやすい、声に力がない
- 風邪をひきやすい
- 冷えやすい、下痢しやすい
血(けつ)とは:栄養と潤いを運ぶ“赤いエネルギー”
「血(けつ)」は現代の「血液」に近い考えですが、それだけではありません。中医学では、からだに栄養と潤いを届ける働き+精神活動を安定させる役割も担っています。
血の主な働き
- 全身に栄養と潤いを供給
- 肌・髪・爪を健康に保つ
- 心を安定させ、眠りの質を高める
血が不足すると…
- 顔色が悪い、めまいがする
- 不眠、夢が多い、情緒不安
- 肌や髪が乾燥しやすい
水(すい)とは:体の中をめぐる体液の総称
「水(すい)」は、リンパ液・消化液・関節液・尿など、血以外のすべての体液を含むとされます。
中医学ではこの水が適切に作られ、巡り、排泄されているかがとても重要です。
水の主な働き
- からだに潤いを与え、関節や皮膚を守る
- 熱を冷ます、毒素を排泄する
- 消化吸収のサポート
水が滞ると…
- むくみ、頭重、めまい、吐き気
- 関節のこわばり
- 痰がからむ、湿疹が出やすい
気・血・水のバランスが大切な理由
「気」は動かすエネルギー、「血」は栄養、「水」は潤い──この3つがバランスよく“めぐっている”ことが、健康の基本とされています。
こんな不調は「気・血・水」の乱れがサインかも
- 疲れやすい・やる気が出ない → 気虚
- 冷えやすく月経不順 → 血虚
- むくみ・痰・湿疹 → 水滞
漢方では、あなたの不調を「病名」ではなく、この気・血・水のどこが乱れているかで見立てて処方します。
まとめ:まずは“巡り”を意識することから
健康とは「何も悪くない」状態ではなく、「全体が調和し、スムーズに巡っている」こと。
気・血・水というシンプルなフレームで自分のからだを見直すだけでも、漢方はぐっと身近になります。
▶ 続けて読む:陰陽と五行とは|自然のリズムで身体を整える考え方
陰陽と五行|自然のリズムで身体を整える考え方 「陰陽」「五行」という言葉を聞いたことがありますか? これらは中医学(漢方)の根本的な世界観を表すものであり、体質・季節・感情・臓腑すべてのベースになる考え方です。 この記事では、自然のリ[…]